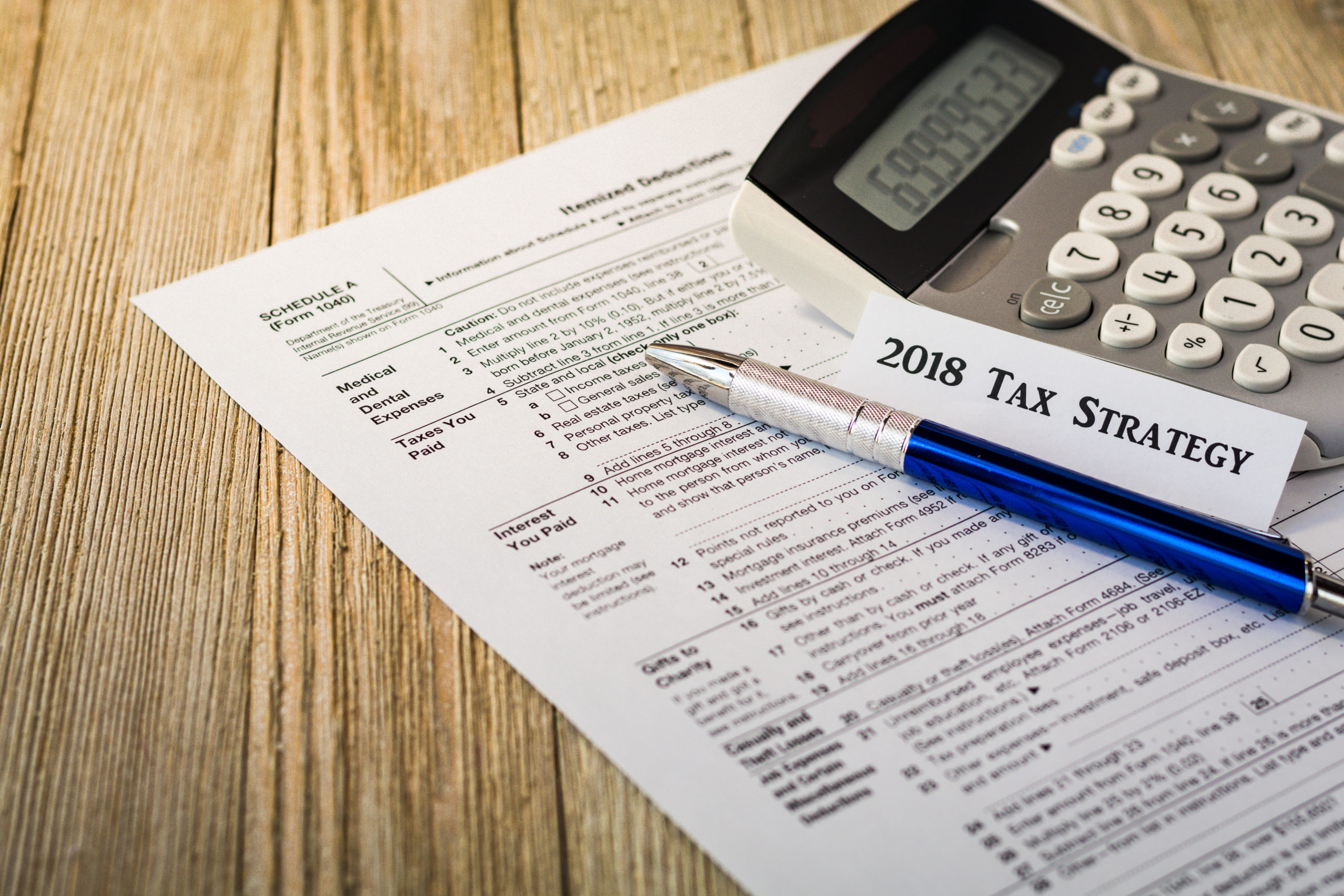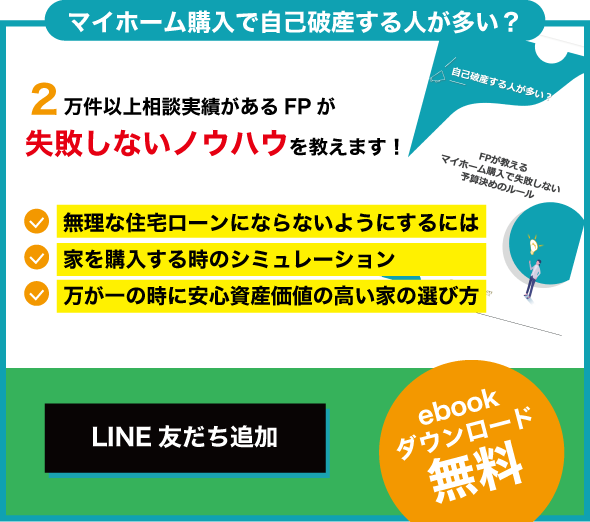家を買うタイミングは?後悔しないために把握すべき知識まとめ【2025年版】

家を検討している方の中には、次のような悩みや疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。
- ✅住まいを手に入れるベストな時期はいつ?
- ✅みんなどのタイミングで決断しているの?
- ✅2025年は本当に買い時なの?
マイホーム購入のタイミングは、多くの人にとって大きな悩みの一つです。
そこで今回は、年齢や収入、貯蓄額などの近年の統計データをもとに、無理のない判断ができる目安や時期について詳しく解説します。
また、事前に考えておくべき重要な注意点についても紹介していますので、後悔のない選択をするためにも、ぜひチェックしてみてください。
データ別で考える家購入のタイミング

この項目では、「年齢」や「収入」などの要素ごとに、不動産購入をどのような視点で考えるべきか、その条件やおすすめのタイミングについて解説します。ご自身の年齢やライフステージ、現在の状況を踏まえて、住宅購入の目安としてにして参考にしてみてください。
(1)自分の「年齢」で考える
国土交通省が発表した「令和5年度 住 宅 市 場 動 向 調 査 報 告 書」を参考に解説すると、住宅購入のタイミングを世帯主の年代別で見た場合「30代後半~40代前半」が最も多い結果となっています。
引用:令和5年度住宅市場動向調査報告書「世帯主の一次取得者」
また、購入者の平均年齢は住宅のタイプによっても異なり、最も低かったのは分譲一戸建て住宅で「36.6歳」、最も高かったのは中古マンションの「44.2歳」でした。
多くの金融機関では、住宅ローンの完済年齢を79歳までとしています。
そのため、35年ローンを組むには、44歳までに借りる必要があります。
つまり、購入時の平均的な年齢である「30代後半~40歳前半」というのは、返済期限を最大限に活用できるという点で理にかなっています。
さらにこの年齢層は、結婚・出産・子どもの入園といった大きなライフイベントが一段落し、生活の基盤が整いやすい時期でもあります。
これらの要素を踏まえると住宅購入の買い時として、妥当なタイミングと言えるでしょう。
基本的に、マイホームの購入は早ければ早いほどメリットが大きいといえます。
賃貸で過ごす期間が短いほど、家賃などの住居費を抑えることができます。
たとえば、10年間家賃10万円で暮らせば、支払い総額は約1,200万円になります。家を早く買えば、リフォームや修繕費用(10~15年ごとに200~300万円程度)を加味しても、長期的には支出を抑えられる可能性が高いです。
「何歳で購入するのがベストなの?」と迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
(2)「年収」で考える
次に、一次取得者(はじめて物件を購入する人)の平均世帯年収について見ていきましょう。
国土交通省の資料によると、令和3年度は「600万円台~800万円台」の世帯が多い結果となっています。しかし、令和5年度になると中古戸建・集合住宅、そして分譲戸建・集合住宅では、「400万円台~600万円台」の世帯が最も多い結果へと変化しています。
引用:令和5年度住宅市場動向調査報告書「世帯年収」
この調査によると、中古戸建住宅購入者の世帯収入は「650万円」と最も低く、最も高かったのは分譲マンション購入者で「840万円」でした。
住宅のタイプによって、200万円前後の差があることがわかります。
また、注文住宅購入者の世帯年収に注目すると全国平均が808万円に対し、三大都市圏では924万円と、さらに高い傾向が見られました。
背景として、東京の地価は2013年以降、明確に上昇を続けており、それに連動して住宅価格も大きく値上がりしています。
それでも東京は全国的に世帯年収が高いため、地価と住宅価格が上昇していても購入できていると考えられます。
ここまではあくまで平均的なデータに基づいた説明です。実態(当社調査)では、世帯年収の7倍程度の物件を購入しているケースが多いです。
たとえば、世帯年収が600万円なら4200万円、1000万円なら7000万円といった具合です。
大切なのは、ご自身の年収やライフプランに合わせて無理のない範囲で物件を選ぶことです。
家を購入するときの年収についてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ下記の記事も参考にしてみてください。
(3)「家族構成」で考える
家族構成では、家のタイプによって傾向が異なることがわかっています。
国土交通省の資料によると、居住人数は「2人~4人」が多いというデータが見られました。
引用:令和5年度住宅市場動向調査報告書「居住人数」
具体的には、同調査によると、中古マンションでは「2人世帯」が最も多く、分譲戸建や注文住宅では、子どもが生まれた後の「3人前後」の世帯が多い傾向にあります。
これは、都市圏にマンションが集中していることによるものです。
こうした背景から、都市部では資産性が高く売りやすい物件を重視する人が、結婚を機に1LDK〜2LDK程度のマンションを購入し、子どもが増えた(もしくはある程度成長して部屋が必要になった)タイミングで住み替えを検討するケースが比較的多く見られます。
このような家族構成のデータを参考にしながら、ご自身にあった家のタイプを選んでみるのも一つの方法です。
(4)「子どもの年齢」で考える
マイナビニュースのデータによると、住宅購入時の子どもの年齢については「妊娠前」が「30.5%」と最も多い結果となっています。
次に多かったのは「3~5歳」で「27.7%」、続いて「0~2歳」が「14.5%」という結果でした。
このデータから、住まい選びのきっかけは結婚後から子どもが生まれる前後に集中していることがわかります。
家族計画とあわせて、住宅購入を考える人が多い傾向にあると言えるでしょう。
1位「妊娠前」(30.5%)
2位「3~5歳」(27.7%)
3位「0~2歳」(14.5%)
4位「6~8歳」(10.5%)
5位「12歳以上」(9.2%)
6位「妊娠中」(4.3%)
7位「9~11歳」(3.4%)
引用:マイナビニュース
最も多かった「妊娠前のタイミング」での住宅購入については「子どもがまだいないほうが引っ越しがしやすい」といった考えをもつ人が多いようです。
また、人によっては「子どもが生まれる前に生活の拠点をしっかり決めておきたい」という理由から、早めに住宅を購入するケースも見られます。
さらに、子どもが生まれると、これまで住んでいた賃貸住宅では手狭に感じることも、購入を考えるきっかけの一つとなっています。
今後お子さんを考えている方は、こうした傾向も参考にしながら住まいの計画を立ててみてはいかがでしょうか。
(5)「貯金額」で考える
PR TIMESの「いくら貯金できたら家を購入したいか」というアンケートによると「1,500万円」と回答した人が最も多い結果となりました。
引用:PR TIMES
「わからない/特にない」と回答した人は「47.2%」と全体の約半数を占めています。
この回答が多く見られる層に注目することで、より実態に近い傾向がみえてきます。
実際に相談を受けていると、東京のような都市部でも、十分に資金を貯めてから住宅を購入する人はごく一部にとどまっているのが現状です。
多くの場合、諸費用として200〜300万円程度、さらに少しの自己資金を加えた合計400〜500万円ほどを用意し、そのタイミングで購入に踏み切るケースが一般的です。
自己資金が少ない場合でも、「諸費用ローン」を利用すれば購入は可能ですが、このローンは住宅ローンに付随する諸費用にしか使えません。
そのため、家具購入や引っ越し費用などに備え、別途200万円程度のゆとり資金を確保しておくことが望ましいでしょう。
さらに、親からの援助によって住宅購入資金を賄う場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度もあります。こうした制度を活用すれば、購入のハードルを下げることも可能です。
また、「24.1%」の人(4人に1人)は1,500万円前後を貯めてから購入したいという回答です。
物件価格以外にも、諸費用などさまざまな支出があるため、余裕をもった資金計画を立てたいと考える人が多いのでしょう。
続いて多かったのは「1,000万円以上1,500万円未満」という回答でした。このアンケート結果からも、住宅購入には多額の貯金が必要だと感じている人が多く、少額の頭金では不安だと考えている傾向が見て取れます。
なお、このアンケート結果はあくまでも一つの目安であり、「1,000万円以上の貯金がないと家を買ってはいけない」というわけではありません。ご自身のライフプランや資金計画に合わせた判断が大切です。
(6)住宅ローンでの「金利」で考える
「金利が上がったらどうしよう」と不安になる方も多いかもしれません。
でも、実際にはそこまで大きな影響が出るわけではありません。
たとえば、5,000万円を35年ローンで借りて、現在の変動金利(0.4%)でスタートしたとします。
この場合、毎月の返済額は約12.7万円。
仮に10年後に金利が1.4%まで上昇しても、その時点での残高を元に再計算された返済額は約14.4万円となり、月々の増加はわずか約1.6万円程度です。
これは、ちょっとした家計の見直しで対応できる範囲であり、「金利が上がるから今はやめておこう」と過剰に心配する必要はありません。
むしろ、「金利が多少上がったとしても無理なく返済を続けられるかどうか」をライフプランから見極め、買ってもよい金額の上限を知った上で購入することが判断ポイントになります。
ライフイベントで考える家購入のタイミング
ここからは、ライフイベントの変化に応じた家購入のタイミングについてご紹介します。
結婚や出産、親との同居など、さまざまなライフステージをきっかけに住宅購入を考えるケースが多く見られます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてみてください。
(1)結婚したタイミングで購入する
「結婚」はライフステージが大きく変わるタイミングの一つです。
このタイミングで家を購入する人は多く、独身時代は賃貸マンションで同棲していたカップルでも、結婚を機にマイホームをもちたいと考えるケースは珍しくありません。
例えば、30歳ごろに住宅ローンを組めば、35年ローンでも65歳の定年までに完済することが可能です。この点は、早めに購入するメリットと言えるでしょう。
ただし、結婚後に家を購入する場合は、将来的な転勤や転職などライフプランの変化も見据えて身長に計画を立てることが大切です。
(2)子どもが生まれたタイミングで購入する
「子どもが生まれたタイミング」は、ライフステージが大きく変化する節目であり、住宅購入を考えるきっかけとして非常に多いケースです。
出産前は将来の生活やライフプランが描きにくく、どのような住まいが自分たちに合っているのかイメージしづらいという声もよく聞かれます。
しかし、子どもの人数や性別がわかるようになると、必要な間取りや立地条件などを具体的に検討しやすくなります。
たとえば、「近くに学校や公園があるか」「治安は良いか」といった、子育てに適した環境かどうかを重視する視点が加わることで、住宅選びにもより納得感が生まれます。
(3)親と同居をはじめたタイミングで購入する
高齢の親と同居するために住宅購入を検討するケースも見られます。
たとえば、「今のマンションにはエレベーターがなく移動が大変」「将来を見据えてバリアフリーの住まいにしたい」といった理由から、新たな住まいを探す人も増えています。
また、二世帯住宅にすることで、共働き夫婦にとっては育児のサポートを得やすくなったり、生活費を効率よく抑えるメリットもあります。
親からの資金援助を受けて購入する人も多く、実は“家を買いやすいタイミング”のひとつといえるかもしれません。
(4)子どもが独立したタイミングで購入する
子どもが進学や就職で家を離れると、家の広さや使われていない部屋が気になりはじめる方も多く見られます。
これまで家族でにぎやかに暮らしていた住まいも、空き部屋が増えると、掃除や管理の負担を感じやすくなります。
現在の暮らしに対して家が広すぎると感じたり、将来を見据えて安心して暮らせる住まいへ住み替えを考えるようになるのは自然な流れです。
こうした背景から、子どもの独立をきっかけに、新たな住まいを検討する人が増えています。
ライフステージの変化に合わせて、これからの人生をより快適に、心地よく過ごすための住まい選びが注目されています。
(5)定年退職したタイミングで購入する
定年退職という人生の節目を迎えると、働き方だけでなく、日々の暮らしのリズムも大きく変わります。
仕事中心だった生活から一転し、自宅で過ごす時間が増えることで、住環境に対する意識も自然と高まっていきます。
たとえば、通勤の利便性を重視して選んだ立地が、今の生活には合わなくなったり、広すぎる家や段差の多い間取りが、将来の体力や健康面で不安材料になることもあります。
これからの自分に合った、より快適で安心できる住まいの購入を考えるのです。
このように、ライフステージの変化は、住宅購入を検討する大きなきっかけになります。
ご自身のライフプランに合わせて、タイミングを見極めることが大切です。
購入のきっかけとなったタイミング

ここからは、実際に家購入のきっかけとなったタイミングについてご紹介していきます。
たとえば、「お金に余裕が出てきたタイミング」や「社宅の退去が決まったタイミング」などが購入のきっかけとして挙げられます。
こうした具体的な状況ごとに、どのような理由で家購入を決意する人が多いのか、詳しく解説していきます。
(1)社宅の退去が決まったタイミング
まずは「社宅の退去が決まったタイミング」で家を購入するケースです。
例えば、将来的に社宅に住めなくなることがわかり、退去に備えてマンション購入に踏み切るというパターンが見られます。
また、家賃補助や住宅補助がなくなるタイミングで家購入を検討する人もいます。
社宅にお住まいの方から住宅購入の相談を受ける際、「みんなどうやってこんなに大きな住宅ローンを払っているんですか?」と驚かれることがあります。
これは、社宅に住んでいた間は居住費が非常に抑えられていたため、その感覚のまま生活を続けた結果、知らず知らずのうちにエンゲル係数(食費などの生活費の割合)が上がってしまっていることが多いからです。
一方で、「社宅だからこそ今のうちに貯金をしておこう」と考え、会社の補助分をしっかり貯蓄に回している人は、住宅購入のタイミングでも「想定通りです」と冷静に対応され、しっかりと資金も貯まっている傾向があります。
つまり、社宅にいる間にエンゲル係数などの生活コストを意識しながら過ごすことも、家の購入ハードルを下げるポイントになるのです。
いずれにしても、退去期限までにできるだけ頭金を用意しておくと、住宅ローンの借入額が抑えられるため、月々の返済負担も軽減できておすすめです。
(2)昇給などお金の余裕ができたタイミング
昇給や昇格によって年収が増えると、住宅ローンの審査に通りやすくなり、融資額を増やせる可能性が高まります。
しかし、昇給と言ってもどのくらい増えれば家計に余裕が出るのか、具体的にイメージできる人は少ないかもしれません。
現在では、毎月の手取りが1万円前後増える昇給が一般的ですが、この程度の収入増でも、月々の住宅ローン返済の負担を軽減し、生活に少し余裕が生まれる場合があります。
例えば、毎月12万円のローン返済があったとしても、昇給で収入が増えれば「無理なく返済できそうだ」と感じる人が増えるでしょう。
昇給による収入の増加は、単に借入可能額が増えるだけでなく、購入後の生活を安定させるためにも大きな安心材料となります。
(3)相場や金利が変動したタイミング
「相場や金利が変動したタイミング」で家購入を決断するケースも多くあります。
住宅価格が上昇する前や、低金利により住宅ローン負担が少ない、不動産価格が翌年以降も上昇すると感じた時に、「今が買い時だ」と判断して購入に踏み切る人がいます。
2008年のリーマンショック以降、世界的な低金利により低金利が続いていたため、金利が安い変動金利で組む人が増加していました。
ですが、2024年以降、少しずつ金利が上がり始めたことから、「将来的な返済負担を抑えるために早めに固定金利で借りよう」という動きが増えてきました。
また、円安、海外の政治不安等により海外需要はまだまだあります。
エリアによるところもありますが、「今後さらに価格が上がる前に購入しておきたい」と考える人も少なくありません。
相場や金利の動きを冷静に見極めながら、自分たちにとって無理のないタイミングで決断することが大切です。
焦りすぎず、将来の資産価値やローン返済計画もあわせて考えていきましょう。
(4)親などに家購入を勧められたタイミング
親や知人に勧められた影響で、家購入を決断したというケースも少なくありません。
それまで家購入を考えていなかった人でも「住宅ローンを組むなら早い方がいい」と親に言われ、購入に踏み切ったということもあります。
また、「子どもに資産を残しておきたい」という親心から勧められることもあるでしょう。
親からのアドバイスを参考にするのもよいですが、自分自身のライフプランに合っているかどうか、しっかりと見極めた上で判断することが大切です。
(5)賃料を払うのが勿体無いと思ったタイミング
「家賃を支払うのがもったいない」と感じたタイミングで、家購入を決断する人も多くいます。
賃貸住宅の家賃や共益費、更新料、駐車場代などと住宅ローンの返済額を比較した際、持ち家の方が負担が軽いと感じたケースも珍しくありません。
また、資産価値が落ちにくい物件であれば、将来売却して利益を得ることも期待できますし、賃貸に出して高い家賃収入を得る可能性もあります。
賃貸と持ち家、どちらが自分に合っているのか、冷静に見極めた上で選びましょう。
なお、賃貸と購入、どちらが得なのか迷っている方は、下記の動画も参考にしてみてください。
家購入のきっかけは、人それぞれさまざまです。
社宅の退去や、昇給による収入アップ、相場や金利の変動、親からのアドバイス、そして家賃を払い続けることへの疑問など、ライフスタイルや環境の変化が後押しするケースが多く見られました。
いずれのタイミングにしても、「自分たちにとって無理のない資金計画が立てられるか」「ライフプランに合った住まい選びができるか」という視点を持つことが大切です。
焦らず、自分たちにとってベストなタイミングを見極めて、納得のいく家探しをしていきましょう。
家を買ってはいけないタイミングは?
家の購入は、人生でも特に大きな経済的決断のひとつです。
しかし、購入のタイミングを誤ると、思わぬ負担や後悔を招くことになりかねません。
特に、以下のような時期には慎重な判断が求められます。
ライフイベント直前の時期
転勤や転職、結婚や出産といったライフイベントの予定が近い時期は、住宅購入を急ぐべきではありません。
たとえば、転職や転勤によって勤務地が変わると、通勤時間や生活環境の希望条件が大きく変化します。購入後に「もっと通勤に便利な場所にすればよかった」と後悔するリスクがあります。
また、結婚や出産により家族構成がまだ、はっきりと固まっていない時も、必要な間取りや周辺環境に求める条件が変わるため、将来のライフプランがある程度固まるまで購入を待つ方が安心です。
収入が安定していない時期
転職直後や独立開業したばかりの時期など、収入がまだ安定していない場合も住宅購入は控えた方が無難です。
住宅ローンの審査では、安定した収入が重視されるため、転職直後では希望通りの融資条件を得られない可能性があります。
仮にローン審査が通ったとしても、収入変動リスクを抱えたまま長期の返済を続けるのは、家計に大きな負担となります。
大きな出費が重なる時期
住宅購入だけでなく、結婚式、出産、子どもの進学、親の介護といった大きな出費が重なる時期も要注意です。
物件価格以外にも、仲介手数料や登記費用、各種税金などで数百万円単位の諸費用がかかります。
さらに、購入後もリフォーム費用や固定資産税、修繕積立金など、継続的な支出が発生します。
これらを事前に見積もったうえで、十分な資金余力がない場合は、無理に購入を進めるべきではありません。

2025年は家を購入するタイミング?

結論から言えば、2025年は“自分たちのライフプランや資金計画が整っているのであれば”購入を前向きに検討できる年と言えるでしょう。その理由は、以下の通りです。
物件の売却増加による選択肢の拡大
近年、後期高齢者の増加により、「相続による売却」や「住み替えによる空き家化」が進んでいます。
その結果、特に郊外や地方を中心に市場に出回る物件が増えており、条件に合った住まいを探しやすくなっている面もあります。
一方で、人気エリアや利便性の高い地域では依然として物件争奪が続いており、「買い手有利」と言えるのは立地や物件の種類によって異なります。
購入を検討する際は、物件の状態や修繕費用も含めて総合的に判断することが大切です。
依然として低水準の住宅ローン金利
2024年にマイナス金利政策は解除され、利上げも実施されましたが、それでも住宅ローン金利は比較的低水準を保っています。
特に、変動金利型ローンでは、年0.6%前後と、依然として借入コストを抑えた住宅購入が可能です。
加えて、住宅ローン控除などの支援制度も引き続き充実しており、購入を後押しする環境が整っています。
住宅購入のタイミングは、ライフプランの安定、収入状況、金利動向、市場環境、資金余力といったさまざまな要素を総合的に判断することが大切です。
焦らず、冷静な視点で最適なタイミングを見極めましょう。
「フラット50」という住宅ローンの登場
従来の最長35年ローンよりもさらに長期の返済が可能になることで、若い世代にとって月々の支払い負担を抑えながら住宅を取得しやすくなる可能性があります。
ただし、返済期間が長くなることで総返済額が増える点や、将来的なライフイベントとのバランスも慎重に見極める必要があります。
2025年が「買い時」かどうかは、制度や相場だけでなく、自分たちのタイミングに合っているかどうかが最も重要な判断基準です。
家購入の前に考えておきたい6つのポイント

家を購入することは、人生でも特に大きな経済的決断です。失敗を防ぐためには、事前の準備と確認がとても大切です。
ここでは、マイホーム購入前に押さえておきたい6つの重要ポイントを紹介します。これらをしっかり考えたうえで、納得して家探しを進めましょう。
(1)「一戸建て or マンション」どっちにする?
家を選ぶ際に多くの人が迷うのが、「一戸建て」と「マンション」のどちらにするかという点です。
それぞれの特徴を比較してみましょう。
一戸建ての特徴
一戸建ては、特に家族の人数が多い方や、空間のゆとりを求める方に向いています。
広いリビングや複数の部屋があれば、家族全員がストレスなく過ごせるほか、庭があればガーデニングやバーベキューなど、屋外の楽しみも増えます。
ただし、建物や外構、庭の管理はすべて自己管理が必要です。修繕費も定期的に発生し、タイミングや業者の選定も自分で行わなければなりません。
その分、マンションのような毎月の管理費や修繕積立金は不要で、計画的に準備していればトータルコストを抑えることも可能です。
また、隣家との距離があるため騒音トラブルが起きにくく、静かに暮らしたい方にも適しています。
建売住宅という選択肢
注文住宅ほどのこだわりはなく、手頃な価格で一戸建てを購入したい方には建売住宅が適しています。すでに建築済みまたは建築中の住宅を購入できるため、完成物件を見てから判断できる安心感があります。
土地と建物がセットになっており、費用が明確で、入居までの期間も短い点がメリットです。
反面、間取りや仕様があらかじめ決まっているため、細かな要望には応えにくいというデメリットもあります。
マンションの特徴
マンションは、特に立地や生活の利便性を重視する方に向いています。
多くの物件は駅近や商業施設の近くにあり、通勤や買い物が便利です。
さらに、建物や共用部分の管理は管理会社が行ってくれるため、自分で外壁やエントランスの清掃・修繕を行う必要はありません。
日々のゴミ出しルールや宅配ボックスなど、細かな設備も整っており、忙しい共働き家庭にも適しています。
一方で、毎月管理費や修繕積立金といった固定費が発生します。
長く住むほど負担は大きくなるため、将来のコストを踏まえた資金計画が必要です。
また、一戸建てに比べて隣接住戸との距離が近いため、音のトラブルが起こりやすい点も注意が必要です。
(2)「新築 or 中古」どっちにする?
家を購入する際に「新築」と「中古」の選択も重要なポイントです。それぞれの特徴を比較してみましょう。
新築物件のメリット・デメリット
新築物件の利点は、何といっても「最新設備」「きれいで快適な住空間」にあります。
誰も住んでいない空間に入居できる清潔感も、新築ならではの特長の一つです。
また、住宅ローン控除や不動産取得税の軽減など、税制優遇の面でもメリットがあります。
最新の断熱・省エネ設備が導入されていることも多く、維持費が安く済みやすいのも魅力です。
ただし、新築物件は価格が高めで、同じ立地・広さで比較すると中古より予算オーバーになりやすい傾向があります。
さらに、「新築=高い資産価値」と考えがちですが、購入直後に価格が下がるケースもあるため、長期的視点での資産形成が大切です。
中古物件のメリット・デメリット
中古物件の最大のメリットは価格の安さと、立地の選択肢の広さです。
都心や駅近といった人気エリアでは、新築の供給が少ないため、「住みたい場所に住む」なら中古を選ぶ方が現実的ということも少なくありません。
また、実際の建物を見てから購入できるので、日当たり・間取り・周辺環境を確認したうえで判断できる安心感もあります。
リノベーションを活用すれば、自分好みの空間に作り変えることも可能です。
一方で、中古物件は築年数による劣化や、修繕費用の発生が前提になります。
購入前には、建物の状態や今後のメンテナンスコストをしっかり確認しておくことが大切です。
(3)間取りはどうする?
家を購入する際、間取りは非常に重要な要素です。
自分のライフスタイルや家族構成に合わせて、どのような物件が最適かを考えてみましょう。
以下では、居住人数別に考えられる物件と、間取りの表記についても解説します。
| 住居人数(世帯構成) | 主なライフステージ | 購入される傾向のある物件タイプ | 備考 |
| 1人(単身世帯) | 独身・若年層 | 中古マンション(1LDK〜2LDK) | 都市部中心、将来的な住み替え前提が多い |
| 2人(夫婦のみ) | 結婚直後、DINKs世帯など | 新築・中古マンション(2LDK〜3LDK) | 都市部では資産性重視の選択が多い |
| 3人(子ども1人) | 出産後〜未就学児童のいる家庭 | 分譲戸建て(3LDK〜4LDK) | 間取り・学区・周辺環境を重視する傾向 |
| 4人以上(子ども2人以上) | 小学生以上の子育て世帯 | 注文住宅・分譲戸建て(4LDK以上) | 郊外も視野に入れた広さや通学利便性を重視 |
| 高齢者世帯(1~2人) | 子どもの独立・定年後 | コンパクトな中古マンション・平屋戸建てなど | 管理のしやすさ・バリアフリー性を重視 |
間取りを選ぶ際、よく目にする「1R」や「2K」といった表記がありますが、これらは以下のような意味を持っています。
- ✅R=ルーム
- ✅L=リビング
- ✅D=ダイニング
- ✅K=キッチン
例えば、「1K」とは、1つの部屋(R)とキッチン(K)がある間取りを示します。
「2LDK」は、2つの部屋(R)、リビング(L)、ダイニング(D)、キッチン(K)がある間取りを指します。
居住人数ごとに希望する間取りを検討する際の参考にしてください。
(4)住宅ローンの返済額・返済期間はどうする?
住宅を購入する際には、住宅ローンの「返済額」や「返済期間」についても考慮しておくことが大切です。
一般的に、住宅ローンの借入目安(年収倍率)は年収の7~10倍程度といわれています。
しかし、借入額の上限を検討する際は、年収倍率だけでなく「返済負担率」も考慮しましょう。返済負担率とは、年収に占める年間返済額、つまり住居費の比率を表す指標です。
返済負担率が高すぎると、当初は問題なくても、毎月・毎年の返済によって生活が圧迫されるリスクがあるため注意が必要です。
よく「住宅ローンの返済負担率は年収の20〜25%が目安」と言われますが、これはあくまで一般的な目安にすぎません。
実際には、お子さまの教育費、老後資金、保険料など、ご家庭によって必要な支出や貯蓄の優先度は大きく異なります。
そのため、本当に無理のない返済計画を立てるには、今後のライフイベントや家計全体を見通したライフプランを作ることが大切です。
自分だけで判断するのが難しい場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談して、将来を見据えた計画を立てることをおすすめします。
また、住宅ローンの借入期間についても慎重に検討すべきポイントです。
住宅ローンの返済期間は最長で35年(フラット35)などを選ぶことも可能ですが、定年を過ぎても返済が続くプランには注意が必要です。
将来の生活費や医療費、年金受給後の収支バランスを考えると、老後にローン返済が残っていると不安材料になることもあります。
また、近年のような社会情勢の変化や収入の不安定化(例:コロナ禍)を経験したことで、「何が起きても対応できる返済計画」を重視する人が増えています。
こうした背景を踏まえ、定年の年齢から逆算して返済期間を設定する、あるいは万が一の備えを残しながら長期返済を組むなど、ライフプランに合わせた柔軟な設計が求められます。
返済期間は一律に「短ければ安心・長ければ不安」とは言い切れません。家計全体と将来のイベントを見通した上で、自分たちにとって無理のない返済プランを組むことが何より大切です。
なお、住宅ローンには「親子ローン」という選択肢もあります。これは、親と子が連帯して住宅ローンを組むことで、世帯合算による借入額の増加や長期の返済期間を実現できる仕組みです。
親の年齢が高くても、子が後継して返済を引き継ぐことで、融資が受けやすくなる場合があります。
ただし、親子ローンには「連帯債務型」「親子リレーローン型」などの種類があり、それぞれ返済責任の範囲や税務上の扱いが異なるため、事前に十分な確認が必要です。
特に相続や贈与の観点も含めて、将来のリスクや負担を家族間でしっかり話し合っておくことが重要です。
このように、住宅ローンの借入額や返済期間、借入方法などの条件は、しっかりとシミュレーションを行ったうえで決定することが大切です。
以下の関連記事では、マンション購入に適した年収や、年収ごとの住宅ローンのシミュレーションについて解説しています。気になる方は、ぜひ本記事とあわせてご覧ください。
(5)費用負担を軽減できる制度が活用できる?
住宅購入において、さまざまな費用負担を軽減するための制度が存在します。
これらの制度を事前に確認し、活用できるものを最大限に利用することで、購入後の負担を軽減できる可能性があります。主に以下のような制度が利用できます。
子育てグリーン住宅支援事業
省エネ性能の高い住宅の新築やリフォームを行う世帯向けの補助金。
- 対象者:子育て世帯(申請時点で18歳未満の子を有する世帯)
若者夫婦世帯(申請時点で夫婦のいずれかが39歳以下) - 補助金額:新築住宅: 最大160万円/戸
- 対象住宅:ZEH水準住宅、長期優良住宅、GX志向型住宅など
- 申請方法:国の登録事業者を通して申請(個人申請不可)
- 申請期限:2025年12月31日まで ※予算上限に達したら早期終了あり
住宅ローン減税
住宅ローンを利用して家を購入した場合に、所得税から一定額を控除する制度。
- 控除額:年末の住宅ローン残高に応じて、最大400万円控除
- 控除期間:最大13年間
- 対象住宅:自分が居住する新築住宅・中古住宅
- 申請方法:初年度は「確定申告」が必要
2年目以降は年末調整でOK
※当初2021年をもって終了する予定でしたが税制改正により利用できる期間が2025年まで延長されます。(ただし、2024年から住宅の種類による借入限度額の変更がありました。)
地方自治体の補助金・助成金
各自治体が独自に行う、住宅購入やリフォームを支援する制度。
- 補助金内容:新築・リフォームの補助金
耐震改修や省エネ住宅への助成金 - 対象者:自治体ごとに条件あり(所得制限、居住年数など)
- 申請方法:自治体の窓口またはオンラインで申請
- ポイント:自治体によっては「移住支援金」や「空き家バンク」も活用できます!
フラット35S(特別金利タイプ)
長期固定金利の住宅ローン「フラット35」において、一定の基準を満たした住宅を対象に、金利が優遇される制度。
- 対象者:新築住宅、省エネ住宅、耐震住宅の購入者
- 金利優遇:最大10年間、通常のフラット35よりも低金利で借り入れ可能
- 申請方法:金融機関を通じて申請
購入する住宅がフラット35Sの基準を満たしている必要あり - ポイント:特別金利により月々の返済額を抑えられるため、ローン負担が軽減される
事前確認と制度活用の重要ポイント
住宅購入にあたって、各種補助金・減税・支援制度を賢く活用するためには、以下を事前に確認しましょう。
- 対象要件の確認
制度ごとに条件(収入制限、住宅の性能基準など)が設定されているので、必ず事前に確認する。 - 申請手続きの把握
申請時期、必要書類、申請方法を事前にチェック。
手続き漏れがあると、せっかくの支援を受けられなくなる可能性あり。 - 自治体独自の補助金調査
地域によっては、移住支援金やリフォーム補助金など、さらに上乗せで支援が受けられる場合も。
自治体のホームページや窓口で最新情報を確認する。 - 早めの情報収集と計画
購入計画の段階から補助制度を意識して動くと、スムーズに利用できる。
事前に制度を理解し、計画的に活用することで、住宅購入の負担を軽減し、より安心してマイホームを購入することができます。
(6)頭金はいくらが理想?ポイントは“バランス”にあり
住宅を購入する際、頭金(自己資金)をどのくらい用意するかは、大きな判断ポイントです。
かつては「物件価格の2割」が目安と言われてきましたが、現在はフルローン(頭金ゼロ)でも住宅ローンが組める時代です。
特に低金利が続く今、無理に頭金を多く用意するより、手元資金を残して将来に備えるという考え方も一般的になってきました。
一方で、頭金を多めに入れると借入額が減り、毎月の返済負担や総返済額を抑えられるメリットがあります。
ただし、頭金を入れすぎて生活資金や教育資金が不足してしまっては本末転倒です。
住宅購入時には諸費用(登記費用、税金、火災保険など)も数百万円かかるため、「自己資金をどれだけ残しておくか」も非常に重要です。
つまり、頭金の金額は「多ければ安心、少なければ危険」といった単純な話ではありません。
住宅ローンの金利条件や今後のライフプラン、万が一の備えなどを総合的に考えたうえで、“ちょうどいいバランス”を見つけることが大切です。
判断が難しい場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、自分たちに合った資金計画を立てておくと安心です。
家を買うときの頭金の決め方について、詳しくは下記記事を参考にしてみてください。

家購入者のリアルな体験談を紹介

ここまでさまざまなデータを基に家購入のタイミングを解説してきましたが、まだ一歩が踏み出せない、という人もいるかもしれません。
そこで、他の人たちはどのタイミングで家購入を考えたのかも見てみましょう。実際の意見や、体験談をご紹介します。
- ✅定年前にローンを完済できるよう30歳で家を購入しました
同い歳夫婦です。30歳の時に家を買いました。当時子なしです。一応35年ローンなので、定年前に払えるようにという事で繰り上げ返済する予定ではありますが、上手く貯金できなくてそのままだとしても安心できるかなと思います。
- ✅子どもの幼稚園を決めるタイミングで購入しました
我が家は昨年、夫24私25の時に建てました!子どもの幼稚園決定をさせるために購入しました。やはり学区を決めてお友達を作ってあげたかったからです!引っ越し当時3歳でしたのでそれなりに床が傷ついたりします
- ✅幼稚園入園前に購入しました
幼稚園入園前にしました!ある程度幼稚園も絞れるし、小学校に上がる時に知ってるお友達ゼロは嫌だったので
皆さんの体験談を見てみると「子どもが小さいときに購入した」という人が多いようです。
過ごしやすい幼稚園や、お友だちづくりなど、子どもの安心できる環境や将来を第一に考えての購入が理由のようです。
また体験談からすると、「定年前に住宅ローンを完済したいから」という理由で早い段階で購入する人も多い印象を受けます。
住宅購入のタイミングには様々なパターンや理由がありますが、迷っているようであれば、体験談のような上記のタイミングも参考にしてみてください。

家購入のタイミングで悩んだら専門家に相談してみる

家の購入を考えるとき、どうしても迷ってしまうポイントが出てきます。
「自分たちだけで計画を立てるのは難しい」「購入資金や購入額についてアドバイスがほしい」「買ってはいけないタイミングを教えてほしい」といった悩みが浮かぶ方も多いでしょう。
そのような場合、専門家に相談してみるのが一つの手です。
不動産会社や宅地建物取引士は選択肢としてありますが、彼らは商業的な利害関係が絡むため、アドバイスが必ずしも中立的でない可能性もあります。
特に購入後のサポートを期待する場合は注意が必要です。
その点、ファイナンシャルプランナー(FP)はお金の専門家であり、家購入のタイミングだけでなく、将来を見据えた資産形成のアドバイスも得られます。
弊社FPは、マンション購入に関する2万件以上の相談実績を持ち、幅広いニーズに対応しています。
家購入のベストタイミングだけでなく、必要に応じて将来に向けた資産形成など、充実したアドバイスを幅広くワンストップで提供させていただきます。
家の購入が安心、そしてスムーズになるためプロのアドバイザーであるFPにご相談ください。
実際の相談事例も公開しているので、ぜひ参考にしてみてください。プロのアドバイザーに相談すれば、あなたの家購入が一段と安心できるものになるでしょう。
まとめ

今回は、年齢や年収などのデータを基に、家購入のタイミングや購入のきっかけ、事前に知っておきたい知識について解説しました。
住宅購入は、人生で最も高額な買い物であり、誰でも迷うものです。しかし、先延ばしにしてしまうと、タイミングを逃し後悔する可能性もあります。
もし、家購入のタイミングや資金計画、返済計画について迷ったら、ぜひ弊社FP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみてください。
FPは将来を見据えた家購入の最適なプランや、資産形成のコツなど幅広くアドバイスを提供します。専門家のサポートを活用して、安心して家購入を進めましょう。
著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆
アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。