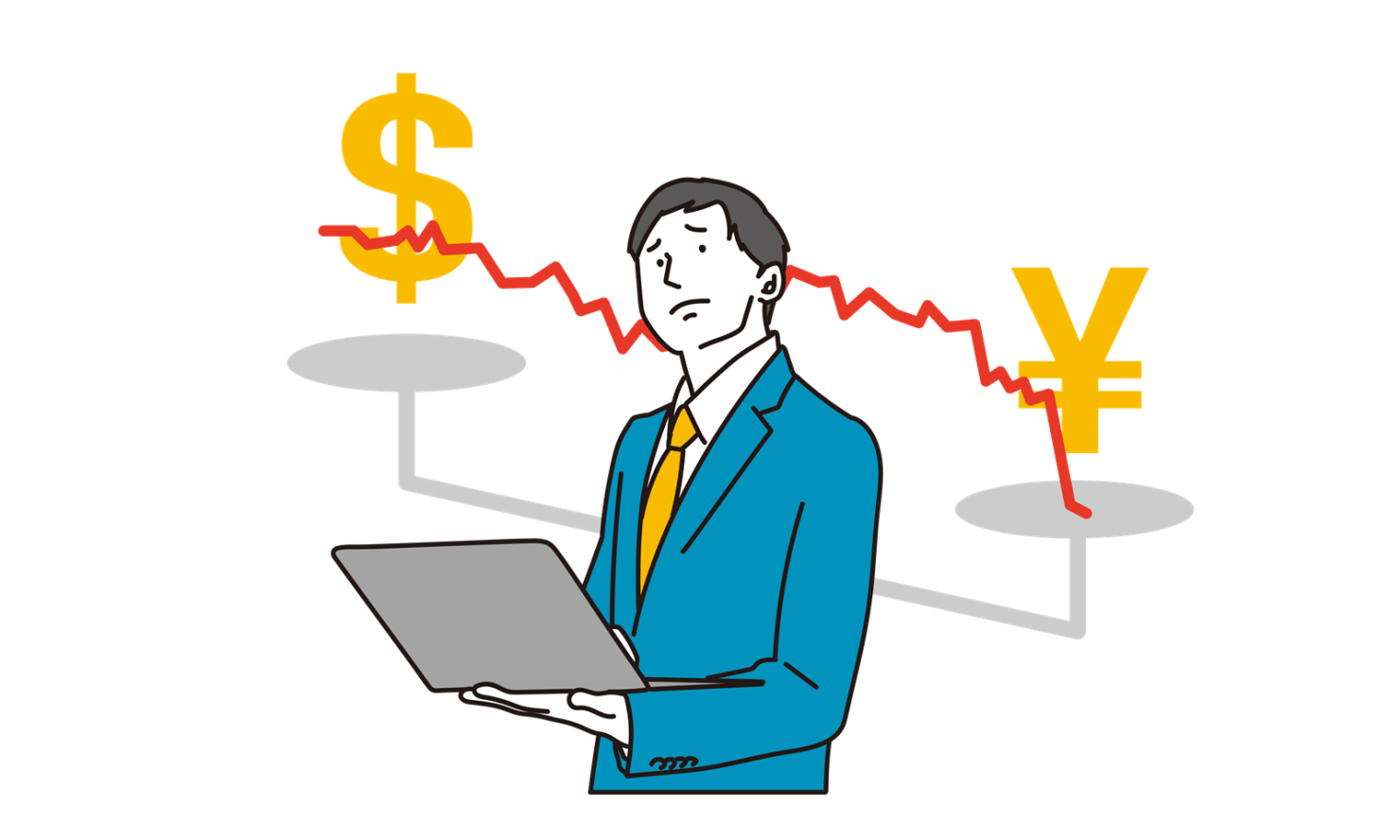50代の平均貯蓄1000万円以上?FPが老後資金を増やす方法も解説

50代は老後生活を考える世代です。
「人生100年」といわれる中、どれくらいの老後資金を準備しておけば安心なのでしょうか。
同世代の貯蓄額の平均値も気になるところです。
本記事では、50代の平均貯蓄や老後資金の増やし方を徹底解説しています。
貯蓄額の平均値や老後の必要資金について知りたい人はぜひ、チェックしてみてください。
50代の平均貯蓄額は「1,199」万円

まずは50代の貯蓄額を、ケースごとにご紹介します。
金融広報中央委員会の調査データを参考に貯蓄額をまとめましたので、さっそくみていきましょう。
参考:金融広報中央委員会 | (家計の金融行動に関する世論調査[総世帯]令和4年調査結果)
(1)50代の平均貯蓄額は「1,199万円」
調査結果によると、50代の平均貯蓄額(金融資産を含む)は1,199万円でした。
よって、50代の貯蓄額は1,000万円以上あることが分かります。
50代の貯蓄額の中央値は260万円でした。中央値というのはデータを大きい順(または小さい順)に並べた際に、中央を位置する値のことです。
平均値と合わせて中央値を見ておきましょう。
他の年代と比較してみると、40代の平均値は785万円(中央値は200万円)、60代の平均値は1,689万円(中央値は552万円)となっています。
50代になると支出が落ち着くこともあり、平均値が1,000万円を超えています。
60代になると中央値が50代の2倍以上もあり、年齢を重ねるごとに貯蓄が増え安定していくのが特徴的です。
(2)50代の世帯別の貯金額
次に、世帯別の預貯金額をみていきましょう。
| 世帯類型 | 貯金額 |
| 世帯主のみ | 370万円 |
| 世帯主夫婦のみ | 673万円 |
| 世帯主夫婦と子のみ | 512万円 |
| 世帯主夫婦と親のみ | 654万円 |
①50代二人以上世帯の貯金額は「613万円」
上記表の中で二人以上の世帯は「世帯主夫婦のみ」「世帯主夫婦と子のみ」「世帯主夫婦と親のみ」の3類型です。
3類型の貯金額の平均値は613万円となります。
したがって、二人以上の貯金額の平均値も613万円に近い数値であるといえるでしょう。
②50代の単身世帯の貯金額は「370万円」
単身者の貯金額は370万円です。
一見、二人以上世帯の貯金額の方が多くみえますが、一人あたりの貯金額で比較してみると単身世帯の方が多いことが分かります。
一人暮らしであれば出費も少ないため、単身世帯はお金を貯めやすい環境が整っています。
特に20歳、30歳から独身であれば、ある程度貯金があるため不動産投資や投資信託などを行っている方もいるでしょう。
(3)50代の年間年収別の貯金額
調査結果によると年間年収別の貯金額は以下のとおりです。
| 年収 | 貯金額 |
| 収入なし | 152万円 |
| 300万円未満 | 308万円 |
| 300~500万円未満 | 461万円 |
| 500~750万円未満 | 572万円 |
| 750~1000万円未満 | 688万円 |
| 1000~1200万円未満 | 1,015万円 |
| 1200万円以上 | 1, |
表をみると、年収が増えるにしたがって貯金額も増える傾向にあることが分かります。
よって貯金額は年収に関係しているといえるでしょう。
(4)50代の約2~3割は貯金がない
| 年齢 | 貯金がない人の割合 |
| 20代 | 21.9% |
| 30代 | 35.8% |
| 40代 | 33.0% |
| 50代 | 34.2% |
| 60代 | 29.9% |
| 70代 | 25.9% |
年代別のデータをみてみると、どの年代においても2~3割の人は貯蓄ゼロであることが分かります。
また、50代は30代に次いで、2番目に貯蓄がないという結果になりました。
老後の貯蓄の考え方!老後資金はいくらあればいい?
老後資金はもらえる年金額や老後のライフスタイルによって異なります。ここでは、自分に合った目標金額の算出方法をみていきましょう。
(1)ねんきん定期便からもらえる年金額を確認
ねんきん定期便とは、年金の加入状況や、将来もらえる年金の見込み額が記載されている書類です。
定期便は毎年誕生月に送られてくるので、まずはその書類で将来の年金額を確認しましょう。
(2)理想の老後生活費を算出する
将来の年金額を把握したら、次は理想とする老後の暮らし方から生活費を算出します。
現在の生活費を参考にしながら、なるべく具体的に目標額をシミュレーションしておくとよいでしょう。
理想を高く設定せず無理のない範囲内で実現できるように考えましょう。
(3)理想の老後生活からの不足金額を算出する
将来の年金額と、理想とする老後生活費が分かったら、1ヶ月あたりの不足分を算出します。
不足分の求め方は以下のとおりです。
(将来の年金額)-(理想の老後資金)=(1ヶ月あたりの不足分)
(4)生きられる年数を掛け算して不足金額を算出する
最後に、65歳から生きられる年数(ヶ月)を1ヶ月あたりの不足分にかけて、将来の不足金額を算出します。
将来の不足金額の求め方は以下のとおりです。
(生きられる年数)×(1ヶ月あたりの不足分)=(将来の不足金額)
生きられる年数は「〇ヶ月」に直すと計算しやすいです。
| 生きる年数 | 65歳から生きられる年数 |
| 75歳まで | 120ヶ月 |
| 85歳まで | 240ヶ月 |
| 90歳まで | 300ヶ月 |
自分の老後資金の計算方法についてより詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
50代のライフイベントで知っておくべき必要なお金

50代は、子どものこと、親のこと、そして自分のことと、さまざまな場面でお金が必要です。
ここでは、知っておいてほしいライフプランごとの資金を3つご紹介します。
(1)子どもの学費
子どもの学費は、私立と公立のどちらを選ぶかによって大きく異なります。
教育機関によって差はあるものの、私立は公立に比べて2~5倍もの学費が必要です。
また、大学や大学院、専門学校への進学の有無によっても子どもの教育資金は大きく異なります。
子どもの教育費用について詳しく知りたい方は、下記記事を参照してみてください。
(2)親の介護、相続、葬儀などの費用
50代は親の将来も考えなければならない年代です。
介護費用や葬儀費用などの相場を以下にまとめましたので、参考にしてみてください。
| ライフイベント | 費用相場 |
| 親の介護 (老人ホーム、医療費を含む) | 500万円 |
| 相続 | 10万円以上 |
| 葬儀 | 90万円 |
「相続はお金がもらえるものでは?」と思われる方もいるかと思いますが、手続きには費用がかかります。
相続の手続きを自分で行う場合は3,000円程度、専門家に依頼した場合は10万円以上の諸費用が必要ですので、注意しましょう。
(3)自分の老後資金
総務省のアンケート調査結果によると、65歳以上(単身世帯)の年金収入は121,496円で、消費支出は143,139円ですので、毎月21,643円の赤字となっています。
例えば65歳から90歳まで25年間生きるとすると、不足分は以下のとおりです。
21,643円×12(ヶ月)×25(年)=6,492,900円
よって老後の生活資金は約650万円が必要ということになります。
さらに、老後に旅行や趣味を楽しむのであれば、目安としてプラスで200~500万円用意しておくと安心でしょう。
参考:総務省統計局(家計調査年報 家計収支編 2022年] )
50代が効率よく貯金を増やす方法
老後に備えてお金を貯めるなら、効率的に増やしたいものです。
ここでは、NISAや債券など投資初心者におすすめの資産運用方法を8つご紹介します。
(1)ライフプランニングを作る
ライフプランは将来起こりうるライフイベントを想定して、お金を準備するための計画を立てることです。
ライフイベントといっても、住宅購入と出産では必要となる費用が大きく異なるので、具体的に考えていくことが大切です。
それではライフプランの作り方を紹介します。
- ✅STEP1:目標を設定する
どんなライフイベントを実現したいのか、実現したい内容をリストアップします。
例えば「海外旅行」「住宅購入」「自動車の購入」「大学へ進学」などです。
- ✅STEP2:スケジュールを設定する
自分で立てた目標をいつまでに成し遂げたいのかを考えます。10年後・20年後・30年後と考えてもいいですし、20代・30代・40代と年代別で考えても構いません。
実現したい時期や期間を設定しましょう。
- ✅STEP3:必要なお金をシミュレーションする
実現するためにどれくらいのお金が必要になるのかシミュレーションします。目標金額に対して毎月どれくらい積み立てればいいか算出します。
- ✅STEP4:現実的な生活プランを考える
シミュレーションから算出した金額と毎月の支出をもとに現実的な生活プランを考えます。
毎月5万円積み立てたい場合、節約を意識するのか、または収入を増やすために副業を行うのかなどを検討します。
例えば節約であれば、ガス・水道・電気代などの光熱費を抑える、安い家賃の家に住むなど節約術はたくさんあります。
収入を増やすために副業を行うのであれば、NISAやiDeCoのような投資信託を行う、不動産投資に挑戦するといった方法も有効です。
また支出の状況を把握するために家計簿をつけ、支出に対する意識を高めることも効果的です。例を見ながらライフプランの作り方を見ていきましょう。
| 実現したいライフイベント | 時期(期間) | 費用 | 毎月の積立金額 |
| 海外旅行 | 1年後(20代) | 40万円 | 約3.5万円 |
| マイカー購入 | 10年後(30代) | 400万円 | 約3.5万円 |
| 住宅購入(頭金) | 10年後(30代) | 600万円 | 5万円 |
| 子どもの大学費 | 20年後(40代) | 700万円 | 約3万円 |
| 老後生活を楽しむお金 | 40年後(60代) | 3,000万円 | 6.25万円 |
表にまとめるとライフイベントごとに毎月の積立金額が一目でわかります。この計画をもと節約や副業などを行い、貯蓄していきましょう。
ライフプランの作り方について詳しく知りたい方は、下記記事を参照してみてください。
(2)資産運用をする
資産運用は「お金」や「不動産」などの財産を、効率的に増やしていくことです。
資産運用と聞くと投資家が行っているイメージがありますが、一般の方も多く利用しており、「NISA」や「iDeCo」などの積立投資が有名です。
近年では40代・50代と比較して、20代・30代がNISAや不動産投資などの資産運用に興味をもつ方が増えているため、早めに取り組んでみてもいいでしょう。
資産運用を行う重要性は2つあります。1つ目は、日本の金利が低いことです。日本は普通預金で0.001%、定期預金で0.002~0.003%しかありません。
日本と比較すると海外は金利が高いため海外で口座開設を行い、お金を預けておけば、より多く利益を得ることができます。
2つ目は、インフレを回避できることです。インフレはお金の価値を下げてしまうため、「預貯金であればお金が減らない」という考えは危険です。
1,000円で10個変えた100円の商品も、3%のインフレが起きれば商品が103円になり9個しか買えなくなるため、お金は減っていないですが価値は下がってしまいます。
インフレを回避するためには、海外で口座開設を行い、資産を分割しておくことが重要です。
これらの理由から不動産投資や「NISA」や「iDeCo」などの積立投資などを行っておくと安心です。
①つみたてNISA
つみたてNISAは、運用益が非課税になる積立投資です。
一般的な株式投資は、利益に所得税と住民税がかかります。
一方つみたてNISAは利益に税金がかからないため、税負担の軽減と節税対策ができる制度です。
NISAについて詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
た、私が講師を務める「新NISA制度丸わかりセミナー」の動画をLINE友達限定にて公開しています。
- ✅つみたてNISAの落とし穴
- ✅新NISAの注意点
- ✅実際に私が実践している投資商品
- ✅成功するための鉄則
などリアルな情報がたくさんです。つみたてNISAで損をしている方、これからNISAを検討している方は、ぜひご覧ください。
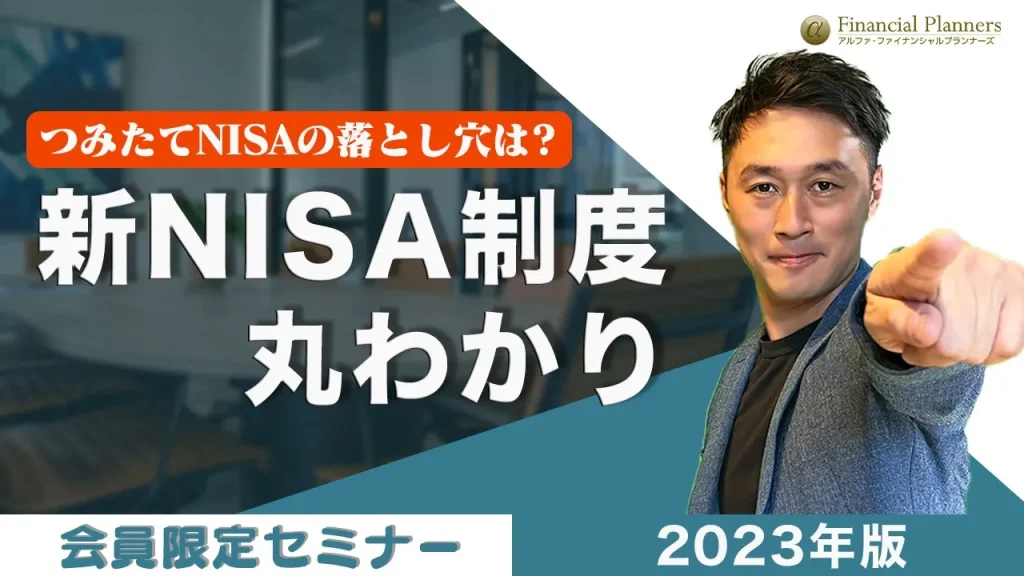
②iDeCo(イデコ)
iDeCoは、企業年金や国民年金などの公的年金とは別に、任意で加入できる私的年金です。
個人型確定拠出年金ともよばれ、掛け金がすべて所得控除になるメリットがあります。
一度設定してしまえば、自動的に資金が積立てられるので、比較的簡単に始められるのが特徴です。
ただし、デメリットとして60歳まで引き出せないことが挙げられます。
そのため、運用する際は余剰資金で行うのがおすすめです。
また、所得控除の対象になる掛け金額は、「会社員」「自営業」「専業主婦(主夫)」など、社会保険の被保険者区分によって異なるため、注意しましょう。
iDeCo(イデコ)について詳しく知りたい方は、下記記事を参考にしてみてください。
また、つみたてNISAとの違いなども把握しておきたい方は、下記記事を合わせてお読みください。
③財形貯蓄
財形貯蓄は、会社が給料の一部を天引きし貯金してくれるサービスです。自分で貯金することが苦手な方や住宅購入を検討している方は利用してみましょう。
財形貯蓄のメリットは、「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」を利用すれば合計貯蓄残高が550万円までは利息に税金が付かないことや、「財形貯蓄を1年以上継続している」「貯蓄残高が50万円以上ある」という条件を満たせば、貯蓄残高の10倍まで住宅ローンの融資を受けられることです。
一方のデメリットは、金利が0.01%前後と高くないことやお金がすぐに引き出せないことです。
財形貯蓄について詳しく知りたい方は、下記記事を参照してみてください。
④投資信託
投資信託は、プロに資産を預けて代わりに運用してもらう資産運用の方法です。
投資に興味はあるけれど、金融商品の選び方が分からないという人は投資信託を利用するのがよいでしょう。
口座開設方法や、始め方、選べる商品は証券会社によって変わるので、自分に合った証券会社を選ぶのが重要です。
一方で投資商品の中では絶対に損をする商品もあります。下記動画ではそのような商品の特徴を解説していますので、損をしたくない方はぜひご覧ください。
⑤金(ゴールド)投資
金投資とは、文字通り「金」に投資する運用方法です。
どの国でも価値が変わらないため、安全で信頼性が高い金融商品としても知られています。
金(ゴールド)投資について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
⑥外貨預金
外貨預金は、米ドルやユーロといった外国の通貨で行う定期預金です。
円よりも金利が高い外貨を選んで預金すると、円預金よりも高い利息が期待できます。
基本的な仕組みは円預金と同じなので、初心者でも比較的始めやすい運用方法です。
ただし、外貨を円に替える際は手数料が発生するため、注意しましょう。
一方で外貨預金にはデメリットもあります。詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
⑦債券
債券とは、投資家からお金を借り入れして発行する有価証券です。一般的には株式投資や投資信託などと比較すると安全性が高い投資商品だと言われています。
投資家はお金を貸して満期が来れば投資した債券の元本と利子が返ってくるため、シンプルでわかりやすく投資初心者に向いています。
⑧株式投資
株式投資は、株式の売買によって自分が投資している企業から配当金などの利益を得る投資方法です。
株式投資と投資信託は似ていますが、投資を行っている対象が異なります。
株式投資は、1社の株式に投資することに対し、投資信託は1つの商品を購入し複数の銘柄に分散投資しています。
投資初心者の方は銘柄まで絞って投資することが難しいため、投資信託から始めるほうがおすすめです。
株式投資は、価格変動リスク・信用リスク・流動性リスク・為替変動リスクといった値動きが不確実になるリスクがあるため、初めて挑戦する方はFPに相談すると手厚いサポートを受けられます。
50代で資産運用する時の注意点

メリットが多く魅力的な資産運用ですが、注意点もあります。
ここでは、50代で資産運用する際に気をつけたいポイントを確認していきましょう。
(1)定年退職の時期を意識してできるだけ早くスタートさせる
50代で資産運用を始める場合、あらかじめ定年退職の時期を考えて運用計画を立てるのがよいでしょう。
退職後は年金生活となり、退職前よりも大幅に収入が減る可能性が高いです。
そのため、退職前と退職後で収入が変化するタイミングに合わせて、運用計画を2パターン用意し、定年後にプランの見直しをすると焦らずにすみます。
(2)リスクが低い商品に限定する
貯金額の理想と現実にかなり差がある場合、焦ってハイリスク・ハイリターンの商品を選んでしまう人がいます。
しかし、50代で資産運用に失敗すると損失分を老後までに働いて貯めるのはなかなか難しいです。
そのため、50代で資産運用する際は、リスクの低い商品で少額から運用するとよいでしょう。
(3)金融機関の投資営業に気をつける
50代は役職がついて収入が増加するのに加え、住宅ローンを払い終わる年代のため、貯金が貯まりやすくなります。
そこで注意したいのが金融機関の投資営業です。
理由としては、投資に関する知識がないと、勧められるがまま商品を購入して損をする可能性があることが挙げられます。
そのため、金融機関の営業を鵜呑みにしないのはもちろん、自分でも情報収集して計画的に資産運用することが大切です。
(4)欲張らず自分に合った投資プランを選ぶ
欲張ってリスクの高い投資プランを選ぶと、元本割れする可能性が高まるため要注意です。
また資産運用といっても不動産投資や債券、NISAのような積立投資など種類はさまざまです。
そのため、資産運用を始める前にはしっかりと情報収集を行い、無理のない範囲内で自分に合った投資プランを選ぶようにしましょう。
50代が資産運用をする時の注意点などについて詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
退職金も投資すべき?退職金の考え方

老後資金を増やすために、退職金を投資に回そうと考えている人もいるでしょう。
結論からいうと、退職金は投資に回すのがおすすめです。しかし、以下のような投資方法はおすすめしません。
- ✅退職金を全額投資する
- ✅ひとつの商品のみに投資する
上記のような極端な投資方法は、老後資金を増やすどころか、損失を出すリスクが高まります。
そのため、退職金を投資する際は全額投資せず、ゆとりのある資金で複数の商品に分散投資するのがおすすめです。
退職金を活用して資産運用を検討するときに注意点について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
不安がある方はFPに相談

「老後に備えて資産運用をしたいけれど、何から始めればいいか分からない」
「資産運用は難しいイメージがあって心配」
など、資産運用に対して不安や悩みがある人はFPに相談するのも選択肢のひとつです。
FPとはファイナンシャルプランナーの略で、資産運用や資産形成などのお金に関する相談業務を行っている人を指します。
弊社は企業会員の方は3回まで無料相談することができます。まず該当するかどうかは確認してみてください。
まとめ

この記事では、50代の平均貯蓄額や老後資金の効率的な増やし方をご紹介しました。
充実したシニアライフを送るためにも、しっかりと資金計画を立てて、老後資金を準備するのがおすすめです。
ただし、資産運用をする歳には無理のない範囲でゆとりをもって運用しましょう。
老後にお金がないとどうなる?老後に備えるプランを解説! | スマートシニア
著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆
アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。
最新の投稿
 税金2024年2月27日不動産を相続したら相続税はいくら?手続き、計算方法や活用方法を解説
税金2024年2月27日不動産を相続したら相続税はいくら?手続き、計算方法や活用方法を解説 不動産投資2024年2月24日不動産所得がある場合は確定申告が必要!計算方法や申請手順を解説
不動産投資2024年2月24日不動産所得がある場合は確定申告が必要!計算方法や申請手順を解説 税金2024年2月23日不動産の生前贈与はした方がいい?メリット、手続きや注意点を解説
税金2024年2月23日不動産の生前贈与はした方がいい?メリット、手続きや注意点を解説 不動産投資2024年2月21日不動産投資クラウドファンディングとは?おすすめ商品も合わせて紹介
不動産投資2024年2月21日不動産投資クラウドファンディングとは?おすすめ商品も合わせて紹介