老後2,000万円問題とは?老後資金の計算方法や足りない時の対策

5年ほど前から「老後2,000万円問題」という言葉を耳にする機会が多くなり、老後のお金のことについて考え始めた人は多いのではないでしょうか。
本記事では、老後 2,000万円問題が注目され続けている理由やその対策である老後資金を貯めるポイントについて徹底解説していきます。
老後に向けた資金づくりに興味のある方はぜひ、この記事を参考にしてください。
そもそも老後2,000万円問題とは

「老後2,000万円問題」とは、2019年金融庁から「老後30年で公的年金以外に約2,000万円の資金が必要」という報告書が出されたことに端を発しています。
報告書内では、「高齢夫婦無職世帯(男性が65歳以上で女性が60歳以上となった無職世帯の夫婦)の平均的な年金手取り額と支出を差し引いた不足額が約5万円発生し、20年で約1,300万円、30年で約2,000万円の取り崩しが必要になる。」と記載されています。
高齢社会となり人生100年時代といわれる中、定年退職後の30年間以上、退職金や貯蓄などを切り崩して生活しなければならないのです。
2024年7月、厚生労働省が5年に1度公的年金に関する長期的な見通しを示す「財政検証結果」で、将来の年金は6%〜18%下がると試算しました。
5年前である2019年の試算結果と比べると、女性の社会進出の増加や株高の好影響もあり、年金の低下率は縮小しているものの、減ってはしまうようです。
また、支給開始年齢を引き上げることも十分に考えられます。
年金のみで老後の生活費をまかなうことが難しくなっている中、リタイア後の生活資金を若いうちから自分で蓄えておく必要がでてきています。
老後2,000万円問題が注目された背景
老後の資金として約2,000万円が必要と聞いて驚き、不安になった人もいるでしょう。
ここでは、この問題が注目されるようになった背景を解説していきます。
平均寿命が延伸したから
| 年 | 男 | 女 |
| 1955年 | 63.60 | 67.75 |
| 1960年 | 65.32 | 70.19 |
| 1965年 | 67.74 | 72.92 |
| 1970年 | 69.31 | 74.66 |
| 1975年 | 71.73 | 76.89 |
| 1980年 | 73.35 | 78.76 |
| 1985年 | 74.78 | 80.48 |
| 1990年 | 75.92 | 81.9 |
| 1995年 | 76.38 | 82.85 |
| 2000年 | 77.72 | 84.6 |
| 2005年 | 78.56 | 85.52 |
| 2010年 | 79.55 | 86.3 |
| 2015年 | 80.75 | 86.99 |
| 2018年 | 81.25 | 87.32 |
| 2019年 | 81.41 | 87.45 |
参考: 令和2年版 厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える
日本人は年々長寿化しています。
上の表からもわかるように1955年では65歳くらいでしたが、2019年では約85歳と20歳程伸びています。
現在60歳の人の約4分の1が95歳まで生きるという試算もあり「人生100年時代」と言われる所以ともなっています。
退職金が減少したから
退職給付制度がある企業(全規模)の割合
| 1992年 | 92% |
| 1997年 | 88.90% |
| 2002年 | 86.70% |
| 2007年 | 85.30% |
| 2012年 | 75.50% |
| 2017年 | 80.50% |
平均退職給付額(全規模)の推移
| 年 | 万円 |
| 1992年 | 2848 |
| 1997年 | 3203 |
| 2002年 | 2612 |
| 2007年 | 2491 |
| 2012年 | 2156 |
| 2017年 | 1997 |
参考:金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」
金融庁の報告の資料によると、退職金給付制度がある企業が年々減ってきていること、給付額がピーク時より約3〜4割減少していることがわかります。
企業は社内で退職金を用意するため独自の資金運用を行っています。
しかし、低金利が長く続いていることで退職金の準備が難しい状況です。
また、退職金給付制度は企業にとって大きなコストとなります。経営状況によっては資金の確保が厳しくもなります。
これらのことが原因で退職金制度の廃止や給付額の減額につながっており、今後も減る可能性は十分あります。
働き方が多様化したから
労働者側の価値観の変化から、終身雇用ではなくフリーランスや転職する人たちが増えてきています。
退職金は勤続年数が金額に反映されることから、転職が増えると退職金が減ってしまいます。
年金制度に不安があるから
従前までは、老後の生活は「年金と退職金で賄っていける」というのが一般的な考え方でした。
しかし、上で述べた「財政検証結果」でも示されている通り、年金が減少する見通しとなっています。
公的年金制度は、現役世代が納めた保険料や年金積立金、税金を高齢者の年金給付に充てるという考え方に基づき運営されています。
少子化が進んでいる現在、これから保険料を納める現役世代が段々と減少していくため、将来の年金制度が不安視されています。
実際に高齢者世帯の貯蓄額は?
では、実際に高齢者世帯の貯蓄額はいくらになるのでしょうか。
- ✅2人以上世帯の貯蓄額
| 2人以上世帯全体 | 共働き世帯のみ | |
| 60歳~69歳 | 2,458万円 | 2,180万円 |
| 70歳~ | 2,411万円 | 2,191万円 |
- ✅単身世帯の貯蓄額
| 男性 | 女性 | |
| 60歳代 | 1,791万円 | 1,423万円 |
| 70歳代 | 1,427万円 | 1,217万円 |
| 80歳代 | 1,750万円 | 1,083万円 |
上記家計調査報告書によると、年齢や世帯によって貯蓄額はさまざまですが、全体的に高齢夫婦よりも単身の高齢者の方が、1人あたりの貯蓄額が多い傾向にあります。
また、男女別の平均額で比較してみると、女性より男性の方が資産に余裕があるという結果になっています。
人によって老後の不足金額が違う

老後2,000万円問題を聞き、「老後までに2,000万円を急いで貯めなければ!」と焦る人がいるかもしれませんが、人によって老後の不足額は異なります。
「出費が多い」「老後収入が多い」などの生活水準によって「2,000万円あれば十分」という人もいれば、「2,000万円溜めても足りない」というケースもあるのです。
そのため、2,000万円を目標にするのではなく、どれだけの貯蓄があれば将来安心して暮らせるのかを前もって計算して用意しておくことが重要です。
老後に考えられる収入
老後の生活資金について考える前に、まずは老後の収入について把握しておきましょう。
老後の収入として考えられるのは、主に年金・退職金・投資の利益の3つです。
(1)年金
老後の収入と聞いて、まず思い浮かぶのが公的年金制度による年金収入です。
原則、65歳になって年金として受け取る場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類が受給できます。
- ✅老齢基礎年金…国民年金や厚生年金に加入していた場合、加入期間に応じた年金給付がある
- ✅老齢厚生年金…企業に勤めて厚生年金に加入していた人がもらえる年金で、年金受給額は給与や賞与の額などによって変わる
厚生年金は企業に勤めている人だけが加入できるため、現在フリーランスであるなど国民年金加入者の方は厚生年金の受給額が少なくなるため、その分を多めに見積もって将来の貯蓄額を決める必要があります。
(2)退職金
会社を退職する人が一定の金額をもらえる退職金制度も、老後収入のひとつです。
ただし、個人事業主の場合は退職金がありませんので、その分自助努力で貯めるべき老後資金は高くなります。
また、勤め先の企業に退職金制度がない場合は自分自身で老後の生活資金を確保しておく必要があります。
早いうちから無理のない範囲で資金を用意しておきましょう。
(3)株の配当など投資での収入
投資での収入も、老後収入となり得ます。
例えば、株式配当、債券の利息収入、不動産の賃料収入など、持っているだけで収入を得られるインカム収入を作ったり、株式やFXの売買益で収入を補填するなどです。
株式、投資信託、債券などの金融商品の利益に対する税金が20.315%かかりますが、株式や投資信託は新NISAをうまく利用することで税金対策になります。
老後に考えられる支出

一方で、老後に必要な費用には、どんな支出が考えられるのでしょうか。
項目と平均的な費用を確認しながら、ご自身の支出がいくらあるか整理してみましょう。
ただし、数値はあくまで平均ですので、ご自身がどうかはしっかり家計簿などから算出しながら考えていきましょう。
(1)生活費
- ✅高齢世帯 1ヶ月の生活費
| 60~69歳 | 70歳~ | |
| 食費 | 67,795円 | 56,741円 |
| 住居費(住宅ローン含む) | 18,422円 | 14,633円 |
| 光熱費 | 19,930円 | 17,822円 |
| 合計 | 106,147円 | 89,196円 |
上記表の数値をもとに年間の生活費を求めると、平均では60歳代で約120万円、70歳以上で約100万円が必要となります。
(2)住宅ローン返済の費用
| 年 | 歳 |
| 2012年 | 38.9 |
| 2013年 | 39.6 |
| 2014年 | 40.4 |
| 2015年 | 39.8 |
| 2016年 | 39.8 |
| 2017年 | 40.4 |
| 2018年 | 40.1 |
| 2019年 | 40.2 |
| 2020年 | 40.3 |
| 2021年 | 41.5 |
| 2022年 | 42.8 |
参考:住宅金融支援機構 「2022年度 フラット35利用者調査」
住宅ローンの借入期間は一般的には30年~35年で契約されることが多いです。
上の表を見ると、住宅ローンを組む平均年齢が少しずつ上がってきており、2022年では42.8歳となっています。
その年齢から返済していくと完済するのは、72歳~77歳となり、定年退職後にも返済が終わっていないという状況が考えられます。
ご自身が退職するときの残債を確認することがおすすめです。
(3)子どもの教育費
| 年 | 初婚夫 | 初婚妻 | 再婚夫 | 再婚妻 |
| 1990年 | 28.4 | 25.9 | 40.1 | 36.5 |
| 2000年 | 28.8 | 27.0 | 40.7 | 37.2 |
| 2005年 | 29.8 | 28.0 | 41.3 | 37.8 |
| 2010年 | 30.5 | 28.8 | 42.0 | 38.6 |
| 2015年 | 31.1 | 29.4 | 42.9 | 39.8 |
| 2016年 | 31.1 | 29.4 | 43.0 | 39.8 |
| 2017年 | 31.1 | 29.4 | 43.3 | 40.1 |
| 2018年 | 31.1 | 29.4 | 43.7 | 40.4 |
参考: 令和2年版 厚生労働白書-令和時代の社会保障と働き方を考える-
婚姻年齢の推移を見ると、晩婚化が進んでいることがわかります。
それに伴い、子どもを出産する年齢も上がっていきます。
定年後も学費等を支払わなければならない、子どもが自立した後の貯蓄額を増やせる期間が短くなるといったことにつながってきます。
また、50代のうちに子供が独立しても、実際には貯金できる期間が短く老後資金が十分に貯められない方もいます。
(4)旅行などの娯楽費
- ✅高齢世帯 1ヶ月の娯楽費
| 60~69歳 | 70歳 | |
| 教育娯楽 | 22,336円 | 16,395円 |
| 趣味 | 16,812円 | 17,121円 |
| 合計 | 39,148円 | 33,516円 |
上記表の情報をもとに年間の娯楽費を計算すると、平均では60歳代で約47万円、70歳以上で約40万円が必要となっています。
これも趣味によってかかる金額は千差万別です。ご自身とパートナーが楽しい老後を過ごせる金額がいくらかを考えておきましょう。
(5)冠婚葬祭などの出費
子どもがいる高齢夫婦の場合、子どもの結婚や出産、教育資金の援助など親や祖父母としての出費は増加します。
また、20-30代前半では結婚式のお祝儀、50代からはお知り合いの葬式に関わる香典などが増える傾向にあります。
起こりうるライフイベントに備えて資金を準備しておくことが大切です。
また、自分が亡くなったときの家族への負担を減らすために自分で葬儀費用を用意しておく人もいます。
その場合の葬儀平均額は約200万円となっています。近年では家族葬や直葬などの普及で金額が変わってきています。
(6)老人ホームなどの介護費用
厚生労働省のデータによると、「75歳以上のうち約30%の人が要支援・要介護の認定を受けている」という結果が出ており、病気になったり日常生活を送るのに支援が必要になったりして、介護サービスを受ける可能性も少なくありません。
また、月々の介護費用は約8万円となっており、支出の中でも大きな割合を占めていることになります。
よく、インターネットで介護費用を検索をすると、入居後の生活費で30万円-50万円かかるなどという情報が出ていますが、これは食費や居住費も含まれます。
実際に介護費用だけを切り取って計算する場合は、上記8万円を参考にしていただくと良いでしょう。
参考:生命保険文化センター「令和3年度生命保険に関する全国実態調査」
自分にあった老後資金の計算方法

先ほど、将来必要な費用は老後の収入やライフスタイルによって異なると説明しましたが、自分に必要な老後資金を計算するにはどうすればいいのでしょうか。
シミュレーションの仕方をご紹介します。
(1)もらえる年金額を算出する
まずは、将来もらえる年金額を確認しましょう。
厚生年金の金額は「ねんきん定期便」から確認できますが、企業年金や私的年金については人事総務や年金窓口に直接確認する必要があります。
(2)理想となる老後生活に必要な費用を算出する
年金額が確認できたら次は老後の支出を算出してみましょう。
家計簿をつけている人は家計収支を参考にしながら、消費支出額を算出します。
その際、今、どれくらいの生活費がかかっているのか?それは老後になってもかかるものなのか?を自問自答していきながら数値化していきましょう。
理想とする老後生活をなるべく具体的にイメージすると老後に必要な費用の目安が分かりやすくなります。
(3)実際に不足となる金額を算出する
老後に必要な費用と老後の収入が分かったら、実際に不足額を求めてみましょう。
「老後収入-老後支出」の差額が不足金額となります。
不足金額が出るようなら、老後までに不足分を補えるように対策を立てましょう。
お金の管理をするときに「マネソル」というアプリがあります。
質問に答えると精密なライフプランを作成してくれます。老後の資金も計算してくれるので、活用してみてはいかがでしょうか。
「マネソル」についてはこちら >
老後資金が不足している場合の対策

老後資金を計算すると、老後までに資金の準備が間に合わない人がいるかもしれません。
資金不足の場合、貯金はもちろん資産運用なども積極的に行うのが大切です。
ここでは、老後資金の準備方法と資産運用におすすめの金融商品をご紹介します。
(1)給与天引きなどの先取り貯金
月末に残ったお金を貯金しようと思うと、なかなかお金は貯まらないものです。
貯金が苦手な方は、財形貯蓄などを活用して先取り貯金をするのがおすすめです。
財形貯蓄とは、給与や賞与収入の一部を金融機関に直接預金する制度で、勤め先の会社が導入している場合は利用ができます。
財形貯蓄について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
(2)公的年金の受給年齢の繰り下げ
公的年金の受給開始年齢は、原則65歳となっています。(生年月日によって60歳~64歳で受給できる人もいる)
しかし、受給開始年齢を遅らせることで、年金の受給額を増やすことができます。
繰り下げは1ヶ月単位で行うことができ、1ヶ月当たり本来の年金額の0.7%が増額されます。
例えば、受給開始年齢を70歳としたならば、42%(0.7×12×5=42)増となります。
2022年4月からは、75歳まで引き下げが可能となり、75歳を開始年齢とすると84%増にもなります。そして、その増額率は一生変わりません。
ただし、年金を繰り下げる分、年金をもらい始める年齢が遅くなります。
そのため、何歳まで働けるかを考え、受給開始年齢を決めることが大切です。
(3)公的年金の上乗せ制度の利用
国民年金とは別に、任意で付加年金に加入することができる人もいます。
加入条件は、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者です。
しかし、国民年金基金に加入している人は、付加年金の保険料を納付することはできません。
月々の保険料は400円で、付加年金の年金額は、200円×付加保険料の納付済期間の月数で計算されます。
例えば、40年間付加保険料を納付したとすると、200円×480月で年金額は、96,000円となります。
つまり、2年を過ぎた時点で、既に支払った保険料の元がとれるということになります。
また、この付加年金の受給も繰り下げることができ、老齢基礎年金と同じ割合で増額となります。
限られた人にはなりますが、最も負担感が少なく気軽に始められる制度とも言えます。
(4)税制優遇制度を利用した資産運用
日本の預金金利はかなり低く、お金を預けていてもほとんど増えません。
預金などの金融資産だけで老後に備えるのが心配な方は、持っている資産を運用するのも選択肢のひとつです。
初めて資産運用をするなら、新NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を利用するのがよいでしょう。
新NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠の2つがあり、どちらも利益全額が所得控除となるのが特徴です。
NISAについて詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
また、私が講師を務める「新NISA制度丸わかりセミナー」の動画をLINE友達限定にて公開しています。
- ✅つみたてNISAの落とし穴
- ✅新NISAの注意点
- ✅実際に私が実践している投資商品
- ✅成功するための鉄則
などリアルな情報がたくさんです。つみたてNISAで損をしている方、これからNISAを検討している方は、ぜひご覧ください。
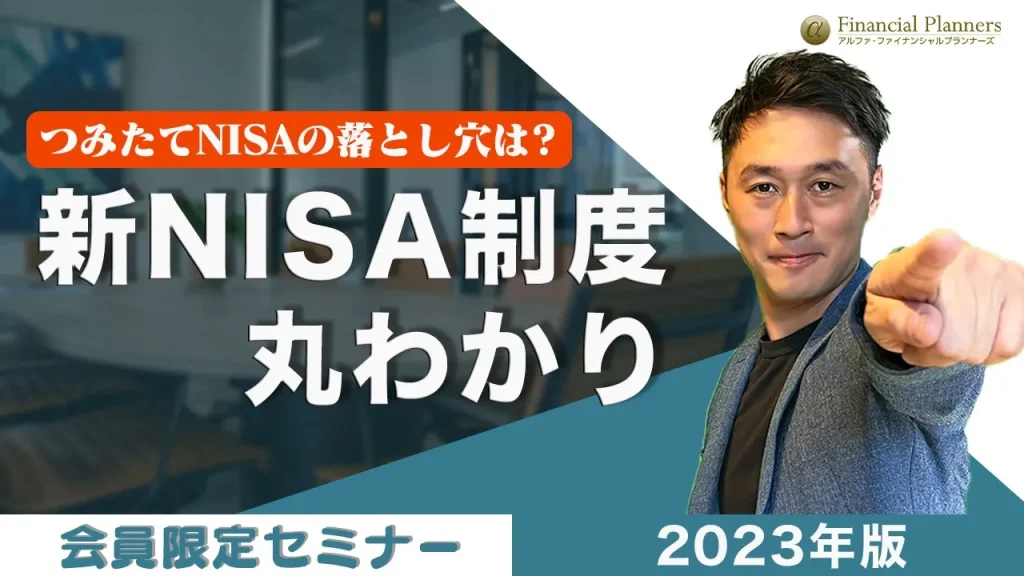
iDeCoは個人型確定拠出年金ともよばれる非課税制度です。
掛金が全額非課税になるため、お得に資産運用ができます。
iDeCo(イデコ)について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
新NISA(つみたて投資枠)もiDeCoも一定金額を積み立てるため、長期的な運用を目的とする金融商品です。
購入できる銘柄は金融機関によって異なりますので、自分に合った商品を選びましょう。
(5)複利効果のある投資信託を活用した資産運用
投資信託で資産運用するのもひとつの方法です。
投資信託とは、投資のプロに資産を預けて代わりに運用してもらう運用方法です。
さまざまな国の株式や債券などに少額で分散投資ができるため、リスクを抑えながら投資ができます。
ただし、少額投資とはいえ元本割れするリスクはありますので、投資信託の仕組みをきちんと理解してから運用することが必要です。
また、商品や購入する金融機関によって手数料(信託報酬、購入手数料)が異なりますのでご注意ください。
さらに、複利効果のある商品と無い商品もあります。
わかりやすい例を上げると、分配型の商品なのか分配なしの商品なのかです。
投資信託は分配金ありのものであったとしても、分配金を再投資(もらう分配金を自動的に積立にまわす)することもできますが、その商品を契約している人の多くが分配金を受け取っています。
ということは、一人が分配金再投資をしていたとして、大多数が受け取ってしまっていたら全体運用的には複利効果を得ることは難しくなります。
そのあたりの注意を払いながら購入しましょう。
ちなみに、新NISAの制度では毎月分配型の商品は選択対象外となりますので、新NISAの対象であったら特に気にせず選択してしまって問題ありません。
投資信託について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
(6)不動産投資など安定した家賃収入を得る投資
不動産に投資し、賃貸として貸し出すことで毎月家賃収入を得るのも資産運用のひとつの考え方です。
不動産投資と聞くと多額の資金が必要なイメージがありますが、中には少額から不動産投資ができる不動産投資信託や不動産クラウドファンディングなど様々あるので、興味のある方は不動産投資も検討してみてはいかがでしょうか。
不動産投資をする際のリスクや回避策について詳しく知りたい方は、下記記事を参考にしてみてください。
老後資金に不安な方はFPに相談

自分の老後資金について不安がある方は、FPへの相談がおすすめです。
FPとはファイナンシャルプランナーともよばれるお金の専門家を指し、お金に関する悩みを解消してくれます。
(1)FPに何が相談できる
FPは基本的にお金に関することなら何でも相談が可能です。
主に下記のような内容を相談できます。
- ✅資産形成のアドバイスや運用商品の一般的な説明
- ✅貯金の増やし方や節約方法
- ✅保険の見直し
- ✅住宅ローン
- ✅相続 など
(2)FPに相談するメリット
お金に関する悩みごとがあったとしても、なかなか他人には相談しにくいものです。
ただし、FPといっても独立系と金融機関系の2つが存在します。
金融機関系は、保険会社系なら保険商品を提案され、銀行、証券系なら投資信託や株を提案されます。
幅広く中立にアドバイスがほしいと思ったら独立系FPを選択することがおすすめです。
まとめ

この記事では、老後に備えた老後資金の計算方法や資金を準備するコツを紹介してきました。
長寿化している現代において、老後2000万円問題は今後どんどん深刻化することが予想されています。
100歳まで安心して長生きするためには、早い段階から老後資金がいくら必要なのかを把握し、逆算して資金を用意しておく必要があります。
また、資金準備には貯蓄だけでなく資産運用も大切です。
お金を貯めるだけでなく運用することも考えながら、正しい知識と確かな情報で老後に備えてお金を増やしておきましょう。
本記事が、老後の生活について考えるきっかけになりましたら幸いです。
著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆
アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。























