サラリーマンにおすすめの投資6選!失敗しないためのポイントも解説

昨今「貯蓄から投資へ」や「老後2,000万円問題」など、投資の必要性がどんどん重要視になり「自分も始めてようか…」と、現在考えているサラリーマンの方も少なくないでしょう。
しかし、本業がありながら、どの投資商品を選んだらいいのか、いくら投資に回せるかなどわからないことも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では「サラリーマンこそ投資する必要性がある」をはじめ、おすすめの投資商品や失敗しないための注意点を具体的に解説していきます。
これから資産運用を考えているサラリーマンの方は、ぜひ参考にしてみてください。
サラリーマンこそ投資を始めるべき理由

なぜ、サラリーマンに投資(資産運用)が必要か、その理由は複数ありますが、主に「老後資金の備え」や「余裕のある暮らし」の2つを挙げることができます。
近年、老後30年間で生活資金2,000万円が不足すると言われている、いわゆる老後2,000万円問題が物議をかもしています。
老後の資金として年金をあてにしている方も少なくないでしょう。ですが近年の少子化により、年金生活者を支える現役世代は減少しています。
集まる掛金が少なくなれば、年金だけに頼るのはリスクです。その他、世界の中でも日本は賃金が上がりません。
給料が上がらないのに輸入品の物価が高くなれば、余裕のある暮らしは難しくなります。つまり、給与だけでは余裕のある生活をするのに難しくなっているのです。このような理由から、サラリーマンには投資が必要と言えるのです。
サラリーマンにおすすめの投資商品6選
ここでは、本業がありながらのサラリーマンにとって、始めやすいオススメの投資商品を6つ紹介します。商品特徴を説明しているので、自分に合う投資商品をチェックしてみてください。
(1)投資信託
「投資信託」とは、投資家から集めた資金を経済・金融の専門家(ファンドマネージャー)が、あなたに代わって運用してくれる金融商品です。
運用を専門家にお願いできるため、投資に関する知識が不十分でも簡単に始めやすいといえます。
また、1万円などの少額からはじめられるため、個人だと投資しにくい株や債券などにも出資できるのが魅力です。
投資信託は特定の企業に投資するのではなく、テーマごとに複数の投資先に分散投資できるため、リスク分散ができる点でも強みです。
手間がかからず、初心者でも実践しやすい投資信託をぜひ検討してみてください。
投資信託についてより詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
なお、下記動画では投資信託で絶対に買ってはいけない商品を解説していますので、損をしたくない方はぜひご覧ください。
(2)不動産投資
「不動産投資」とは、マンションやアパートなどの不動産を購入し、それを人に貸すことで家賃収入を得ることを主とした投資です。
運用が上手くいけば、不労所得や将来的に大きな利益を得ることが可能です。
不動産投資の場合、資産価値が比較的変動しない理由から、株やFXなどのハイリスク・ハイリターン投資と比べ、ミドルリスク・ミドルリターン投資だといわれます。
とはいえ空室や家賃滞納といったリスクはつきものです。不動産投資の知識がまったくない初心者の方は、物件選びなどで失敗する可能性が高いため勉強は必須です。
不動産投資のリスクについて詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
(3)金(ゴールド)投資
「金(ゴールド)投資」とは、名前の通り金を売買する投資商品です。
株や債券などは、例えば経済状況が悪化すれば破綻のリスクも考えられますが、金の場合はその価値がなくなることがありません。
また金には「有事の金」という言葉があるのですが、世界情勢の混乱時に価格が上がる傾向にあります。そのためリスク回避の目的に購入している方も少なくありません。
ただし金投資には利子や配当がありません。得られるのは値上がり益のみです。
また、金貨や金地金などの現物資産で購入する際は、盗難のリスクがあるためその点は注意が必要です。
金(ゴールド)投資について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
(4)外貨預金
「外貨預金」とは、日本円以外の通貨で預金することです。通常外国の通貨の方が、日本円と比べて金利が高い傾向にあります。
例えば、三井住友信託銀行の2022年12月5日時点の「外貨定期預金(1年)」の金利を見てみると、下記の通りでした。
- ☑日本円:0.002%
- ☑ユーロ:0.010%
- ☑豪ドル:0.10%
- ☑米ドル:0.10%
- ☑英ポンド:0.35%
- ☑NZドル:0.75%
つまり、外貨で預金する方がより好ましい運用結果が期待できると言えます。
ただし、預金した外貨を円に交換する際、預金した時点より円高になっていると、元本割れのリスクもあるのでその点は理解しておいてください。
(5)株式投資
「株式投資」とは、株式会社が発行した株を売買して、利益や配当金を得るものです。
株式投資の代表的な利益に「値上がり益(キャピタルゲイン)」があります。安いときに買って高い時に売ることで得られる利益です。
他にも、特定の日に株を保有していることで得られる「配当金(インカムゲイン)」や、日本株の中にはカタログギフトなどの「株主優待」を提供している企業もあります。
メリットが多い印象を受けますが、株式投資には株価が下がって損をするリスクや、投資していた企業が倒産してしまうなどのリスクもあることを覚えておきましょう。
株式投資で勝つためには、情報収集や冷静な判断、そして分析が必要です。
(6)ETF
「ETF」とは上場投資信託と呼ばれるもので、通常の投資信託とは異なり、証券取引所に上場している株式と同様に取引が可能です。
ETFのメリットは分散投資、少額からはじめられる、リアルタイムで取引可能といった点です。
一方、通常の投資信託と比較し商品が少ない、また自動的な積立ができないケースが多いといったデメリットもあります。
分散投資や、売買のタイミングを自分で決めたいという人は、ETFを検討してみてください。
サラリーマンが投資をする上で心がける3つのこと

投資はただ漠然とやっても利益を得られません。そこでサラリーマンが心がけるべき、投資の3大原則といわれる「長期・積立・分散」の3つを解説します。
(1)長期投資
「長期投資」とは、短期間に売買するのではなく長期保有(数年~数十年)で投資を行うことをいいます。
長期的な投資のメリットは「複利効果を活かせる」点です。
複利とは、元本についた利子を次の投資に組み入れ、元本を増やしていく仕組みです。参考の計算式は「複利=(元本+前年利子)×金利」です。
例えば100万円を年利5%で運用した場合、1年後には5万円の利子が発生します。複利では、この利子分の5万円を含めた金額で再度運用されます。
投資期間が長くなれば、それだけ複利の恩恵を大きく受けられるのです。
(2)分散投資
2つ目は「分散投資」です。こちらは、投資対象を1つに絞るのではなく、複数の種類の商品に分散して投資するやり方です。
例えば1つの銘柄にだけしか投資しないと、暴落した際に資産が大きく減ってしまう恐れがあります。
投資には「卵は1つのカゴに盛るな」という言葉があります。つまり一極集中だと何かあったときのリスクに耐えられません。
異なる性質の商品に投資していれば、一方の価格が下がってももう1つでマイナスをカバーできる可能性があります。
(3)積立投資
「積立投資」とは、例えば月々5万円など、一定期間定期的に決まった金額で同じ銘柄を購入していく投資手法です。
積立投資なら、忙しいサラリーマンでも購入のタイミングに悩まなくて済みます。
なお、積立投資では時間分散の有効性、つまり「ドルコスト平均法」により価格のブレが抑えられるのも利点です。
価格が安いときにたくさん買う、そして価格が高いときは少なく買うことで、平均購入単価が抑えられる投資法です。
サラリーマンが投資で注意すべき7つのポイント
次に、サラリーマンが投資を行う上で気を付けるべきポイントを7つお伝えします。
本業をおろそかにしない、計画性を持つなど投資で失敗しないために必ず覚えておきたい内容です。成功するためにぜひ確認してください。
(1)本業に影響しないよう配慮する
まずは「本業に影響しないよう配慮すること」です。例えば株式投資をはじめてみると、株価の動きが気になって本業に身が入らないといった人も少なくありません。
それによって仕事上のミスが起きてしまっては、仕事の評価が下がってしまいます。
サラリーマン投資家が心がけるのは長期間の投資です。短期の動きを気にせず、それよりも自分自身のスキルを高めていくことで、収入アップを狙いましょう。
(2)就業規則に違反していないかを確認する
サラリーマンが投資を行う際は「就業規則に違反していないか」確認することも大切です。
例えば副業禁止の公務員の場合、条件によっては不動産投資ができないケースもあります。無視した場合、最悪免職処分を受ける可能性もあるため注意しなくてはいけません。
また、例えば証券会社や銀行で働いている人が株式投資を行う際には、事前の届け出が必要となるケースがほとんどです。勤務先に確認しましょう。
トラブルを起こさないためにも、就業規則は事前に確認しておきましょう。
なお、公務員が不動産投資をする際の注意点について、詳しくは下記記事を参照にしてみてください。
(3)投資は計画性を持って行うこと
投資は「計画性」を持って行いましょう。例えば短期で結果を出したいのか、それとも長期間継続するのか、それによって選ぶ投資商品が異なります。
また、毎月生活費とは別にいくら投資に回せるのかも事前に決めておくべきです。何も考えず投資してしまうと、生活に影響してしまいます。必ず余裕資金で行いましょう。
投資をする際は商品や投資金額を決め、計画性そして目的を持って行うのが、失敗しないコツです。
(4)NISAやiDeCoなどの節税を活用する
サラリーマンが投資を行う際は「NISA(少額投資非課税制度)」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」などの節税を活用しましょう。
一般的なNISAでは年間120万円(非課税期間:最長5年間)までが非課税、積み立てNISAには年間40万円(非課税期間:最長20年間)までの非課税投資枠が設けられています。
また、売買手数料も無料です。例えば投資信託の分配金や、個別株の売却益などには原則20.315%の税金がかかるため、それが非課税となるメリットは大きいです。
興味がある場合は証券会社でNISAの口座開設を検討してみましょう。
そしてiDeCoの場合、掛金全額が所得控除の対象となり、税金が軽減されるのがメリットです。
つみたてNISA、iDeCo(イデコ)について詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
また、私が講師を務める「新NISA制度丸わかりセミナー」の動画をLINE友達限定にて公開しています。
- つみたてNISAの落とし穴
- 新NISAの注意点
- 実際に私が実践している投資商品
- 成功するための鉄則
などリアルな情報がたくさんです。つみたてNISAで損をしている方、これからNISAを検討している方は、ぜひご覧ください。
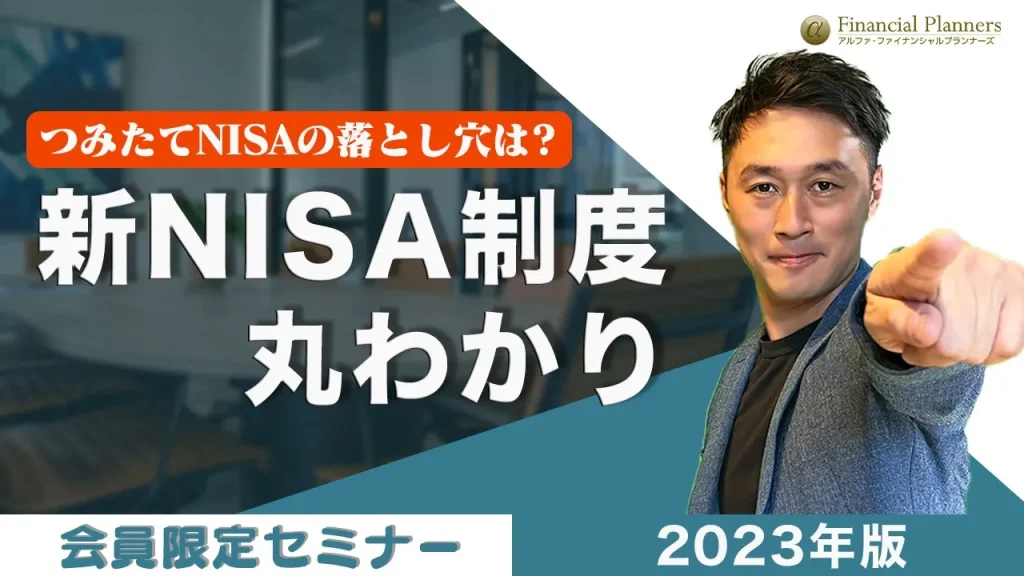
(5)無理のない投資プランを立てる
「無理のない投資プランを立てる」ことも、サラリーマンが投資を行う上で重要です。
「FXで10倍のレバレッジを利用して、短期で儲けてやろう」などと考える人もいますが、その結果取り返しのつかない事態になってしまった、という失敗例は少なくありません。
投資初心者は「少額投資」「積立投資」が、分散などリスク軽減のためおすすめです。赤字になっては資産形成の意味がありません。
つまり、ご自身の状況、属性に合った投資プランを立てる事が重要です。投資プランの立て方がわからない方は、ぜひ一度我々FPに相談してみてください。
(6)短期投資やデイトレードは避ける
サラリーマンが投資をする際は「短期投資やデイトレード」は避けましょう。デイトレードとは、数時間もしくは当日中に取引を済ませる投資手法です。
短期間のうちに売買を積み重ねていくため、平日忙しいサラリーマンには向いていません。
また、短期投資で常に相場や値動きを気にしなくてはいけない状況では、メンタル的に余裕が持てません。
その点長期投資であれば、日々の値動きを短期投資ほど気にしなくてもよいため、心理的に安心できます。
(7)属性がいいことからカモにされやすい
サラリーマンは「属性がいいことからカモにされやすい」ということも覚えておきましょう。
特に不動産投資で金融機関から融資を受ける際、毎月決まった収入が得られる会社員だと、自営業やフリーランスと比較し有利です。
そのため、サラリーマンはカモにされるリスクがあるのも確かです。
不動産投資は不動産投資ならではのメリットが多い投資商品ではありますが、全く知識がない、営業マンに言われるがままに投資すると、失敗するケースが多くあります。
せっかくの高属性なので、それを活用して不動産投資をするのは一つの選択肢としてありますが、きちんと自分の投資目的に合っているかどうかを判断するようにしましょう。
不動産投資の失敗例を下記記事にて紹介していますので、事前に把握しておきたい方はぜひ読んでみてください。
サラリーマンは投資で得た利益はどうなる?

サラリーマンが投資で得た収益については、確定申告する必要があるケースがあります。
例えば株取引や投資信託の場合、源泉徴収されない証券口座(一般口座など)で運用しているのであれば税務署に申告・納税が必要です。
一方、源泉徴収ありの特定口座で運用していれば基本的に申告不要です。(※損失があったときの繰り越し控除は除く)
また、不動産投資の場合不動産所得が20万円以下なら確定申告の義務はありませんが、超えるようであれば確定申告が必要となります。
信頼できる専門家に相談する

投資初心者の方は、「どの投資商品を選べばよいかわからない」「自分に合った投資方法がわからない」という人も多いでしょう。
そのような場合は、信頼できる専門家に相談してみましょう。
お金のプロフェッショナルである我々FP(ファイナンシャルプランナー)であれば、あなたの投資目的に適った投資商品、投資プランを提案させて頂きます。
まとめ

今回は、サラリーマンが投資を始めるべき理由やおすすめの投資商品、そして運用方法などについて徹底解説しました。
上がらない給料、少ない年金など将来の不安を考えると、サラリーマンに投資が必須なのは明確です。とはいえ、生活に影響しない余剰資金で無理なく行いましょう。
また、業務にも影響しないよう注意してください。自分に合った投資商品や始め方、資産形成がわからないような場合は、ぜひ気軽に当社のFPに相談してみてください。
著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆
アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。




















