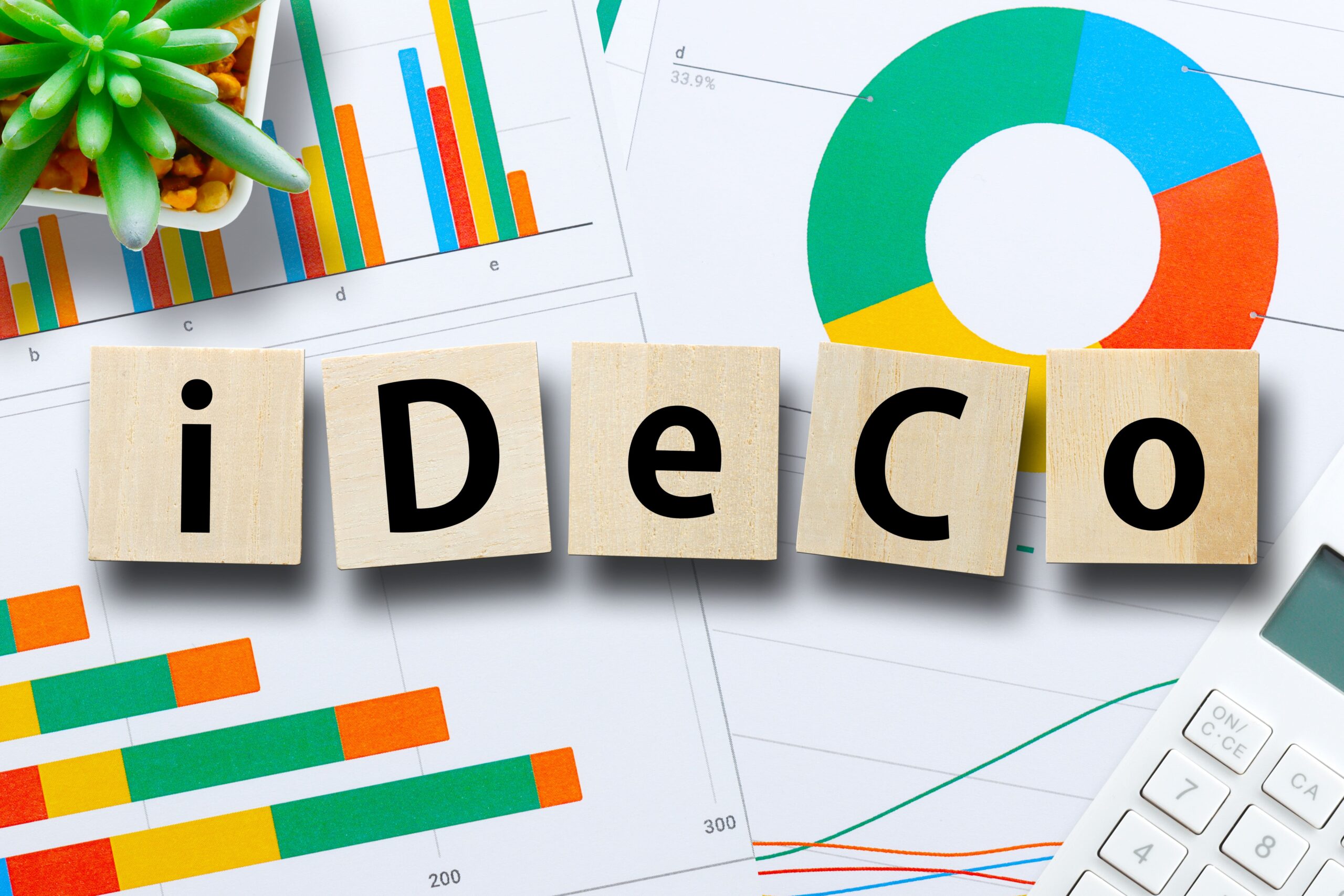妊娠・出産に費用はいくら?自己負担額を抑えるコツや助成制度を解説

妊娠や出産はとても嬉しいニュースです。
一方、出産費用について不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。
特に初めての妊娠では妊婦検診や出産費用の見当がつかず、「妊娠したけどお金がない」と心配が募る方もいるかもしれません。
本記事では、妊娠・出産にかかるお金の疑問が解決できるように、出産費用や助成制度の詳細について丁寧に解説します。
さらに、出産費用を抑えるコツや妊娠が分かったらやっておきたいこともまとめましたので、妊娠や出産にまつわるお金の不安をグッと減らせる内容になっています。
安心して出産に臨むためにもぜひ最後までお読みください。
出産費用の自己負担額の全国平均は「482,294円」

厚生労働省が令和5年に出したデータによると、令和4年度の入院費用・分娩費用など出産にかかる費用は全国平均で482,294円でした。(正常分娩のみ)
施設別の出産費用平均額は以下のとおりです。
- ✅公的病院:463,450円
- ✅私的病院:506,264円
- ✅診療所(助産所含む):478,509円
(参照:出産費用の見える化等について|厚生労働省保険局保険課)
出産する施設によって多少異なりますが、一般的な出産費用の総額は約50万円と考えて良いでしょう。
妊娠・出産する時に関わる費用大きく4つ
子供を産むときには出産費用の他にも必要な費用があります。この項では妊娠してから出産までにかかる費用を4つにわけて解説します。
(1)妊婦健診時の費用
妊婦健診は妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために欠かせないものです。
厚生労働省が作成した「妊婦健診のリーフレット」には、妊婦健診のスケジュール例が以下のように記載されています。
- ✅妊娠初期~23週:4週間に1回(計4回)
- ✅妊娠24~35週:2週間に1回(計6回)
- ✅妊娠36週~出産:1週間に1回(計4回)
1回目の妊婦検診が8週目の場合、標準的な受診回数は合計14回です。
妊娠は病気ではないため、産婦人科での健診費用は保険が使えず全額自己負担となります。
妊婦健診費用は受診する病院によって異なりますが、妊娠の有無を検査する初診は約1万円、2回目以降は5,000~7,000円が相場です。
週数によっては検査項目が追加されるため、1回あたり1万円を超える場合もあります。
(2)入院、分娩する時の費用平均「482,294円」
令和4年度の正常分娩における出産費用の全国平均は482,294円ですので、40~50万円が相場と言えます。
(参照:令和5年出産費用の見える化等について|厚生労働省保険局保険課)
入院・分娩する時の費用は、入院する施設や分娩方法によって異なります。
施設や分娩方法によって出産費用がどれくらい異なるかについては、次の項で詳しく説明します。
(3)マタニティ、ベビー用品の費用
マタニティ用品、ベビー用品などの出産準備品を揃えるのにもお金がかかります。いくらかかるかは人によって異なりますが、10~15万円が相場になるでしょう。
マタニティ用品としては以下のようなものが挙げられます。
- ✅マタニティウェア
- ✅マタニティ下着
- ✅マタニティパジャマ
- ✅妊婦帯
- ✅授乳服・授乳用ブラジャー
- ✅産褥ショーツ・産褥パッド
ベビー用品としては以下のようなものが挙げられます。
- ✅服や肌着、靴下
- ✅スタイ(よだれかけ)
- ✅ベビーベッド・布団
- ✅ベビーカー
- ✅チャイルドシート
- ✅ベビーバス
- ✅おむつ・おしりふき
- ✅哺乳瓶
- ✅抱っこひも
なお、市区町村によっては育児用品の購入費助成制度(補助金制度)がありますので、事前に確認しましょう。
(4)その他病気など長期入院する時の入院費
妊娠・出産は、ときに思いがけないトラブルや異常が発生する可能性があり、長期入院が必要になることもあります。
出産時の入院日数は、経腟分娩の場合5,6日間、帝王切開の場合7,8日間が一般的です。
しかし、産後の子宮の状態や体調によっては、入院が延長されるケースもあります。
また、妊娠中にも切迫早産や妊娠高血圧症候群、双子でリスクが高いなどの理由で管理入院が必要となるケースも珍しくありません。
万が一、異常や病気などトラブルが発生した場合は入院費(入院料)が上乗せされる可能性も考慮しておきましょう。
出産費用は基本保険適用外である?

厚生労働省の「国民健康保険の給付について」によると、国民健康保険では疾病や負傷に関しては必要な給付を行いますが、そのなかに妊娠や出産は含まれていません。
そのため、基本的に出産費用は保険適用外です。
ただし、妊娠や出産の中でも異常分娩などで医療行為が必要となった場合は、通常の診療と同様に健康保険の対象になります。
例えば、対象となる例は以下のとおりです。
- ✅妊娠高血圧症候群、妊娠悪阻の処置
- ✅貧血の治療
- ✅帝王切開分娩となった場合の手術費用
- ✅陣痛促進剤の投与、吸引・鉗子分娩による手術費用(異常を理由に行われた医療行為である場合)
自然分娩の介助措置として行われる会陰切開や会陰裂傷縫合術は、保険適用の対象外です。
また、民間の医療保険などは適用されるの?という質問を多くいただきますが、健康保険の適用外となる自然分娩の場合は、基本的には医療保険も適用されません。
帝王切開など医療行為が介入し健康保険が適用される場合のみ、民間の医療保険の対象となります。
しかし、数は少ないですが、自然分娩であっても出産入院時に給付を受けられる民間保険も存在します。
出産時にも補償される保険に加入しておきたい方は、あらかじめ保険会社に確認しておきましょう。
出産費用は様々なケースで変わる
先述したように、出産費用はケースによって異なります。
この項では、出産費用に影響するさまざまなケースを紹介しますので参考にしてください。
(1)出産する時にお住まいの「都道府県」によって変わる
出産費用は都道府県によって異なり、一般的に東京など都市部が高く、地方は低いという傾向にあります。
厚生労働省保険局のによると、令和4年公的病院・正常分娩都道府県別出産費用の平均値は、最も高いのは東京都の562,390円、最も低いのは鳥取県の359,287円です。
東京と鳥取では20万円以上の差があります。
一方で、大阪府や愛知県、福岡県などの地方の大都市が全国平均より低かったり、地方のなかでも山形県や新潟県、茨城県などは50万円を超える平均値となっていたりします。
実家が地方にある場合は、里帰り出産によって出産にかかるお金を節約できるかもしれません。
具体的な出産費用を病院に確認して比較してみましょう。
(2)出産する時の「施設」によって変わる
出産費用は出産する時の施設によって異なります。
分娩できる施設は主に総合病院、産婦人科専門の診療所、助産院(助産所)の3種類あります。
出産費用は各施設の医師やスタッフ、設備によって決まりますので、一般的に平均額が高い順に、病院 > 診療所 >助産院(助産所)となります。
出産費用を抑えたい場合は、医師が常駐せずに助産師が分娩介助をする助産院がおすすめですが、助産院は緊急帝王切開などには対応できません。
もし何かあった場合は緊急で総合病院などに搬送されることになりますので、不安がある方は最初から総合病院を選択することをおすすめします。
(3)出産する時に「産み方」によって変わる
出産費用は出産するときの産み方、つまり分娩方法(出産方法)によって異なります。
分娩方法は大きく分けて「自然分娩」「帝王切開」「無痛分娩(和通分娩)」の3つの方法があります。
➀自然分娩
自然分娩は医学的な処置を施すことなく自然に出産する分娩方法で、基本的に健康保険が適用されず全額自己負担となります。
②帝王切開
逆子など自然に分娩することが難しいと判断された場合に手術によって分娩する方法で、手術は医療行為の対象になりますので健康保険が適用されます。
また、1か月の医療費が上限額を超えた分は差し戻してもらえる高額療養費制度も利用できます。高額療養費制度については次の項で詳しく説明しますので確認してください。
予定帝王切開であれば、自然分娩よりも自己負担額が安くなるケースもあるようです。
一方で、自然分娩から緊急で帝王切開に切り替えたケースは費用も高額になるため、同じ帝王切開でも病院や状況によって金額は異なります。
③無痛分娩
無痛分娩は妊婦の希望によって、麻酔で分娩時の痛みを抑えて出産する方法です。
傷みを和らげる出産方法として和通分娩と呼ばれることもあり、両者には明確な定義分けがなく、どちらも痛みの少ないお産を目指すものです。
なお、基本的には自然分娩ですので保険は適用されません。
麻酔や陣痛促進剤の料金が追加されるので、通常の自然分娩よりも費用がかかります。
(4)出産する時に「曜日・時間」によって変わる
あまり知られていませんが、出産は曜日や時間帯のタイミングによっても費用は異なります。
通常の診療でも深夜や土日は料金が高くなるように、出産も受付時間外や休診日は深夜料金や休日料金が加算される場合があります。
加算される金額は病院によって異なりますが、プラス3~5万円を見ておくと良いでしょう。
妊娠・出産費用の自己負担額を抑えられる助成制度6つ

出産の際にはいくつか助成制度や補助金(助成金)の受給がありますので、上手に利用しましょう。
この項では、出産費用の自己負担額を抑えられる公的支援制度や手続きを6つ徹底解説します。
(1)妊婦健診費用の助成
妊娠中は、母体と赤ちゃんを守るために通常14回ほど妊婦健診に通院します。
その際、住んでいる自治体から妊婦検診費用を一部助成してもらうことが可能です。
流れとしては、病院の診察により妊娠が確定した後、自治体の窓口に妊娠の届け出をすると、母子手帳と一緒に「妊婦健康診査費用受診券(補助券)」を受け取れます。
受け取った補助券を次回からの妊婦健診の際に病院の窓口に提出すると、妊婦検診費用から一定額が差し引かれます。
助成金額や妊婦健診の費用は自治体や医療機関によって異なりますが、補助券を使った場合の健診にかかる自己負担額は1回あたり1,000~3,000円前後が目安です。
妊婦健診費用の枚数や助成金額は各都道府県の自治体によって異なりますので、お住まいの自治体のホームページや窓口で確認しましょう。
(2)出産育児一時金
先述したように、正常分娩は公的医療保険の対象とはなりません。
しかし、妊娠4カ月(85日)以上の人が出産したときは、公的医療保険から出産育児一時金の支給を受けられます
出産育児一時金は令和5年(2023年)3月31日までの出産の場合は1児につき42万円でしたが、令和5年4月1日以降の出産の場合、1児につき50万円(産科医療補償制度に加入の医療機関などで妊娠週数22週以降に出産した場合)に増額されました。
多くの医療機関で導入されている「直接支払制度」を利用すれば、医療機関での支払い額は50万円を超過した部分のみで済みます。
正常分娩の出産費用は全国平均で482,294円であるため、出産育児一時金制度を使うと持ち出し(自己負担)なく出産できるケースも多いでしょう。
また、出産費用が50万円に満たなかった際の余剰分も、手続きをすれば還元されます。
「出産するためのお金がない」と心配していた方も、トラブルのない自然分娩であれば大きな費用負担なく出産できるでしょう。
詳細は全国健康保険協会の「出産一時金について」を確認してください。
(3)出産手当金
出産のため会社を休み給料が支払われなかった場合は、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
対象は出産の日(実際の出産が予定日の後になったときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内となり、会社を休んだ期間を対象として支給されます。
出産手当金の額は以下の計算式によって求められます。
- ✅1日あたりの金額=支給開始日(※)の以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
※最初に給付が支給された日のこと
なお、出産手当金の金額の計算方法について詳細は全国健康保険協会の「出産で会社を休んだとき」を確認してください。
「出産育児一時金」は国民健康保険と健康保険の両方で運用されている制度ですが、「出産手当金」は健康保険、つまり勤務先で加入する保険の被保険者のみが受け取れる制度です。
自営業などで国民健康保険に加入している方や、夫の扶養家族として健康保険に加入している方は支給対象外となります。
(4)育児休業給付金
育児休業給付金とは、育休取得時に勤務先の雇用保険から支払われる給付金のことです。
原則1歳未満(最長2歳まで)の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合、一定の要件を満たすことで「育児休業給付金」を受けられます。
育児休業の期間中、休業開始時賃金日額の5割~7割弱の金額が支給され、性別に関わらず夫婦同時に育児休業給付金を受け取ることも可能です。また、2022年10月から新設された「産後パパ育休」により、男性の育児休業がさらに取得しやすくなりました。
産後パパ育休は、子の出生日から8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として2回に分割して育児休業が取得でき、一定の要件を満たすことで「出生時育児休業給付金」を受けられます。
支給要件、申請期間や申請手続き、支給額など詳細は厚生労働省の「育児休業給付について」を確認してください。
なお、育児休業給付金は雇用保険の加入者であること(基本的には会社員)が条件です。
個人事業主や自営業者、フリーランスは対象外ですので注意してください。
(5)高額医療費制度
高額療養費制度とは1ヶ月(1日~末日まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、医療費の家計負担が重くならないように上限額を超えた分が後から支給される制度のことです。
自然分娩では対象になりませんが、帝王切開や吸引・鉗子分娩などの医療行為がなされた場合は高額療養費制度の適用対象になります。
また、帝王切開が予定されている場合など医療費が高額になると分かっているときは、あらかじめ「限度額適用認定証」を提示すると、事前に支払い額の負担が減らせます。
(6)医療費控除
医療費控除とは、1年間にかかった医療費の世帯合計額が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合に、一定額が所得控除の対象となる制度のことです。
妊娠中に受けた健診や検査、産後の1か月健診交通費なども医療費控除の対象になります。
また、分娩費用や入院中の食事代や病院都合の差額ベッド代など、病院に対して支払った費用も一般的に医療費控除の対象となります。
ただし、出産育児一時金など保険金で補填される金額は差し引かなければなりません。
医療費控除を利用する際は確定申告をする必要があるため、お住まいの税務署に必要書類を忘れずに提出しましょう。
医療費控除の詳細は国税庁の「医療費を支払ったとき」も参照ください。
簡単にできる妊娠・出産費用を抑えるコツ

出産費用についてかかる費用や公的制度を解説してきました。
この項では、出産や出産準備にかかる出費を抑えるコツを説明します。
(1)出産する病院を複数で比較する
妊娠がわかったら出産する病院の候補をいくつかピックアップして、医療機関を比較検討することをおすすめします。
総合病院、クリニック、助産所によって分娩費用や入院時の個室代は異なります。公的な助成制度を確認し、予算内の医療機関かどうか判断しましょう。
初回の受診時に、出産にかかる費用を医療機関に確認することもできます。
費用面も重要な判断基準である一方、万が一の事態に備えて自宅から医療機関までの距離やアクセスの良さ、設備が整っているかどうかも大切なポイントです。
安心して出産できる医療機関を選ぶためには、各医療機関の特徴を知る必要があります。
周囲の出産経験者に利用した病院の情報を聞いたり、掲示板やSNSなどを利用したりして、確かな情報を手に入れましょう。
(2)ベビー用品は少しずつ買い足せばいい
赤ちゃんの衣類やスタイ、グッズやおもちゃなどのベビー用品は、子どもが生まれる前に全て揃えるのではなく、出産後に少しずつ買い足すことをおすすめします。
なぜなら、必要なものは人によって異なるからです。
初めての妊娠や出産の場合は必要なものが分からず、ネットや本などで調べたベビーグッズやマタニティグッズを完璧に揃えたくなるかもしれません。
しかし、買ったものを使わなかったら無駄になってしまいます。
外出ができない産後であっても、必要なものはネット通販で届けてもらうことも可能です。
赤ちゃん用品は、産後すぐに必要となる最低限のものだけ準備し、必要を感じたときにその都度揃えていくほうがトータルでかかる費用を抑えられるでしょう。
(3)レンタルサービスも検討する
ベビー用品はレンタルサービスを利用すると費用を抑えられます。特にベビーベッドやハイローチェアなど使用期間が短いものは、レンタルが賢い選択肢といえます。
最近はレンタルも種類が豊富です。また、赤ちゃんに合わなかった場合でも、買い直しの費用や手間を省けます。
レンタルサービスの中には数日間や数週間だけレンタルできる会社もありますので、里帰り中だけ利用するときにも便利です。
レンタルするときの注意点としては、お住まいの地域が対象エリアに含まれているかどうかという点です。
現在はさまざまな会社がベビー用品のレンタルサービスをしていますので、出産前からいくつか比較、検討しておきましょう。
妊娠が分かったらやっておきたいこと3つ

最後に、妊娠が分かったらやっておきたいことを3つ説明します。
(1)子どもの教育方針を話し合う
妊娠が分かったら、子どもの教育方針について夫婦で話し合いましょう。
生まれてもないのに教育方針とはまだ早いのでは?と思うかもしれませんが、時間に余裕がある今だからこそ、出産までにゆっくり夫婦で話し合うことをおすすめします。
具体的には、幼稚園もしくは保育園〜大学まで「公立か私立か」だけでも決めておくと良いでしょう。
特に、中学受験までは子どもの意思より親の教育方針が強く反映されます。
受験するときになって夫婦の意見が別れないように、今から話し合っておきましょう。
(2)子どもの教育資金いくらかかるかを把握する
文部科学省の令和3年度子供の学習費調査によると、子ども一人幼稚園から大学までにかかる教育費用の目安は約1,000万円です。
また、私立に通う場合は約2,500万円かかるというデータがあり、公立より多額の費用が必要となります。
つまり、生活費とは別に、最低でも一人につき1,000万円程度を教育資金として用意しなければなりません。
子どもにかかる教育資金、そして現状の貯蓄額やこれから得られる収入の予測額などを把握して、どのように備えていくかを検討しておきましょう。
子どもの教育資金がいくらかかるかについてより詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
(3)教育資金の計画を早めに立てる
多額な教育資金を準備するためには、教育資金を貯めるための計画をできるだけ早く立てましょう。
大きな資産を作るには、「時間」が強力な味方となります。少額ずつの積み立てでも長期間続けるとまとまった額に成長していくため、1日でも早くスタートを切ることが大切です。
教育資金準備の手段としては、一般的な貯金の他に以下の3パターンがあります。
- 積み立て:
保険商品、金融商品を活用する方法です。保険会社をはじめ、さまざまな学資保険が提供されています。最初の一歩としてホームページなどで調べてみましょう。 - 借り入れ:
民間融資、公的融資、親族から融資を受ける方法です。自分で全額貯めるのが難しい場合は借り入れという選択肢もあります。まずは親族に相談してみるのが良いでしょう。 - 贈与
親族等から資金の贈与を受ける方法です。注意点としては多額の贈与税などが発生する場合もあります。贈与税が発生しない暦年贈与などを上手に利用しましょう。
上記も参考にし、教育資金の計画を早めに立てることをおすすめします。
より効率よく準備したい方は、ぜひ下記記事も併せてお読みください。
教育資金に不安な方はFPに相談する

妊娠や出産費用、そして高額な教育資金。「子どもを産んで育てるにはこんなにお金が必要なのか」と一人で落ち込んでしまう前に、専門家の力を借りましょう。
「餅は餅屋」という有名なことわざがあるように、教育資金のことはお金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめです。
妊娠・出産、という大きなイベントの中で教育資金まで考える余裕はなかなかないかもしれません。
しかし、出産した後は子育てに忙しい日々が待ち受けています。
これからの長い人生の「お金」についてじっくり考えられえるのは、妊娠中の今が絶好のチャンスともいえるでしょう。
(1)FPに何が相談できる
FPに相談するのが初めての方は「教育資金もFPに相談できるの?」と思っているかもしれません。
FPはお金の専門家ですので、もちろん教育資金についてもサポートできます。
相談できる内容を下記に挙げましたので参考にしてください。
- ✅家計の見直し・節約の仕方、家計簿の付け方
- ✅ライフプランの作成方法
- ✅老後資金・年金の運用
- ✅教育資金や子どもの教育費、贈与について
- ✅出産費用や入院費用、保育料について
- ✅住宅購入の際の頭金・住宅ローン返済
- ✅資産運用や資産形成の方法、投資について
- ✅生命保険など保険全般
他にもお金に関する不安や悩みがあれば、まずはアドバイザーに相談してみましょう。
(2)FPに相談するメリット
FPに相談できる内容が理解できても、相談して得られるメリットがわからない方もいるでしょう。
FPに相談すると、お金に関する知識やスキルが身に付けられるだけでなく、将来に対して前向きな気持ちで向き合えるようになります。
- ✅プロに家計の見直しをしてもらう→生活費が削減できる
- ✅ライフプランを立ててもらえる→将来の夢や目標が実現できる
- ✅投資方法や運用方法を相談できる→不安なく投資が始められる
- ✅保険の見直しをしてもらえる→家族の保険料が軽減できる
- ✅教育資金の相談ができる→早い段階から無理なく教育資金を貯められる
上記はほんの一例です。
FPに相談するメリットは「お金の悩みや疑問を解決できること」です。
自分一人では気が付きにくい節約ポイントや資産を増やす方法をアドバイスしてもらえるので、進むべき道が明確になり効率的なアクションを起こせるようになるでしょう。
出産や子供にかかるお金に不安がある方、妊娠中にお金を貯めたい方は、ささいなことでもまずはお気軽にご相談ください。
まとめ

出産費用の平均金額は約50万円です。また、妊婦健診のため、一般的に14回病院に通い、検査費用1回の費用相場は約3,000〜5,000円となります。
妊娠から出産まではお金が必要ですが、出産育児一時金は令和5年4月1日以降の出産から1児につき42万円から50万円の支給に増額されました。
また、出産育児一時金の他にも妊婦健診費用の助成制度や出産手当金などもありますので、費用について必要以上に不安になることはないでしょう。
一方、万が一のことに備えたり、予定外に費用がかかったりすることを想定し、ある程度預貯金をしておくこともおすすめします。
ご自身と赤ちゃんの健康を一番に考えて、楽しいマタニティライフを送ってください。
著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆
アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。
最新の投稿
 税金2024年2月27日不動産を相続したら相続税はいくら?手続き、計算方法や活用方法を解説
税金2024年2月27日不動産を相続したら相続税はいくら?手続き、計算方法や活用方法を解説 不動産投資2024年2月24日不動産所得がある場合は確定申告が必要!計算方法や申請手順を解説
不動産投資2024年2月24日不動産所得がある場合は確定申告が必要!計算方法や申請手順を解説 税金2024年2月23日不動産の生前贈与はした方がいい?メリット、手続きや注意点を解説
税金2024年2月23日不動産の生前贈与はした方がいい?メリット、手続きや注意点を解説 不動産投資2024年2月21日不動産投資クラウドファンディングとは?おすすめ商品も合わせて紹介
不動産投資2024年2月21日不動産投資クラウドファンディングとは?おすすめ商品も合わせて紹介