子どものために毎月いくら貯金すべき?必要な貯金額と貯金方法を紹介

これから子育てを始めるにあたり、「子どものための貯金はいくら用意すべきか」と気にされている方は多いのではないでしょうか。
子育てには多額の費用がかかるというイメージがある一方で、具体的な金額を把握するのは難しいものです。
本記事では、「子どものための貯金はいくら必要なのか」という疑問にお答えするため、必要な金額や効果的な貯蓄方法を徹底解説します。
子どものための貯金についてお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
年代別!子育て世代の貯蓄額を確認しよう

子育て世代の貯蓄額はどのくらいなのでしょうか。
ここでは、金融広報中央委員会が公表している子育て世代の貯蓄額の中央値を年代別に確認してみましょう。
中央値とは、データを数値順に並べた際のちょうど真ん中の値を指します。
平均値は、極端に貯蓄額の多い世帯の影響を受けやすく、実態より高い値になる傾向があります。
そのため、この記事ではより実態を反映しているとされる中央値をご紹介します。
| 世帯主の年齢 | 金融資産保有世帯 | 金融資産を保有していない世帯を含む |
| 20代 | 171万円 | 30万円 |
| 30代 | 337万円 | 150万円 |
| 40代 | 500万円 | 220万円 |
| 50代 | 745万円 | 300万円 |
出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 令和5年調査結果」を参考に著者作成
※表の金額は、預貯金、生命保険などの保険商品、有価証券などを含めた金融資産の総額の中央値
幼稚園から大学まで!子どもの教育費はいくらかかる?
次に、子どもの教育費について、幼稚園入園から高校卒業までと大学に分けて詳しく解説します。
(1)幼稚園から高校までにかかる教育費
幼稚園入学園ら高校卒業までにかかる教育費は以下の通りです。
費用の内訳は、大きく以下の3つに分けられます。
・学校教育費:授業料、学費、教科書代など
・学校給食費:学校で提供される給食の費用
・学校外活動費:学習塾や習い事などの費用
全て公立校に通った場合と全て私立校の場合を比較すると、合計費用には約3倍の差があります。
特に、公立小学校と私立小学校では費用差が顕著で、大きな影響を与えるポイントとなります。
ただし、習い事や学習塾の利用状況によっては、教育費を平均よりも抑えられるケースも少なくありません。
| 公立 | 私立 | |
| 幼稚園 | 553,938円 | 1,042,014円 |
| 小学校 | 2,017,590円 | 10,968,672円 |
| 中学校 | 1,627,425円 | 4,681,077円 |
| 高等学校 | 1,793,256円 | 3,090,849円 |
| 合計 | 5,992,209円 | 19,782,612円 |
出典:文部科学省「令和5年度子どもの学習費調査」を参考に著者作成
(2)大学にかかる教育費
大学入学初年度にかかる費用は以下の通りです。
同じ私立大学であっても、進路選択によって費用に大きな差が生じることが分かります。
| 授業料 | 入学金 | 施設設備費 | 合計 | |
| 国公立 | 535,800円 | 282,000円 | 817,800円 | |
| 私立文系 | 827,135円 | 223,867円 | 143,838円 | 1,194,841円 |
| 私立理系 | 1,162,738円 | 234,756円 | 132,956円 | 1,530,451円 |
| 私立医薬系学 | 2,863,713円 | 1,077,425円 | 880,566円 | 4,821,704円 |
出典:文部科学省「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」、「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果」を参考に著者作成
(3)必要となる金額の目安
では、必要となる金額の目安として、全て公立校に通う場合と、全て私立校に通う場合の合計額を見てみましょう。
公立でも約840万円、私立では約2,390万円とかなりの金額差があることがわかります。
①全て公立の場合
| 幼稚園から高校 | 5,992,209円 |
| 大学(入学費用を含めた初年度) | 817,800円 |
| 大学(入学初年度以外の3年間) | 1,607,400円(授業料535,800円×3年) |
| 合計 | 8,417,409円 |
著者作成
②全て私立の場合(大学は私立文系)
| 幼稚園から高校 | 19,782,612円 |
| 大学(入学費用を含めた初年度) | 1,194,841円 |
| 大学(入学初年度以外の3年間 | 2,912,919円 (授業料827,135円×3年+施設設備費143,838円×3年) |
| 合計 | 23,890,372円 |
著者作成
子どものために毎月いくら貯金すればいい?
子どもの成長に伴い、教育費の負担は徐々に大きくなります。
将来の進路によって必要な金額は異なりますが、教育費は高額になるため、計画的に貯蓄しておくことが大切です。
あらかじめ毎月の貯金額の目安を決めておくことで、無理なく資金を準備しやすくなります。
将来の教育費に備えるために、どれくらい貯めればよいのかを考えてみましょう。
(1) 貯金の目的と目標金額を明確にする
貯金を計画的に進めるためには、目的と目標金額を明確にすることが大切です。
何のために貯めるのか、いつまでにいくら必要なのかを具体的に決めておくことで、無理なく貯蓄を続けられます。
目的としては、次のようなことが考えられます。
・大学費用:学費や仕送りに備える
・留学費用:海外での学びの機会を確保する
・成人後の家の購入費用:将来の住宅資金の準備
「いつまでに、いくら貯めるのか」を具体的に決めましょう。
例えば、「大学進学までに300万円」など、目標を数値化すると計画が立てやすくなります。
目的と金額を明確にすることで、貯金のモチベーションが上がり、計画的な資産形成につながります。
早めに目標を設定し、無理のない範囲で貯蓄を始めましょう。
(2) 毎月貯金する目安
子どもの進路によって必要な教育費は異なりますが、計画的に貯蓄を進めることで負担を軽減できます。
ここでは、1つのモデルケースとして、以下の条件で貯金した場合にどれだけ貯まるかを試算してみましょう。
モデルケースの貯蓄額
・0歳から小学校卒業まで:毎月 3万円 貯金
・中学生の期間:毎月 2万円 貯金
・高校生の期間:毎月 1万円 貯金
子どもが成長するにつれて生活費も増えるため、中学・高校と進学するにつれて貯蓄額を少しずつ減らす想定です。
この場合、大学進学時には合計540万円を貯めることができます。
さらに、児童手当を活用することで貯蓄額を増やせます。
2024年10月からは、所得制限の撤廃や支給期間の高校生までの延長が決定しており、児童手当を貯金に回すことで、より多くの教育資金を準備することが可能になります。
次の章では、児童手当についても詳しく説明します。
教育費どうする?子どものために確実に貯金できる6つの方法

子どものための貯金を効率よく増やすには、早い段階で教育方針を明確にし、必要な費用を見える化することが重要です。
公立校に通わせるのか、私立校に通わせるのかによって、貯金の目標額は大きく異なります。
教育方針を早めに決めることで、必要な学費が具体的に把握でき、その後の貯蓄計画や資金運用の戦略を立てやすくなるでしょう。
(1)毎月の給与から定期預金や積立預金をする
月々の貯金額をあらかじめ決めて定期預金や積立預金に入れることで、確実に貯蓄を増やすことができます。
積立預金は、一度設定すると毎月自動的に積み立てが行われるため、貯蓄に効果的な「先取り貯金」の仕組みを簡単に作ることができます。
また、元本保証があり、引き出す時期を自由に設定できるため、安全性や柔軟性を求める教育資金の貯金方法として適しています。
定期預金の金利が高い銀行については、別の記事で詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
(2)出産祝いやお年玉を貯める
出産祝いやお年玉を貯めておく方法は、無理なく子どものための資金を蓄えるのに効果的です。
親としても、子どもがいただいたお金を大切に管理する意識が働きやすく、抵抗なく貯金に回しやすいでしょう。
例えば、株式会社ベビーカレンダーの調査によると、いただいた出産祝いの合計額の平均は1人当たり約43万円でした。
また、学研教育総合研究所の調査結果では、子どもが受け取るお年玉の合計額についての平均値も確認されています。
- ✅小学生:20,225円
- ✅中学生:27,499円
参照:学研教育総合研究所「小学生白書Web版2024年11月調査」,「中学生白書Web版2024年11月調査」
出産祝いと、小学1年生から中学3年生までのお年玉を全て合計すると、約64万円となります。
そのうち半分だけを貯金に回しても、約32万円のまとまった金額を確保できます。
また、子どもと一緒にお年玉の使い道を考えることは、良い金銭教育にもつながります。
お金を使いすぎるのではなく、節約し、計画的に貯金する大切さを実感する良い機会になるでしょう。
(3)児童手当を貯める
自治体から支給される児童手当は、子どもの教育資金を貯める強力な味方となります。
児童手当制度により、子どもが生まれてから中学校卒業までに支給される金額は、以下の通りです。
- ✅3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,0000円)
- ✅3歳~高校生年代まで:月額10,000万円(第3子以降は30,0000円)
児童手当を全額貯金すれば、中学校卒業時には約200万円の貯蓄が可能です。
18歳までに備えておく目標金額が400万円の方であれば、児童手当だけでその半分をまかなえる計算となります。
児童手当は、2024年10月から制度改正により所得制限が撤廃され、支給期間が高校生まで延長されました。
また、第3子以降の支給額が3万円に増額されるなど、より多くの家庭が恩恵を受けられる内容となっています。
例えば、配偶者と子ども2人を扶養する世帯主の場合、以前は年収が960万円以上のケースなどは受給に制限がありましたが、現在は所得制限が撤廃されたため、高所得世帯も対象となります。
なお、詳細は自治体に確認が必要です。
(4)財形貯蓄や社内預金などの制度を活用する
勤務先に財形貯蓄や社内預金の制度がある場合は、積極的に活用しましょう。
財形貯蓄のメリット
財形貯蓄は、給与から天引きで積み立てができるため、計画的に貯金がしやすい制度です。
特に「一般財形貯蓄」の場合、貯めたお金の使い道に制限がなく、自由なタイミングで引き出すことが可能です。
そのため、急な出費にも柔軟に対応できます。
社内預金の魅力
社内預金とは、会社が従業員の給与の一部を天引きし、貯蓄を代行する制度です。
この制度では、厚生労働省令により最低利率が0.5%と定められており、銀行の定期預金よりも高い利率で貯蓄できるのが大きなメリットです。
また、預けたお金はいつでも出し入れが可能ですが、預け入れの上限額が設定されている場合もあります。
ただし、社内預金制度を導入する企業は減少傾向にあるため、勤務先にこの制度がある場合は、優先して活用することをおすすめします。
財形貯蓄の詳細について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
(5)学資保険で積み立てる
子どもの教育費を貯める方法として人気が高いのが、学資保険です。
学資保険は、支払った保険料を積み立てる仕組みで、子どもが18歳になる満期時に利息を加えた満期保険金を受け取ることができます。
学資保険の特徴とメリット
学資保険の特徴は、生命保険の役割も兼ね備えている点です。
契約者である両親に万が一のことがあった場合、保険料の払込が免除される「保険料払込免除」が適用され、満期時には満額の保険金を受け取ることが可能です。
さらに、学資保険は元本保証があり、銀行の定期預金と比べて利回りが高い商品が多いため、安全かつ効率的な資産形成が期待できます。
学資保険のデメリットと注意点
一方で、途中解約をすると大きく元本割れしてしまう点がデメリットです。
そのため、無理のない範囲で支払いを続けられる保険料を設定することが重要です。
計画的に保険料を支払い、確実に積み立てていきましょう。
(6)新NISAを活用する
近年の投資ブームの中で注目を集めている新NISAは、投資信託や株式などの投資によって得られる利益が非課税となる制度です。
長期的な資産運用を目的に、子育て世代でも利用者が増加しています。
子どもの将来のための資金を効率的に築く方法として、新NISAは非常におすすめです。
新NISAのメリット
新NISAを活用して資産運用を行えば、預貯金よりもスピーディーに資産を増やせる可能性があります。
特に、長期運用が資産形成の成功のカギとなります。
最低でも10~15年以上の投資期間を見据え、子どもが資金を必要とするタイミングから逆算して運用を始めると良いでしょう。
市場の値動きを示す指数に連動する「インデックス型投資信託」は、コストが低く分散投資がしやすい点が魅力です。
また、毎月の積立投資を設定すれば、自動的かつ比較的安全に資産を増やせます。
新NISAの注意点とリスク
ただし、投資には元本割れのリスクがあります。
市場の状況や現金化するタイミングによっては、損失が生じる可能性もあります。
そのため、教育資金の全額を投資に回すのではなく、一部を新NISAで運用するのが安心です。
NISAについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
また、私が講師を務める「新NISA制度丸わかりセミナー」の動画をLINE友達限定にて公開しています。
- ✅つみたてNISAの落とし穴
- ✅新NISAの注意点
- ✅実際に私が実践している投資商品
- ✅成功するための鉄則
などリアルな情報がたくさんです。つみたてNISAで損をしている方、これからNISAを検討している方は、ぜひご覧ください。
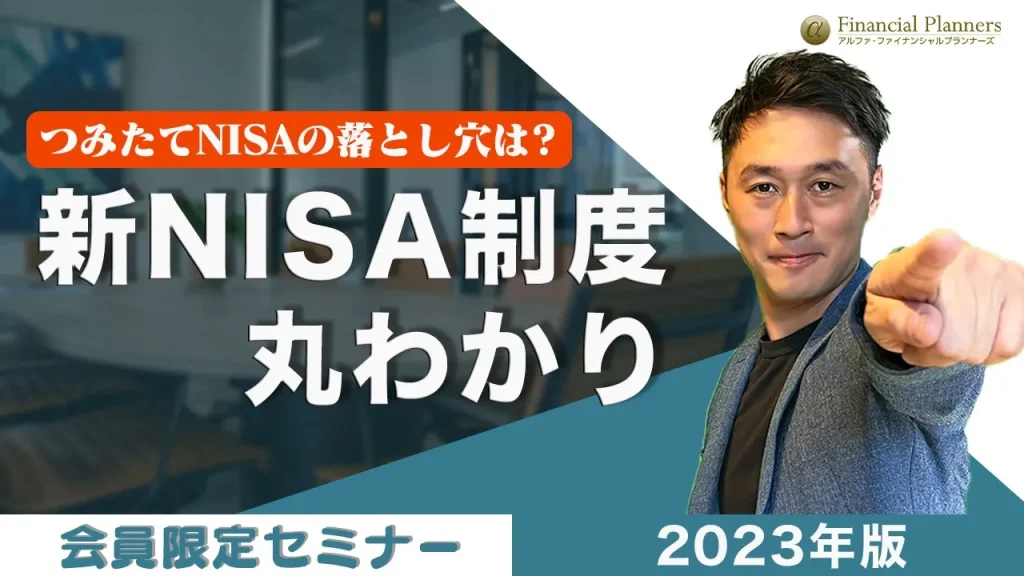
一方で、NISAと同じく目にする機会の多いiDeCoは、自分の年金を積み立てるための制度であり、60歳まで引き出しができません。
iDeCoは教育費の貯蓄としてではなく、両親の老後資金への備えとして活用したい制度です。
iDeCoについて詳しく知りたい方は、下記記事を参照にしてみてください。
なお、iDeCoはなんでおすすめなのか、下記動画でも解説しています。ぜひ合わせてチェックしてみてください。
なお、どの方法がいいかわからない方は、ぜひ一度我々FPに相談してみてください。
子どもの通帳で教育費を貯める
子ども名義で銀行口座を開設すると、子どものために貯めたお金を明確に管理できるというメリットがあります。
また、「20歳の記念に通帳をプレゼントしたい」と考え、コツコツと預貯金をする親御さんも少なくありません。
ただし、大きな金額を子どもの名義で預ける場合、贈与税が発生する可能性がある点には注意が必要です。
事前に税制の仕組みを確認し、必要に応じて専門家に相談すると安心です。
(1)子ども名義の通帳で教育費を貯金する
子ども名義の通帳で教育費を貯金することで、生活費や家庭の貯蓄と明確に区別できます。
「子どものためだけに貯めたお金」を実感しやすくなるため、貯金への意欲が高まるでしょう。
お子さんに物心がついてきたら、貯金額を共有するのもおすすめです。
両親が貯金を実践する姿を見せることで、お子さん自身が自然とお金や節約の大切さを学ぶ良い機会となります。
一方で、お子さんが成長して通帳を管理できるようになると、親が自由にお金を引き出しにくくなる点はデメリットといえます。
この点を考慮しながら計画的に利用することが大切です。
(2)子どもの貯金で贈与税がかかる?
子ども名義の口座に親が貯金をしている場合、「贈与」とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。
たとえば、親が子ども名義の通帳にコツコツと貯金し、それを成人後に手渡す際、贈与税が発生してしまうケースがあるため注意が必要です。
贈与税が非課税となる範囲
子どもへの贈与額が1年間に110万円以内であれば、非課税枠の範囲内となり、贈与税は発生しません。
そのため、子どもへ渡す口座の預貯金額を110万円以内に抑えることで、贈与税の心配を防ぐことができます。
贈与額が110万円を超える場合の対応
110万円を超える金額を渡したい場合は、年間の入金額を110万円以下に抑え、その都度贈与契約書を作成しておくと安心です。贈与契約書があれば、贈与の事実を証明できます。
教育資金の非課税贈与制度
また、親や祖父母が子どもにまとまった資金を一括で贈与する場合、教育資金として最大1,500万円まで非課税となる制度を活用することも可能です。
大切なプレゼントに余計な税金がかからないよう、事前に制度を確認し、適切に手続きを進めましょう。
貯金以外で教育費を用意する方法

近年の低金利の影響で、銀行に貯金をしているだけではお金を増やすことは難しくなっています。
そこで、教育費を準備する方法として、効率的にお金を増やす投資、教育ローン、および奨学金制度をご紹介します。
(1)投資信託でお金を増やす
当面使う予定のないお金は、投資信託などの金融商品で運用することを検討してみましょう。
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を専門家が運用する仕組みです。
専門家が株や債券を選び、その運用による利益が投資家に分配されます。
自分で投資先を判断する必要がないため、投資初心者でも失敗のリスクを抑えやすいのが特徴です。
また、一般的な株式投資では数十万円から数百万円の資金が必要ですが、投資信託は数千円程度から始められるため、少額からでも手軽に投資をスタートできます。
投資信託の仕組みや詳細について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
なお、下記動画では投資信託で絶対に買ってはいけない商品について解説していますので、損をしたくない方はぜひご覧ください。
(2)教育ローンを利用する
貯金だけでは教育費が足りない場合、教育ローンの利用を検討するのも一つの方法です。
教育ローンは金融機関が提供する制度で、子どもの教育費をまかなうための借入れが可能です。
類似の制度として国の奨学金制度がありますが、奨学金は世帯年収が一定以下であることが条件で、返済義務は子どもにあります。
一方、教育ローンは利用条件に制限が少なく、返済義務が保護者にあるため、子どもに負担をかけずに済むのが特徴です。
ただし、教育ローンには以下の点に注意が必要です。
・審査基準:一定以上の収入がないと審査に通らない場合があります。
・金利:奨学金に比べて金利が高めです。
これらの違いを理解した上で、自身の状況に適した方法を選びましょう。
教育ローンの詳細については、日本政策金融公庫「教育一般貸付」や日本学生支援機構「貸与奨学金」を確認してみてください。
(3)奨学金制度を利用する
奨学金制度の中で最も利用者が多いのは、大学進学時に利用される日本学生支援機構(JASSO)の奨学金です。
2017年度からは、返済義務のない「給付型奨学金」が開始され、成績や経済状況などの条件を満たして審査を通過すれば、給付金として受給できます。
返済が必要な「貸与型奨学金」には以下の2種類があります。
・第一種奨学金(無利子):受給条件が厳しいが、利息がかからない。
・第二種奨学金(有利子):条件が比較的緩やかで利用しやすい。
労働者福祉中央協議会が2022年に実施した「奨学金や教育費負担に関するアンケート」によると、奨学金を返還中の人の平均借入総額は310万円でした。
また、日本学生支援機構の「令和 4 年度 学生生活調査結果」では、4年制大学昼間部の学生の55.0%が奨学金を利用していることが明らかになっています。
大学生の半数i以上が奨学金を活用し、学費の負担を軽減しているのが現状です。
お子さまの進路希望を実現するため、教育費が不足する場合は、お子さまと相談しながら奨学金制度の活用を検討してみましょう。
教育費について利用できる国の制度

利用できる世帯は限られていますが、子育て世代向けに国が用意する支援策もあります。
ご自身が対象となるか確認して、申請が必要であれば準備していきましょう。
(1)幼児教育・保育の無償化
幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無償化されています。
保護者の収入に関する条件などは特段ありません。
幼稚園については月額上限2.57万円であり、超えた部分は自己負担となります。
一方、0歳から2歳の子どもは、住民税非課税世帯のみ利用料が無償化されています。
(2)高校無償化
高校無償化には「高等学校等就学支援金」と「高等学校等奨学給付金」の2つの制度があります。
いずれの支援金も返済は不要です。
高等学校等就学支援金は授業料支援を目的としており、年収約910万円未満の世帯が対象です。
国公立高校の場合は約12万円、私立高校の場合は約40万円の支援金が受け取れます。
高等学校等奨学給付金は、教科書代など授業料以外の教育費支援を目的としており、生活保護世帯や年収約270万円未満の世帯が対象です。約3~15万円が給付されます。
(3)大学無償化
大学無償化制度は正式には「高等教育の修学支援新制度」と言います。
制度の内容としては「授業料等減免」と「給付型奨学金」の2つです。
授業料等減免では、収入状況によって授業料や入学金が免除・減額されます。
収入条件以外にも、高校2年までの学業成績や大学入学以降の成績が一定以上であるなど、要件があります。
昼間制で住民税非課税世帯の学生が受けられる支援金上限額は以下の通りです。
| 入学金(国公立) | 授業料(国公立) | 入学金(私立) | 授業料(私立) | |
| 大学 | 約28万円 | 約54万円 | 約26万円 | 約70万円 |
| 短期大学 | 約17万円 | 約39万円 | 約25万円 | 約62万円 |
| 高等専門学校 | 約8万円 | 約23万円 | 約13万円 | 約70万円 |
| 専門学校 | 約7万円 | 約17万円 | 約16万円 | 約59万円 |
出典:文部科学省「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度」を参考に著者作成
給付型奨学金では、学生生活を送るための生活費が毎月支給されます。
住民税非課税世帯の学生の支給額は以下の通りです。
| 自宅生(国公立) | 自宅外(国公立) | 自宅生(私立) | 自宅外(私立) | |
| 大学 短期大学 専門学校 | 29,200円(33,300円) | 66,700円 | 38,300円(42,500円) | 75,800円 |
| 高等専門学校 | 17,500円(25,800円) | 34,200円 | 26,700円(35,000円) | 43,300円 |
出典:文部科学省「学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度」を参考に著者作成
※生活保護世帯で自宅から通学する方、および児童養護施設等から通学する方には、カッコ内の金額が支給されます。
いずれの制度も、非課税世帯に準ずる世帯の支給額は、上限額の 2/3 または 1/3 となります。
どのくらいの支援が受けられるかは、日本学生支援機構の公式サイトで進学資金のシミュレーションが可能です。
受けられる支援を逃さないよう、事前に準備しておきましょう。
また、令和6年度(2024年度)から、現行の「高等教育の修学支援新制度」が拡充されます。
主な変更点は、対象世帯の拡大です。世帯年収約600万円(目安)までの多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)や、私立大学の理工農系学部・学科に通う学生等が新たに支援の対象となります。
この拡充により、これまで支援の対象外だった中間所得層の多子世帯や、特定の学部・学科に在籍する学生への支援が強化され、経済的負担の軽減が期待されています。
さらに、令和7年度(2025年度)からは、多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)の学生に対して、所得制限なく大学等の授業料・入学金が国の定める一定額まで無償化される予定です。
対象世帯: 扶養する子供が3人以上いる世帯。
所得制限: 所得制限はなく、すべての多子世帯が対象となります。
支援内容: 大学等の授業料・入学金が、国が定める上限額まで無償化されます。例えば、私立大学の4年制の場合、年間授業料70万円、入学金26万円が上限となります。
適用条件: 3人以上の子供を同時に扶養している期間中に、大学等に在学している学生が対象です。例えば、長子が就職して扶養から外れた場合、残りの子供が2人になるため、無償化の対象外となります。
対象機関: 一定の要件を満たした大学、短期大学、高等専門学校(4・5年次)、専門学校が対象です。対象外の学校に入学した場合、支援を受けることはできません。
申請手続き: 自動的に適用されるわけではなく、所定の期間内に申請が必要です。詳細な申請方法や手続きについては、文部科学省や各大学の公式サイトで確認してください。
この制度により、多子世帯の経済的負担が軽減され、子供たちの高等教育への進学が促進されることが期待されています。
まとめ

子どものための貯金は、家計の状況によって必要金額が異なります。
一般的な教育費の目安は以下の通りです。
- ✅幼稚園から大学まで公立に通学した場合:約850万円
- ✅幼稚園から高校まで私立、大学は私立文系に通学した場合:約2,400万円
高額な教育資金を用意する方法は、貯金だけでなく、投資や教育ローン、国の支援策なども活用できます。
現在の家計や資産状況を踏まえ、教育資金としてどれくらいの金額を準備すればよいのかわからない方は、FP(ファイナンシャルプランナー)への相談がおすすめです。
お金のプロであるFPは、効率的な資産形成方法やライフプランの設計など、さまざまなお金の悩みに具体的なアドバイスを提供します。
金銭的な理由で子どもの選択肢や将来の可能性を狭めないためにも、貯金目標額を明確にし、早めに準備を始めましょう。
著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆
アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。























