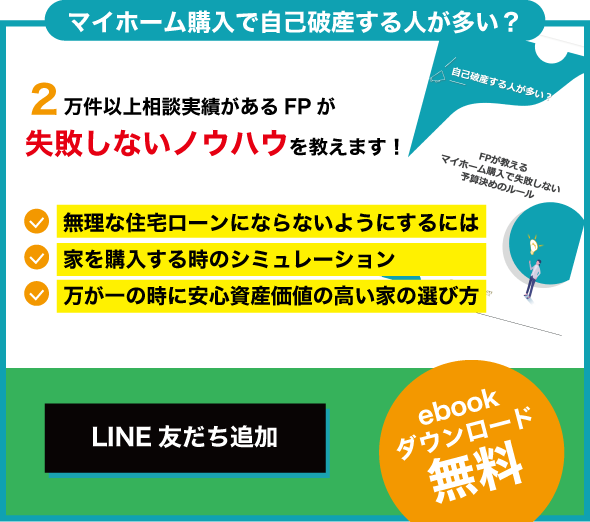不動産購入する時にかかる4つの税金!FPが節税するコツも合わせて解説

あこがれのマイホーム。ですが、住まいの購入には購入代金以外にも多額の費用がかかります。
その中でも忘れてはならないのが税金。
今回は不動産を購入する際にかかる4つの税金について解説します。
払わなければならないけれど、できるだけ減らしたいのが税金というもの。
その仕組みも難解です。FPが節税するコツも一緒に説明します。
不動産購入する時にかかる4つの税金

不動産購入時にかかる税金は以下の4つです。
- 契約書などに必要な「印紙税」
- 不動産購入にかかる「消費税」
- 不動産の登記をする時にかかる「登録免許税」
- 不動産取得税
では、それぞれについて見ていきましょう。
契約書などに必要な「印紙税」
契約書などに収入印紙を貼付することによって納付するのが印紙税です。
契約書や領収書に切手のような紙が貼ってあって、多くの場合印鑑で消印されています。あれが収入印紙です。
収入印紙を購入し、契約書などに貼付して納税します。
(1)契約書に記載されている金額によって印紙税が変わる
印紙税は契約書や領収書の記載金額に応じて税額が決まっています。
契約金額が少ない取引は印紙税額も安く、高額な取引はそれに連れて高額となる累進課税です。
(2)印紙税には「軽減措置」がある
不動産の売買契約書の場合は、令和6年3月末までは軽減税率が適用されるので注意が必要です。
印紙税の本則課税と軽減税率は以下のようになります。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円超50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円超100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円超500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円超1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円超5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円超1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円超のもの | 60万円 | 48万円 |
不動産購入にかかる「消費税」

一番身近な税金といえる消費税もかかります。
不動産を買う場合の消費税は少々複雑です。
建物は消費税の対象ですが、宅地にはかかりません。
また、売主が誰かによって消費税がかかるケースとかからないケースがあります。
不動産購入にかかる消費税についてチェックしていきましょう。
(1)消費税がかかるケースとかからないケース
ただ、消費税は売主の属性によってかかる場合とそうでない場合があるのです。
売主が課税事業者であれば消費税がかかるものの、売主が非課税事業者や不動産を業としていない個人だとかかりません。
また、土地は非課税です。
なお、物件自体に消費税がかからないケースがあっても、仲介手数料などの諸費用は課税対象となります。
不動産の登記をする時にかかる「登録免許税」
登録免許税は所有権移転登記や抵当権設定登記の際に納税する税金です。
不動産を購入した人で登録免許税を納税した覚えのある人は多くないでしょう。
登録免許税は多くの場合、司法書士が行なう登記手続きの報酬に含まれているものです。
納税者が直接納める税金ではありません。
(1)登録免許税の計算方法
登録免許税はほとんど司法書士が計算してくれます。
基本的な計算式は以下のとおりです。
- ✅登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
課税標準は申請する登記の種類によって異なります。
主に①不動産の価額、②債券金額、③不動産の個数、などです。
税率も登記の種類によって異なるほか、政策的に軽減措置が採用されることもあります。
(2)登記には4つの種類がある
登記には多くの種類があり、主なものは以下のとおりです。
このほか、抵当権などの抹消登記、配偶者居住権の設定登記などがあります。
- ①売買を原因とする所有権の移転登記
- ②相続,贈与,財産分与などを原因とする所有権の移転登記
- ③所有権の保存登記
- ④抵当権または根抵当権の設定登記
それぞれの登録免許税の課税標準と税率は以下のとおりです。
| 課税標準 | 本則税率 | 軽減税率の有無 | |
| 売買 | 固定資産課税台帳の価格など | 1,000分の20 | あり |
| 相続、贈与、財産分与 | 固定資産課税台帳の価格など | 1,000分の4 | 相続であり |
| 保存登記 | 固定資産課税台帳の価格 登記所が認定した価額 | 1,000分の4 | あり |
| 抵当権等設定 | 債権金額(根抵当権の場合にあっては,極度額) | 1,000分の4 | あり |
(3)不動産の種類によって軽減措置が変わる
登録免許税には多くの特例や軽減措置があります。
主な理由は不動産の取引の活性化です。不動産取引には納税がついてまわります。
その負担をなるべく小さくしようと一定の要件に該当すれば軽減措置が受けられるようになりました。
各種の特例措置の詳細をご紹介します。
なお、税率については国税庁の資料によりました。
①新築不動産の保存登記の特例
個人が住宅用家屋を令和6年3月31日までの間に新築した場合の保存登記は、税率が1,000分の1.5に軽減されます。
②中古不動産の移転登記の特例
個人が中古住宅のような居住用家屋の売買または競落した場合で、自分で住む場合には税率が1,000分の3に軽減されます。
③土地の移転登記の特例
令和8年3月31日までに土地の所有権移転登記をした場合には、1,000分の15まで税率が軽減されます。
④抵当権の設定登記の特例
個人が、令和6年3月31日までの間に自宅の新築や増築をした場合には、1,000分の1まで税率が軽減されます。
不動産取得税

不動産取得税はその名の通り、不動産を取得した時にかかる税金。
ただ、課税されるタイミングは不動産を購入した時点ではなく、購入後しばらく経過した後になります。
これは不動産登記の情報が法務局から都道府県にもたらされるまでタイムラグがあるからです。
その後都道府県から所有者に課税がなされるため、課税のタイミングが数カ月から1年ほど遅くなります。
新築住宅の場合はしばらくすると担当者が建物の調査に訪れ、その後課税されます。
(1)不動産取得税の計算方法
不動産取得税の税額計算は以下のように算出します。
- ✅不動産取得税額 = (課税標準)×(税率)
ここでの課税標準は固定資産税評価額が基礎になります。
物件価格や不動産売却価格ではないことが注意点です。
固定資産税評価額は市町村が発行する納税通知や評価証明書でも確認できます。
(2)不動産取得税の軽減措置
まず税率について標準税率は4%ですが、軽減措置の延長が繰り返されており、ながく3%です。
建物の場合は課税標準を計算する際、固定資産税評価額から建物の建築からの年数に応じた控除額が引かれます。
新築の場合は1,200万円、長期優良住宅の場合は1,300万円です。
住宅用地は課税標準額が2分の1に減額される特例があります。
さらに以下のいずれか多い額が控除されるのです。
- ①4万5千円
- ②土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率
不動産購入で非課税、税金の還付を受けるには?

不動産を購入する際にはなるべく税金は安く抑えたいところです。
税金は政策的な観点から非課税になる、あるいは税金の還付を受けられることがあります。
不動産購入を促進させるには、国が増えてほしいと考える優良な住宅や親世代からの資産の移転には優遇措置がつくのです。
非課税、税金の還付を受ける方法や条件について確認してみましょう。
(1)認定長期優良住宅を選ぶ
認定長期優良住宅とは耐震性に優れ、断熱性や環境への配慮もなされた住宅のことです。
この長期優良住宅に認定されるとさまざまな税務上の特典を得られます。
具体的には、2024年3月31日までに入居すると以下のような減税があります。
- ①建物保存登記の際の登録免許税が1,000分の15から1,000分の10へ
- ②建物移転登記 1,000分の3から一戸建て1,000分の2 マンション1,000分の1へ
(2)住宅ローン減税を利用する
住宅ローン減税は住宅ローン控除とも呼ばれ、自宅を購入する人によく利用される手段です。
適用要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の0.7%の税金が13年間にわたって所得税や住民税が還付されます。
一般の住宅だと年間で毎年21万円、13年で最大273万円です。
認定長期優良住宅だとそれぞれ35万円、455万円となります。
住宅ローン減税を受けるためには入居初年度は確定申告が必要です。
会社員の場合、2年目以降は年末調整ができるため確定申告は不要になります。
(3)住宅購入に関する贈与税の非課税制度を利用する
贈与税には住宅取得等資金の贈与税の非課税措置があります。
これは親や祖父母といった直系尊属から住宅用資金の贈与を受けたとしても、最大1,000万円までは贈与税がかからない制度です。
この制度を利用すると親世代からの資金援助がスムーズに行えます。
税金について詳しく知りたい方はFPに相談する

税金について詳しく知りたい場合はFPに相談してみましょう。
税金はとても複雑にできています。
住宅ローン減税を受けるための確定申告書の書き方や提出すべき必要書類も難解です。
国税庁のサイトなどをみて理解したつもりでも、実は実際とは違っていた、なんてこともあります。
FPは財務のプロフェッショナルです。税金にもきちんと勉強しています。
専門的なことは専門家への質問を検討してみましょう。
まとめ

今回は4つの税金を中心にお話ししました。
税金は納税しなければならないものですが、やり方次第で節税も可能です。
もし節税できればそのお金を住宅の購入費用にまわしてもよいでしょう。
住宅購入を促進させるために多くの特別控除や特例も用意されています。
税金の基礎知識を押さえ、ときにはFPにも相談して、不動産を購入しましょう。
著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆
アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。
最新の投稿
 税金2024年2月27日不動産を相続したら相続税はいくら?手続き、計算方法や活用方法を解説
税金2024年2月27日不動産を相続したら相続税はいくら?手続き、計算方法や活用方法を解説 不動産投資2024年2月24日不動産所得がある場合は確定申告が必要!計算方法や申請手順を解説
不動産投資2024年2月24日不動産所得がある場合は確定申告が必要!計算方法や申請手順を解説 税金2024年2月23日不動産の生前贈与はした方がいい?メリット、手続きや注意点を解説
税金2024年2月23日不動産の生前贈与はした方がいい?メリット、手続きや注意点を解説 不動産投資2024年2月21日不動産投資クラウドファンディングとは?おすすめ商品も合わせて紹介
不動産投資2024年2月21日不動産投資クラウドファンディングとは?おすすめ商品も合わせて紹介