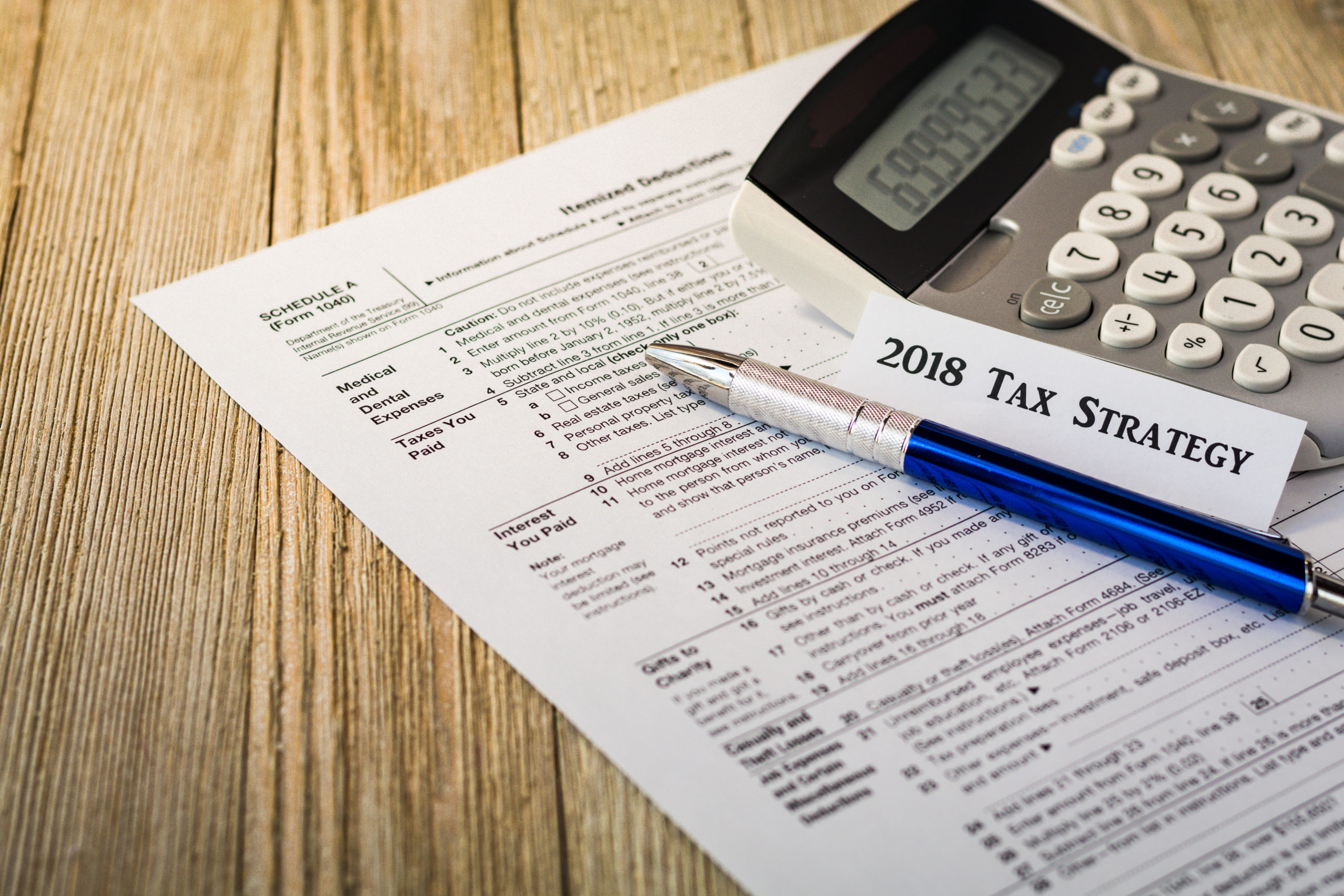300万円で資産運用にオススメ投資商品8選|成功するコツも合せて解説

お金を貯めることは言うほど簡単ではありませんが、ある程度のまとまった金額になるとさまざまな投資に活用できるようになります。
そこで今回は、20代でなんとか到達できるかどうかといわれる300万円の貯蓄で始められる、オススメの投資商品9選と成功のためのコツを解説します。
貯金300万円以上ある割合は?

社会人として働き始め、毎月積立をしている人もいれば、娯楽や趣味などにお金を使い、全く貯金をしていない人もいるでしょう。では、貯金が300万円以上ある人の割合はどれくらいなのでしょうか。
まずは、世帯の貯蓄状況について、厚生労働省の令和5年「家計の金融行動に関する 世論調査(総世帯)」を参考にしてみましょう。
| 29歳以下 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | |
| 金融資産を保有していない | 42.2% | 30.2% | 30.0% | 30.3% | 24.6% | 21.6% |
| 1~99万円 | 22.6% | 13.1% | 10.0% | 9.6% | 6.6% | 5.7% |
| 100~299万円 | 16.7% | 16.1% | 12.8% | 9.6% | 8.5% | 9.1% |
| 300~499万円 | 8.0% | 10.1% | 8.7% | 7.6% | 5.4% | 6.8% |
| 500~699万円 | 4.0% | 6.3% | 6.8% | 5.3% | 6.2% | 6.3% |
| 700~999万円 | 2.2% | 4.6% | 6.1% | 5.5% | 5.5% | 5.6% |
| 1,000~2,999万円 | 2.1% | 11.6% | 15.4% | 17.1% | 21.0% | 23.5% |
| 3,000万円以上 | 0.1% | 4.0% | 6.0% | 10.7% | 19.0% | 18.9% |
これを整理すると、各世代ごとに貯蓄が300万円以上ある人の割合は以下の通りです。
| 29歳以下 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | |
| 貯蓄300万円以上 | 16.4% | 36.6% | 43.0% | 46.2% | 57.1% | 61.1% |
こうしてみると300万円の貯蓄を達成することは簡単なことではないとわかります。
しかし、貯蓄額が多いほど投資に回せる資金を確保でき、さらに資産を増やす可能性が高まります。
また、年齢にもよりますが、仕事を退職した後の生活資金を考えると、貯蓄や金融資産は多ければ多いほど安心です。
したがって、300万円は一つの通過目標と言えるでしょう。
300万円で資産運用する時にオススメの投資商品9選
300万円の資産運用は、リスク許容度や投資の目的によって選択肢が異なりますが、しっかりと分散投資を行うことで、安全性を高めながら資産を増やす可能性があります。
以下では、300万円で取り組むのに適した9種類の投資商品とそのメリットを紹介します。
(1)専門家が運用してくれる「投資信託」
「投資信託」とは、投資家が拠出した資金を運用の専門家が国内外の株式や債券などに投資・運用し、その成果を投資家に分配する商品です。
①メリット
投資信託は、株式、債券、不動産など、さまざまな資産に分散投資する仕組みを持っています。
これにより、特定の資産や市場の変動リスクを抑えることができます。
一点集中型の投資に比べ、計画的で安定した運用が期待できます商品の特徴は目論見書で確認できるため、投資初心者にも分かりやすく、長期的な運用では複利効果による収益が期待できる商品もあります。
②オススメしたいポイント
投資信託は、資産形成を始めるうえで適した投資商品であり、銀行や証券会社などの金融機関で広く取り扱われています。
投資判断はプロが行うため、株価のチャートを頻繁に確認する必要はありません。
若くて長期投資が可能な場合は、多少リスクがあっても高いリターンを期待できるファンドが、そうでない場合はリスクの低い商品が適しています。
具体例として、現在人気の投資信託の1つに、米国株式の指数であるS&P500を追随するファンドがあります。
このファンドは、2008年のリーマンショックや2022年のインフレショックで一時的な下落を経験しましたが、長期的に見ると2004年から2024年の20年間で4.6倍に成長しています。
なお、すべての投資信託が新NISAで購入可能というわけではありませんが、対象商品であれば投資で得た利益が非課税になるため、大きなメリットがあります。
投資信託について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
なお、投資信託で絶対に買ってはいけない商品を下記動画にて解説していますので、ぜひご覧ください。
(2)1万円からスタートできる「不動産クラウドファンディング」
「不動産クラウドファンディング」は、多くの投資家が出資した資金をもとに、不動産運用会社が不動産を投資・運用し、そこから得られる家賃収入(インカムゲイン)や売却益(キャピタルゲイン)で利益や元本を投資家に償還する仕組みです。
簡単にいえば、「不動産への共同投資」を可能にするサービスです。
①メリット
小額から始められる点が「不動産クラウドファンディング」の特徴で、ほとんどの場合、最低出資額は1万円程度です。
通常の不動産投資と異なり、管理や運営の手間が不要で、運用会社に全てを任せられるのも大きなメリットです。
また、投資家保護のために優先劣後システムが採用されており、元本割れのリスクが抑えられています。
②オススメしたいポイント
不動産クラウドファンディングは、不動産投資の中では低リスクな選択肢ですが、リターンはそれほど高くなく、途中解約ができない長期投資となる点に注意が必要です。
この特徴を踏まえると、安定した利回りを期待する商品として適しているものの、大きな資金を割り当てるのは控えたほうが良いでしょう。
(3)インフレに強い「金(ゴールド)投資」
古代から現代に至るまで、金ほど普遍的な価値を持ち続けている資産はありません。そんな金に投資する方法が「金(ゴールド)投資」です。
金貨や金地金などの現物を購入する方法や、毎月一定額または一定量の金を購入する積立投資など、投資方法が多様である点も特徴です。
①メリット
国が発行する通貨や債券、企業の株式は、発行元の国や企業が破綻した場合、価値が失われるリスクがあります。
しかし、金は世界中でその価値が認められているため、価値がゼロになる心配がありません。
また、金投資は大きなリターンを期待するものではありませんが、投資価値が失われるリスクがほとんどない点が大きなメリットです。
②オススメしたいポイント
金の価値は、世界の物価変動に連動しており、インフレに強い投資資産とされています。
特に日本を含む先進国ではインフレ傾向が強まっているため、貨幣価値の目減りへの備えとして金への投資は有効です。
また、毎月任意の金額を設定して積立投資を行うこともできるため、長期的にコツコツと資産を増やしたい方にも適しています。
金(ゴールド)投資について詳しく知りたい方は、下記の記事をご参照ください。
(4)リスクの少ない「国債」
国債とは、国が発行する債券のことです。
個人向け国債は、個人が購入しやすいように設計された国債で、「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3つのタイプから選べます。
①メリット
国債は、国が資金を調達するために発行する債券であり、元本と利子の支払いは日本国政府が責任をもって行うため、信用度の高い金融商品とされています。
ただし、利回りは市場環境によって変動するため、必ずしも銀行預金より高いとは限りません。
また、通常の国債は中途解約が難しく、価格が変動するため、元本割れのリスクが伴う場合もあります。
一方で、個人向け国債は元本保証があり、発行から1年を経過すれば途中換金が可能である点が大きなメリットです。
②オススメしたいポイント
個人向け国債は、毎月募集されており、1万円から1万円単位で購入可能です。
金利は最低でも年0.05%が保証されており、安全性を重視する投資家に適した商品です。
ただし、発行から1年間は換金できませんが、1年を過ぎると1万円単位で中途換金が可能になります。
中途換金の際には、直近2回分の利子相当額が差し引かれる点に注意が必要です(差し引かれる金額は、各利子の税引前金額に0.79685を乗じた額となります)。
(5)節税効果がある「新NISA」
従来の一般NISAとつみたてNISAが一本化され、2024年から「新NISA」としてスタートしました。
この制度では、非課税保有限度額が1,800万円に引き上げられ、保有期間が無期限となるなど、大幅に拡充されています。
新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠の2つの枠組みが設けられ、それぞれの投資スタイルに合わせた運用が可能です。
①メリット
新NISAのつみたて投資枠の最大のメリットは、運用益や分配金が非課税になる点です。
通常の投資では、運用益や分配金に対して20.315%の税金がかかりますが、つみたて投資枠を活用することで、この税金が免除されます。
また、この投資枠では投資信託を中心とした商品が対象となっており、長期運用に適しているため、比較的リスクが低い運用方法として魅力的です。
②オススメしたいポイント
新NISAは、投資の運用益が一定額まで非課税になるため、節税効果を期待できる投資商品です。
非課税の仕組みは資産形成を後押しする重要な手段であり、その特性を活かすことで運用効率をさらに高めることが可能です。
ただし、非課税であることだけを理由に投資判断を行うのではなく、投資対象のリスクとリターンを十分に検討することが重要です。
2024年以降、年間投資枠や非課税保有限度額が大幅に拡大され、非課税期間も無期限化されました。
これにより、特に長期投資を行う方にとって非常に有利な制度となっています。
投資期間が長ければ長いほど、非課税の恩恵をより大きく享受できるでしょう。
| 2023年まで | 2024年以降 | |
| 年間投資枠 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税保有期間 | 最長20年間 | 無期限化 |
| 非課税保有限度額 | 800万円 | 1,200万円 |
私が講師を務める「新NISA制度丸わかりセミナー」の動画をLINE友達限定にて公開しています。
- つみたて投資枠の落とし穴
- 新NISAの注意点
- 実際に私が実践している投資商品
- 成功するための鉄則
などリアルな情報がたくさんです。つみたてNISAで損をしている方、これからNISAを検討している方は、ぜひご覧ください。
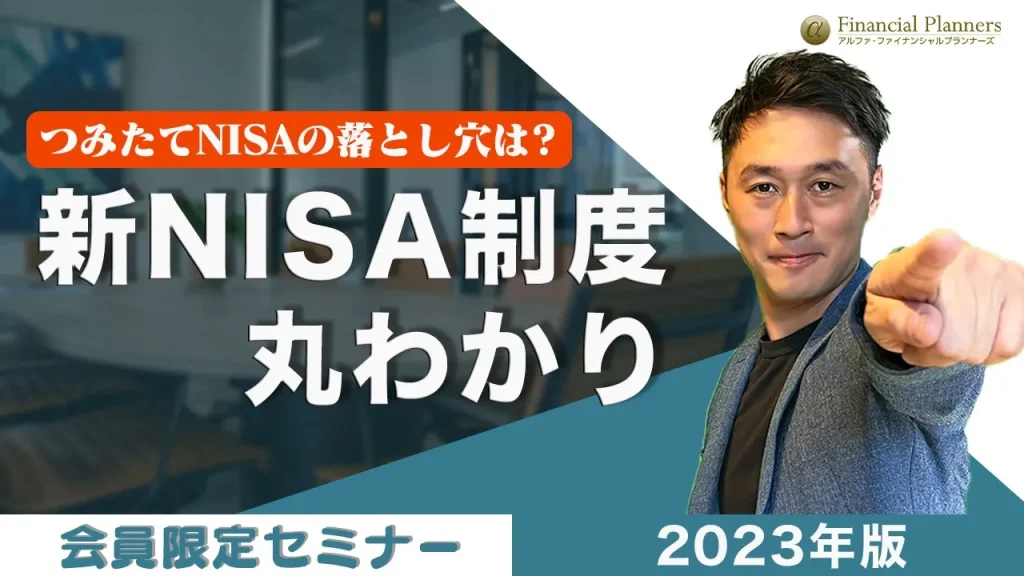
(6)高配当企業の「株式投資」
「株式投資」といえば投資の王道ですが、その投資スタイルはさまざまです。
短期的な売買で売却益を狙う方法や、配当金や株主優待を目的として株式を長期保有する方法があります。
その中でも、高配当企業の株式に投資することで高利回りを狙う長期保有は、基本的で堅実な株式投資といえるでしょう。
①メリット
高配当企業の株式を長期保有する主なメリットは、毎年支払われる配当金による高利回りが期待できる点です。
また、投資先企業が成長すれば株価の上昇によるキャピタルゲインも見込めます。
さらに、長期保有の場合、短期的な株価の変動に左右されず、腰を据えて企業の成長を見守ることができるため、精神的な負担が少なくなるでしょう。
②オススメしたいポイント
高配当企業への株式投資は、忙しい日常を送る方や、資金を長期間固定できる方に特にオススメです。
成長が期待できる企業を見つけ出し、その成長を見守ることは「投資家」としての醍醐味を味わえる方法でもあります。
ただし、業績悪化や経済環境の変化、最悪の場合には企業の破綻など、リスクが伴うことも忘れてはなりません。そのため、十分なリサーチと分散投資が重要です。
(7)融資を活用できる「不動産実物投資」
不動産を購入し、それを他人に貸し出すことで家賃収入を得るのが「不動産投資」で、歴史的にも古典的な投資といえます。
現物投資となるので、建物や家賃収入の管理などが必要になり、所得税や固定資産税なども課税されるので、理論上の利回りだけでは判断できない点に留意が必要です。
①メリット
不動産購入と聞くと多額の資金が必要なイメージがありますが、200万円ほどの手持ち資金があれば融資を利用することで投資が可能です。
この融資を活用することで、元手以上の利益を狙う「レバレッジ効果」が期待できます。
さらに、不動産投資には相続税の節税効果もあるため、資産状況や年齢によっては、投資によるリターンだけでなく、相続対策としてのメリットも考慮する価値があります。
ただし、空室リスクや金利上昇リスクといった不動産特有のリスクには注意が必要です。
不動産投資のリスクや成功のポイントについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
②オススメしたいポイント
不動産投資の成功は、投資物件の選定が重要なカギを握っています。
適切な物件を選べば、家賃収入による安定したインカムゲインだけでなく、売却時のキャピタルゲインも期待できます。
また、不動産は現物資産であるため、価値が完全にゼロになる可能性は非常に低いという安心感があります。
しかし、その一方で、現物資産は流動性が低い点も特徴です。
このメリットとデメリットのバランスをよく考慮した上で投資判断を行うことが重要です。
投資を始める前には、過去の失敗事例やリスク回避策をしっかり学んでおくことが大切です。
詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
(8)為替レートを活用した「外貨預金」
外貨預金は、日本円ではなく外国の通貨で預金をする投資手法です。
これは、外貨を直接保有するのと同義であり、投資としての選択肢が広がる手段の一つです。
代表的な通貨にはドルやユーロがありますが、その他にも多くの選択肢があり、それぞれの通貨に応じたリスクや金利が異なります。
①メリット
外貨預金の主なメリットは、日本と投資先通貨の金利差による利息収入と、為替レートの変動による利益です。
日本は長期間にわたり超低金利が続いているため、諸外国との金利差が大きくなっており、高い利息収入を期待できる場合があります。
また、円安時には資産の価値が増加するため、資産防衛の手段としても利用できます。
ただし、円高に転じた場合には資産価値が減少するリスクも伴います。
②オススメしたいポイント
外貨預金は、通貨安のリスク分散の手段として有効であり、投資ポートフォリオの一部に組み入れることで、リスクとリターンのバランスを取ることが可能です。
日本国内での投資と組み合わせることで、それぞれのメリットとデメリットを相殺し、より安定した資産運用を目指すことができます。
ただし、為替手数料や預金時の金利の動向を十分に確認し、自分の資産運用の目的に合った形で活用することが重要です。
(9)複数の物件を投資できる「REIT」
「REIT(不動産投資信託)」は、不動産投資の一種ですが、一つの物件に共同出資する「不動産クラウドファンディング」と異なり、複数の物件に分散して投資できることが大きな特徴です。
①メリット
REITが複数の物件に投資できる理由は、個別の不動産への直接投資ではなく、複数の不動産を運用する不動産運用会社への出資であるためです。
この仕組みにより、個別物件への直接投資や不動産クラウドファンディングと比べ、投資の流動性が高い点が大きなメリットです。
市場で取引されるため、比較的簡単に売却して現金化することが可能です。
また、複数物件への分散投資により、単一物件に依存するリスクを軽減できる点も魅力です。
②オススメしたいポイント
REITは不動産投資の一種ですが、その性質は投資信託に近い商品です。
そのため、不動産運用会社の経営状況や実績をしっかりと見極め、破綻リスクを最小限に抑えることが重要です。
さらに、少額から投資を始められる点も魅力で、分散投資の一環として活用するのに適しています。
不動産に興味はあるが、直接物件を購入するにはハードルが高いと感じる方にとって、手軽に始められる点が特におすすめです。
300万円の資産運用をした場合のシミュレーション
資産運用の成果をイメージするには、具体的なシミュレーションが有効です。
金融庁が制作した「資産形成シミュレーター」を利用すれば、投入金額・年利・設定期間を入力するだけで、1年ごとの資産の増加額を簡単に計算することができます。
また、資産形成における積立投資を考える場合には、「つみたてシミュレーター」がおすすめです。
このシミュレーターでは、毎月の積立額・年利・積立期間を入力すると、将来の資産額を計算し、グラフで視覚的に確認することができます。
これらのツールを活用することで、具体的な数値を基にした資産運用の計画を立てることが可能となり、目標達成のための明確なビジョンを描く手助けとなるでしょう。
◇300万円を30年間、資産運用(複利)をした場合は下のような金額になります。
| 年利1% | 年利3% | 年利5% | |
| 1年目 | 303万円 | 309万円 | 315万円 |
| 3年目 | 309.9万円 | 327.82万円 | 347.29万円 |
| 5年目 | 315.3万円 | 347.78万円 | 382.88万円 |
| 10年目 | 331.39万円 | 403.17万円 | 488.67万円 |
| 20年目 | 366.06万円 | 541.83万円 | 795.99万円 |
| 30年目 | 404.35万円 | 728.18万円 | 1,296.58万円 |
出典:金融庁「資産形成シュミレーター」
資産運用で失敗しないコツ

会社員が毎月の給料をコツコツ貯め、100万円を超え、やがて300万円に達するまでには、多くの努力と時間が必要です。
そうして築き上げた大切な資産を運用する際、「損失を出してしまうのではないか」と不安を感じるのは自然なことです。
しかし、資産運用の際に基本的な注意点を押さえれば、リスクを大幅に抑えることができます。
ここでは、資産運用で失敗を防ぐための重要なポイントについて考えてみましょう。
(1)資産運用する目的を明確にする
資産運用を始める際には、まずその目的を明確にすることが重要です。
若い世代であれば、「300万円を元手に、5年後に500万円、10年後に1000万円を目指す」といった成長志向の目標が考えられます。
一方、ある程度の年齢に達している場合は、老後の生活費や年金収入の補填など、将来設計を具体的にシミュレーションし、必要な金額を基に投資計画を立てることが求められます。
目的が不明確だと、投資の進捗や成功を判断できず、適切なタイミングで調整や撤退をすることも難しくなります。
(2)資産運用にリスクがあることを理解する
資産運用にはリスクが伴います。
リスクがあるからこそリターンが生まれるものであり、失敗した場合の損失は自分が負担しなければなりません。
そのため、リスクの程度や仕組みを理解することが大切です。
また、投資のノウハウを学び、知識を深めることでリスクを軽減することができます。
十分な勉強と情報収集を怠らないようにしましょう。
(3)無理して投資しない
リスクを理解したうえで、無理な投資を避けることも重要です。
300万円を一度に投資するようなことは控え、不測の事態に備えて余剰資金で運用を行うことを心掛けましょう。
必要な費用の支払いのために借金をしてしまうような状況は避けるべきです。
投資は余裕をもった資金で行うことが、精神的な安定にもつながります。
(4)分散投資してリスクヘッジする
資産運用の基本は「分散投資」です。
投資先を広げることでリスクを分散させ、安定した成果を目指すことができます。
ここで紹介した投資商品以外にも、節税効果のあるiDeCo(イデコ)や、リスクが比較的低い国債・ETF・保険商品など、複数の選択肢を検討しましょう。
少なくとも3つ以上の異なる投資先を組み合わせることで、リスクヘッジが可能です。
また、興味のある分野だけでなく、幅広い投資情報を収集することが成功のカギです。
資産運用の仕組みなどについて詳しく知りたい方は、下記記事をご参照ください。
(5)長期での運用を考える
これまでおすすめの投資商品について、メリットやオススメポイントを説明してきましたが、どれも長期的な運用を前提とすることで資産を増やす可能性が高まるものです。
もちろん投資にはリスクが伴い、損失が発生することもあります。
しかし、損失が出たからといって焦って資産を手放すのではなく、長期的な視点で運用を続けることが重要です。
銀行預金だけでは大きく資産を増やすことは難しいですが、300万円の運用シミュレーションの結果からも分かるように、運用期間が長くなるほど資産の増加幅は大きくなります。
投資の成功には、時間を味方につけることが欠かせません。
投資初心者はFPなどの専門家に相談する
300万円から始める投資は、投資家としての第一歩となるかもしれません。
しかし、ネット上には投資に関する情報が溢れている一方で、中には信頼性の低い情報や怪しいものも含まれています。
投資初心者が最も避けるべきことは、少額の損失であっても失敗を経験し、それをきっかけに「投資を嫌いになってしまう」ことです。
少しでも不安を感じたり、迷いがある場合は、FP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、自分に合った投資計画を立て、自信を持って投資を始めることができるでしょう。
まとめ

給与の伸び悩みや実質賃金の大幅な低下が続く日本において、従来どおりの考え方では将来への不安が募るばかりです。
こうした状況の中で、生活の安定と将来の安心を確保するためには、貯蓄が300万円に達したタイミングを契機に、投資による資産運用を始めることを検討してみてはいかがでしょうか。
この記事を参考にしながら、自分に合った投資方法を見つけるとともに、FP(ファイナンシャルプランナー)など専門家の知識やアドバイスを活用することで、より充実した投資家人生の第一歩を踏み出せることを願っております。
著者

- 株式会社アルファ・ファイナンシャルプランナーズ
- AFP、宅地建物取引士、DCプランナー、証券外務員一種、二種、内部管理責任者、不動産賃貸経営管理士、住宅ローンアドバイザー、日商簿記2級
☆「幻冬舎ゴールドオンライン」にて記事連載中☆
☆「NewsPicks」にて記事連載中☆
アジア金融の中心地であるシンガポールに10年間滞在。その後、外資系銀行にてプライベートバンカー、セールスマネジャー、行員向け経済学講師を経て独立系ファイナンシャルプランナー事務所を設立。著書に『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』、『50代から考えておきたい“お金の基本”』。Bond University大学院でマーケティングと組織マネジメントを研究。経営学修士。