
|写真左から大和ライフネクスト株式会社 人事部部長 土屋氏、インシュアランスエスコート部ソリューション課 兼 パートナー課 松永氏
働き方の多様化とともに、企業における従業員の金融リテラシー向上が重要課題となっています。マンション・ビル管理運営大手の大和ライフネクスト(従業員数8,400名以上)では、従業員の資産形成を支援する各種制度について、活用率が伸び悩んでいることに課題を抱えていました。2022年4月より、同社は金融教育サービス「マネソル+(マネソルプラス)」を導入し、従業員の金融教育や資産形成に活用しています。今回は、インシュアランスエスコート部の松永氏と人事部部長の土屋氏に、導入の経緯から具体的な成果、そして今後の展望についてお話を伺いました。
人事部門・保険事業部門が手を組み、従業員の資産形成支援のためのプロジェクトを始動

ーー まず、自己紹介をお願いします
松永氏:インシュアランスエスコート部で保険代理店事業を担当しています。生損保両方を扱っていますが、主力は損害保険です。マンション居住者向けのファイナンシャルプランニングを手がけており、アルファ・ファイナンシャル社とは8年以上の取引があります。当社で管理しているマンションの入居者に向けて、協業して金融資産セミナーを開催した実績もございます。
土屋氏:人事部で部長として、主に給与や社会保険、福利厚生(確定拠出年金や財形貯蓄、持株会の管理など)の業務を統括しています。最近では、人事給与システムの開発プロジェクトも所管しています。
ーー 貴社が社内で抱えていた福利厚生に関する課題を教えてください
松永氏:従業員向けの保険や福利厚生の制度利用について、案内を出しても従業員の認識や反応が思うように得られないことが課題でした。当社は従業員の自主性を重視する社風のため、施策を定着させるまでに慎重なアプローチが必要でした。
土屋氏:確定拠出年金(DC)の運用状況にも問題点があります。37〜38%の従業員が全額を定期預金で運用している状態で、特に若手社員の運用意識が低く、入社時の初期設定のままという状況が続いていました。日々の業務もある中で、自分自身の資産形成については後回しにされてしまう傾向があり、対応策として社内セミナーも実施しましたが、参加者は限定的でした。このように両部署で同じ課題を抱えていたため、従業員の金融リテラシー向上を目指すプロジェクトを共同で進めることになりました。
金融教育の相談が結果的にマネソルプラスの導入へ
ーー マネソル+(マネソルプラス)を導入したのはいつごろですか?
松永氏:2021年に検討を始め、2022年4月に導入しました。従業員の金融リテラシー向上を社内プロジェクトとして進めるにあたり、コンテンツの提供について相談させていただきました。導入時は、従業員にどのように見せていけば効果的かといった不安もありました。しかし、動画コンテンツの活用方法やプログラムの組み方など、具体的な提案をいただき、現在も従業員の反応を見ながら、改善を重ねています。
土屋氏:実を言うと、マネソル+を導入した認識は最初、ありませんでした。従業員の金融リテラシー向上を目指す社内プロジェクトを進める中で、コンテンツ提供について、アルファ・ファイナンシャル社に相談しました。私たちの課題に合わせて的確な提案をいただき、そのサービスを一つずつ入れたものが結果として、マネソル+だったわけです。
ーー 導入にあたって予算面での課題はありましたか?
松永氏:一般的に、マネソル+を導入する場合は福利厚生の予算内でやりくりする必要があると伺っています。しかし、今回は私の所属するインシュアランスエスコート部の販促ととらえて導入いたしました。
確定拠出年金の100%定期預金運用の割合が約14%ダウン

ーー マネソル+(マネソルプラス)を導入して社内に起きた変化についてお教えください。
松永氏:大きく3つの変化を感じています。1つ目は、確定拠出年金(DC)の運用状況です。導入前は37〜38%の従業員が全額を定期預金で運用していましたが、現在は23〜24%まで減少しました。約14%の従業員が新たに資産運用を始めたことになります。2つ目は、従業員の声の変化です。社内アンケートでは「具体的な疑問点が解消された」といった声が寄せられ、セミナー参加者からも前向きな反応が増えています。日常会話においても「お金のことが気になっていた」「どうしたらいいか分からなかった」という従業員が、積極的に質問してくれるようになりましたし、当部門への問い合わせも増えました。3つ目は、動画コンテンツの活用です。アルファ・ファイナンシャル社は金融教育の分野での実績があり、提供される情報の正確性と質に安心感があります。また、さまざまな切り口からのアプローチは、社内展開のヒントとなっています。このように、確実に従業員の認知度と関心が高まっていることを実感しています。
土屋氏:プロジェクト全体としても、前進していると感じています。1年目は「最初の一歩を踏み出してもらう」ことに注力し、セミナーでは専門的な内容は最小限に抑えるように工夫しました。具体的には、当社従業員がアルファ・ファイナンシャル社のFPに相談する様子を配信したり、実際に資産運用を始めた社員の体験談を共有したりしています。このようにさまざまな形式のコンテンツを配信し、従業員の関心を高める工夫をしています。
ーー マネソル+(マネソルプラス)を使って新たに発見された課題があればお教えください。
土屋氏:広く社内に浸透させていくことの難しさを実感しています。金融の知識やリテラシーは、目の前で困らない限り、なかなか自発的な行動につながりません。しかし、一度金融教育に関心を持った従業員が、自ら積極的に学ぼうとする姿勢が見られたことが印象的でした。このように自発的な行動の変化が起きる点は、大きなメリットだと感じています。
多様な働き方の実現と自律的なキャリア支援へ!10年で変わる職場文化

ーー今後の貴社の福利厚生および従業員ウェルビーイングの動きについてお教えください。
土屋氏:福利厚生に関する施策は、時代の変化に合わせて柔軟に見直していく必要があると考えています。特に重視しているのは、従業員が安心して長く働ける環境づくり、いわゆる「就業期間の長期レンジ化」です。具体的には、従業員が必要に応じて休暇を取得できる、あるいは仕事のペースを調整できる制度の充実さです。育児休業や時短勤務の期間延長など、一時的にペースダウンしても働き続けられる選択肢を増やしています。仮に、家庭の事情で一度退職しても、状況が改善して復職を希望する場合、再度キャリアを積みやすくなっています。以前は、一度キャリアを中断すると復帰が難しいという風潮がありました。多様な働き方を受け入れる文化が、この10年で社内に根付いてきているように感じています。
松永氏:働き方が多様化し、キャリアが長期化する中で、従業員一人ひとりが自身の将来設計を立てることが不可欠になってきています。以前は、一つの働き方を続ければ、年齢に応じて決まった給付を受けられる時代でした。しかし、現在はさまざまな分岐点があり、財形貯蓄や保険など、リスクに備えた計画を自分で設計する必要があります。このような環境の中で、会社としては従業員が自身のライフプランを設計できる力を身につけられるよう、環境を整えていくことが重要だと考えています。
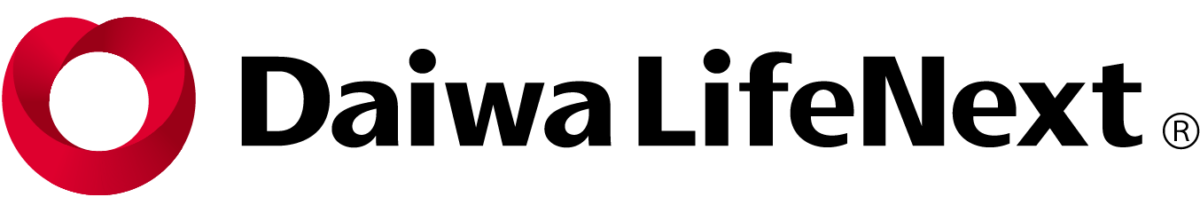 大和ライフネクスト株式会社
大和ライフネクスト株式会社
大和ハウスグループの一員として、マンション・ビルなどの管理運営事業を展開する企業。全国約28万戸のマンションを管理する業界大手で、従業員数は約8,400名(2025年1月時点)です。管理事業を通じて、安心・快適な住環境の提供を目指しています。


