住宅ローンを組む際、「年収の何倍まで借りられる?」「どの程度の返済額が現実的なの?」など、不安を抱えることも多いでしょう。
今回は、年収ごとの借入可能額や無理のない返済比率の目安、夫婦の収入合算やペアローンの活用方法などについて解説します。
【最新金利】おすすめの人気住宅ローンを徹底比較!金利・手数料・優遇が良いのは?
住宅ローンは年収の何倍くらいが目安?
住宅ローンの借入可能額は、審査基準の一部である「返済負担率」によって決まります。
返済比率とは、年収に占める年間の借金返済額の割合のことで、年収500万円の人が1年間に100万円を返済しているなら「返済比率は25%」です。
住宅金融支援機構が示す基準では、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下が理想です。
この基準をもとに、金融機関が審査を行い借入可能額を算出します。
借入可能額を試算する際は、年収×返済負担率で算出した年間返済額をもとに検討すると良いでしょう。
下記は年収別の目安となる借入可能額の一覧表です。
ただし、実際の借入可能額は、物件の価値や頭金の額・返済期間や利用者の信用度などにより変わります。あくまでも目安として理解しておきましょう。
【例:年収ごとの借入目安(35年返済と仮定した場合)】
| 年収 | 返済比率 | 年間返済額 | 毎月の返済額 | 借入可能額の目安 (金利手数料込み※) |
|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 30% | 105万円 | 87,500円 | 3,675万円 |
| 500万円 | 35% | 175万円 | 145,800円 | 6,125万円 |
| 700万円 | 35% | 245万円 | 204,100円 | 8,575万円 |
| 900万円 | 35% | 315万円 | 262,500円 | 1億1,025万円 |
年収で借入可能額をシミュレーションする際は手取りではなく額面
住宅ローン審査では、手取りではなく額面年収(総支給額)を基準に計算します。
給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」、個人事業主の場合は確定申告書の「所得金額」が基準です。
「手取り額で計算すべきでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、手取り額を基準にすると、控除の多い少ないで借入可能額が変わってしまいます。
そのため、金融機関では公平性を保つために、手取りではなく額面年収をもとに審査が行われるのが通常です。
住宅ローンを組む際は、単純に「年収の何倍まで借りられるか」を基準に考えるのではなく、毎月の生活費や将来の支出を考慮し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
子どもの教育費や親の介護費用など、将来的に大きな支出を想定し借入額を抑えておくと良いでしょう。
金融機関の審査基準をクリアできるからといって、最大限の借入をしてしまい、後々の生活が苦しくなるケースも少なくありません。
返済負担率ギリギリのローンを組んだあと、収入が減少したり予想外の出費が増えたりして、返済が厳しくなる事例もあります。
「いくら借りられるか」よりも、「いくらなら無理なく返せるか」を軸に考えることが、住宅ローンを成功させるポイントといえるでしょう。
住宅ローンの返済額は毎年いくらが現実的?
住宅ローンの返済額を決める際には、年収に対する返済比率を基準に考えるのが一般的です。
多くの金融機関では、「年収400万円未満なら30%以下」「年収400万円以上なら35%以下」を目安としています。
しかし、これはあくまでも借入可能な最大の返済負担率で、実際には無理のない範囲で計画することが重要です。
教育費や老後資金、車の買い替えなどの大きな支出が発生する可能性を考慮すると、実際には20%~25%程度の返済負担率でローンを組むほうがいいでしょう。
手取り年収の何%がベスト?返済比率の目安
実際に無理なく返済できる住宅ローンの割合は、手取り年収の20%~25%以内が理想です。
生活費や貯蓄、その他の支出を考慮したうえで、余裕をもって返済を続けられるかどうかを見極めましょう。
以下の表では、年収ごとの無理のない返済額の目安を示しています。
【無理なく返済できる年間・月々の返済額目安】
| 年収 (額面) | 年収 (手取りの目安) | 総返済額 (年収の20%) | 毎月の返済額 (年収の20%) |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 約320万円 | 80万円 | 約67,000円 |
| 600万円 | 約480万円 | 120万円 | 約100,000円 |
| 800万円 | 約620万円 | 160万円 | 約133,000円 |
| 年収 (額面) | 年収 (手取りの目安) | 総返済額 (年収の25%) | 毎月の返済額 (年収の25%) |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 約320万円 | 100万円 | 約83,000円 |
| 600万円 | 約480万円 | 150万円 | 約125,000円 |
| 800万円 | 約620万円 | 200万円 | 約167,000円 |
年収やライフプラン・家族構成によっても、住宅ローンの適正な返済額は大きく異なります。
同じ年収でも、貯蓄の有無や支出のバランスによって借入可能額は変わってくるため、画一的な基準で判断するのは危険です。
例えば、年収500万円の夫婦で子どもがいる場合なら、教育費や生活費が増えることを想定し、あえて返済比率を低めに抑えたほうがよいかもしれません。
返済比率を20%程度に設定し、余裕を持った資金計画を立てることができれば、リスクも最小限に抑えられます。
また、現在の収入を基準にローンを組んでしまうと、収入が減少した際に返済が困難になるケースがあります。
転職や病気などで収入が減るリスクも考慮し、余裕を持った返済計画を立てましょう。
年間返済額を抑えるためのコツ
住宅ローンの返済額を抑えるには、いくつかの方法があります。
最も基本的なのは、頭金を増やし借入額そのものを減らす方法です。また、低金利の住宅ローンを選択することも検討しましょう。
変動金利型の住宅ローンは当初の金利が低く、毎月の支払い負担も軽減できますが、将来的な金利上昇リスクも考慮する必要があります。
返済期間を延ばすことで、毎月の返済額を低く抑える方法もあります。
最近では50年ローンといった超長期の住宅ローン商品も登場しています。しかし、返済期間を延ばすとその分利息の支払い総額が増えるため、結果的に総支払額が大きくなります。
余裕がある場合は、繰り上げ返済を活用し、元本を早めに減らすように努めましょう。
その一方で、繰り上げ返済を急ぐよりも「余剰資金を資産運用に回す」という選択肢もあります。
どの方法を選ぶかは、自身のライフスタイルや将来設計をもとに考えましょう。
【金利予想】変動金利と固定金利の違い・メリット・デメリット|今後住宅ローンの金利はどうなる?
住宅ローンは夫婦の収入合算やペアローンも可能
共働き世帯では、収入合算やペアローンを利用する方法もあります。
どちらも借入額を増やせるメリットがありますが、将来のライフプランによる影響も考慮が必要です。
収入合算とペアローンの違い
住宅ローンを借りる際、夫婦や親子の収入を組み合わせる方法として収入合算とペアローンがあります。どちらも借入可能額を増やせる手段ですが、それぞれ特徴が異なります。
- 申込者本人の収入に、配偶者や親族の収入を合算する方法
- 契約者は1人で、合算者は連帯保証人または連帯債務者になる
- 金融機関によっては、「配偶者の収入の50%しか合算できない」など、収入の割合が制限される場合もある
- 契約者が単独でローンを管理できるため、所有権を単独にしたい場合や、ペアローンのように契約を2本作る手間を避けたい場合に適している
【収入合算が向いている人】
- 単独での借入額が希望の金額に届かない人
- 育休や転職で合算者の収入が減る可能性がある人
- 住宅の所有権を分けたくない人
- 夫婦や親子がそれぞれ住宅ローン契約を結ぶ方法
- 各契約者が互いに連帯保証人となり、双方が住宅ローン控除を受けられるメリットがある
- ペアローンは、収入が高いパートナーと低いパートナーが適切な比率で負担を分けられるため、公平な持分を考えている場合や、相続対策を考えている場合に向いている
- ただし、契約が2本になるため、事務手数料や保証料が2倍かかる点には注意が必要。
【ペアローンが向いている人】
- 夫婦・親子ともに安定した収入がある人
- 住宅の持分を公平に分けて所有したい人
- 相続税対策を考慮したい人
最近では、事実婚や未婚のカップルでもペアローンを利用できる金融機関が増えており、選択肢の幅が広がっています。
【保存版】住宅ローン控除の仕組み・条件・申請方法を完全解説!最新の法改正でどうなった?
収入合算やペアローン利用時のメリット・デメリット
収入合算やペアローンには、それぞれメリットとデメリットがあり、状況に応じて慎重に選ぶ必要があります。
収入合算を利用する最大のメリットは、契約者1人の収入では希望額に届かない場合でも、収入合算で借入額を増やせる点です。
また、契約者を1人にしておくことで住宅ローンの管理がしやすいというメリットもあります。
一方、収入合算のデメリットは、合算者が連帯保証人または連帯債務者になる点です。万が一、契約者が支払い困難に陥った場合、合算者が責任を負わなければなりません。
また、離婚など合算者との関係が悪化した際には、住宅ローンの負担が問題になる可能性があります。
ペアローンのメリットとしては、夫婦や親子それぞれが住宅ローン控除を受けられることが挙げられます。
単独でローンを組むよりも税制上の優遇を受けやすく、団体信用生命保険(団信)に加入できれば、どちらか一方に万一のことがあっても、団信で完済されるのが大きな利点です。
ペアローンのデメリットは「手数料が高くつく」点です。事務手数料や保証料が2倍かかるため、初期費用の負担が大きくなる点には注意しましょう。
また、どちらかの収入が減少した場合には、もう一方の負担が増え、家計に影響を与えるリスクもあります。
離婚や別居時には住宅の所有やローンの返済をどうするかが大きな問題となるため、慎重に検討する必要があります。
住宅ローンの審査には年収以外の項目もある
具体的な審査項目は非公開ですが、最低限住宅ローンの審査で見られるポイントについては理解しておきましょう。
住宅ローンの審査では、年収だけでなく信用情報・勤続年数・雇用形態・物件の担保価値・健康状態なども重視されます。
【元融資担当者が解説】住宅ローンの審査はどこを見られる?通過率をアップさせるためのポイント
信用情報
住宅ローンの審査では、申込者の信用情報が厳しくチェックされます。これは、過去の借入履歴や支払い状況を確認し、返済能力を判断するためです。
信用情報機関(CICやJICCなど)に登録されている情報には、クレジットカードやカードローンの利用履歴、返済状況、延滞の有無、債務整理(自己破産や任意整理)の履歴などが含まれます。
スマホの分割払いもローンの一種とみなされるため、未納や延滞があると住宅ローンの審査に影響が出るかもしれません。
審査に通りたいなら、ローンやカードは期日までに返済し、不要なクレジットカードや使っていないカードローンは解約しましょう。
勤続年数・雇用形態
金融機関は、申込者の収入が安定しているかどうかを確認するため、勤続年数や雇用形態もチェックします。
一般的には、勤続1年以上が審査通過の条件で、3年以上の勤務実績があると信用度がアップします。
転職直後だと審査に不利になる場合がありますが、同業種への転職であれば収入の安定性が認められ、審査ではプラスに働くことも多いでしょう。
また、雇用形態も重要なポイントです。正社員は審査が通りやすいですが、契約社員や派遣社員、フリーランス・個人事業主の場合は、安定した収入を証明することが必要です。
特に個人事業主やフリーランスは直近2年分の確定申告書を求められるため、収入の波が大きいと審査が厳しくなります。
審査に通りたいなら、「転職を予定している場合は、審査が終わるまで待つ」、フリーランスであれば「収入を安定させ、確定申告書を適正に申告する」といったことを意識しましょう。
契約社員や派遣社員で働いているなら、同じ会社で長く働いている実績を示すと有利になります。
物件情報
購入予定の不動産価値も重要な要素です。
金融機関は、万が一返済不能になった場合に備えて、物件を売却して回収できるかどうかを判断します。
そのため、担保評価の高い物件ほど審査が通りやすく、大きな額も借りられるでしょう。
特に新耐震基準(1981年以降)を満たした物件や、流通性の高いエリアにある物件は高評価です。
一方で、再建築不可物件や借地権付きの物件は担保評価が低くなり、融資額が減額される可能性があります。
さらに、違法建築(建ぺい率・容積率オーバー)や、市街化調整区域にある物件は、そもそも融資対象外となるケースもあるため注意しましょう。
審査を通過しやすくするには、担保評価が高い物件を選ぶことが重要です。
新築や築浅物件は評価が高く、中古物件でも耐震補強済みのものやリノベーション済みのものは評価が上がる可能性があります。
購入予定の物件が金融機関の基準に適合しているか、事前に相談しておくのもおすすめです。
健康状態
住宅ローンの審査では、申込者の健康状態も重要なチェック項目です。
ほとんどの金融機関では、団体信用生命保険(団信)への加入が融資の条件となっており、加入できない場合は基本的にローン契約はできません。
団信の審査では、既往歴や現在の健康状態がチェックされます。
高血圧や糖尿病などの持病がある場合、保険に加入できないことがあり、その場合は団信なしで利用できる住宅ローンを検討する必要があります。
また、常用している薬がある場合、薬の種類によっては団信の審査に影響を与えるため注意しましょう。
住宅ローンにかかる頭金や諸経費
住宅ローンを利用する際には、頭金や諸経費についても計算しておきましょう。頭金を増やすことができれば、毎月の返済負担は軽くなります。
一方で、印紙税や登記費用、保証料や火災保険料までをローンで支払うのは難しく、自己資金で支払わなければならないケースがほとんどです。
事前に必要な金額を把握し、無理のない資金計画を立てるようにしましょう。
【保存版】住宅ローンを借りる流れは?申込〜融資までにすること・必要書類・気をつけるポイントを専門家が解説
頭金は物件価格の10~20%が理想
住宅ローンを組む際の頭金は、物件価格の10〜20%程度を入れるのが理想です。例えば、5,000万円の物件を買うのであれば、1,000万円の頭金を準備しておきましょう。
また、金融機関の審査でも頭金があるほうが返済比率が改善し、承認されやすくなることが多いです。
ただ、最近の住宅ローンは、頭金を用意しなくても利用できるケースがほとんどです。そのため、必要以上に頭金にこだわる必要はないのかもしれません。
返済負担を下げたいなら、頭金を無理に入れるよりも資金が余剰した際に繰上げ返済する方法もあります。
頭金を無理に入れすぎると、手元資金が不足するリスクも発生します。
想定外の支出が発生した際に、フリーローンやカードローンを利用せざるを得なくなる可能性があるため、慎重に判断することが重要です。
印紙税
住宅ローン契約時には、金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼付する必要があります。
この印紙税は借入額によって異なり、例えば1,000万円超~5,000万円以下で2万円、5,000万円超~1億円以下で6万円ほどがかかります。
住宅ローン実行時に必要な、「抵当権設定登記にかかる登録免許税」にも注意しましょう。(債権額の0.4%)
ただし、印紙税や登録免許税は住宅ローンの借入金には含められないため、自己資金で支払わなければいけません。
所有権移転登記や保存登記にも別途費用が発生するため、金融機関には「諸経費がいくらかかるのか?」を事前に確認してくと良いでしょう。
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁、No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
手数料・保証料
金融機関への手数料や、保証会社に支払う保証料も必要です。手数料は金融機関ごとに異なりますが、3〜5万円程度はかかります。
一方、保証料は借入額や審査結果に応じて変動し、例えば一括払いの場合は数十万円単位になることもあります。
- 一括支払い(外枠方式):契約時に一括で支払う
- 毎月払い(内枠方式):金利に上乗せされる
手数料や保証料は金融機関によって異なるため、借入時に事前に確認し、諸経費を含めた資金計画を立てることが重要です。
各種公的書類取得費
住宅ローンの申込時や契約時には、さまざまな公的書類の取得が必要となります。
これらの書類は役所で発行されるため、発行手数料がかかります。課税証明書や所得証明書、印鑑証明書、住民票を取得する際の手数料も想定しておきましょう。
- 所得証明書・課税証明書:300円~500円程度
- 印鑑証明書・住民票:300円~500円程度(自治体による)
火災保険料
住宅ローンを組む際には、火災保険への加入が必須となるケースがほとんどです。
これは、万が一の火災時に住宅を再建できるようにするためであり、金融機関としても貸し倒れリスクを回避する目的があります。
- 補償範囲:火災・落雷・風災・水害など
- 契約期間:最長10年(保険会社による)
- 費用:建物の構造や所在地によって異なる
なお、保険料は一括払いが基本で借入金には含まれないため、自己資金で準備しなければいけません。
補償内容や契約年数によって保険料が異なるため、複数の保険会社を比較して選ぶと良いでしょう。
【最新金利】住宅ローンの借り換えにおすすめのタイミングと注意点
住宅ローンの年収倍率についてよくある質問
住宅ローンを検討する際の、「年収倍率の目安」や、「年収別の借入可能額」、「審査基準」など、よくある疑問についてもお答えしていきたいと思います。
年収400万円や500万円の場合はいくらまで借りられる?
住宅ローンの借入可能額は、年収に対する返済比率と完済時の年齢によって決まります。
年収400万円の場合、理想の返済比率は35%で、35年ローンだと「約4,900万円が理論上の上限額」です。
年収500万円なら、35年ローンで約6,125万円の借入が可能です。
ただし、実際の借入可能額は金利や金融機関の審査基準によって変わります。
年収でシミュレーションする際は「手取り?」それとも「額面?」
住宅ローンのシミュレーションは「額面年収」で行います。
給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」、個人事業主は確定申告書の「所得金額」が基準です。
実際の返済計画を考える際は、生活費や貯蓄を考慮し、手取り額でシミュレーションするのも一つの方法ですが、ローン審査ではあくまでも額面年収が判断基準となることを理解しておきましょう。
共働きなら年収合算は可能?注意点は?
共働き世帯では、収入合算やペアローンを活用することで借入可能額を増やせます。
収入合算では、配偶者が連帯保証人または連帯債務者となり、ローン契約は1本です。
一方、ペアローンは夫婦それぞれが債務者となり、2本のローンを組みます。
収入合算では、合算できる収入に制限がある場合があり、ペアローンでは審査基準が厳しくなることもあるため注意しましょう。
将来的な収入の変動やライフイベントを考慮し、どの方法が適しているか慎重に選ぶ必要があります。
頭金0円でも年収倍率通り借りられる?
頭金がなくても、年収倍率の範囲内で住宅ローンを組むことは可能です。
金融機関によっては頭金なしで全額借入できる商品もあり、自己資金が少なくても住宅を取得できるケースも多いでしょう。
ただし、頭金を用意すると借入額を抑えられ、審査も有利に進めてもらえます。
また、住宅取得には物件価格以外にも諸費用がかかるため、最低でも諸費用分は自己資金でまかなえるよう準備しておきましょう。
住宅ローンを組む時は「年収倍率」と「返済比率」を意識するのが重要
住宅ローンの借入額は年収倍率、返済比率や手取り額、共働きの収入合算など多くの要素で決まります。
住宅ローンを組む際は、単純に「年収の何倍まで借りられるか?」という単純な考え方ではなく、将来の収入変動やライフプランを見据え、慎重に検討するようにしましょう。

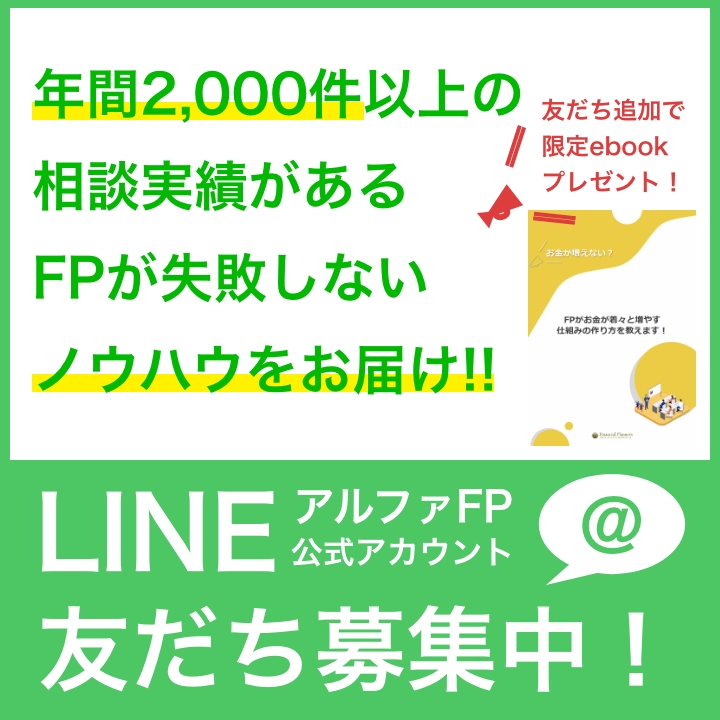

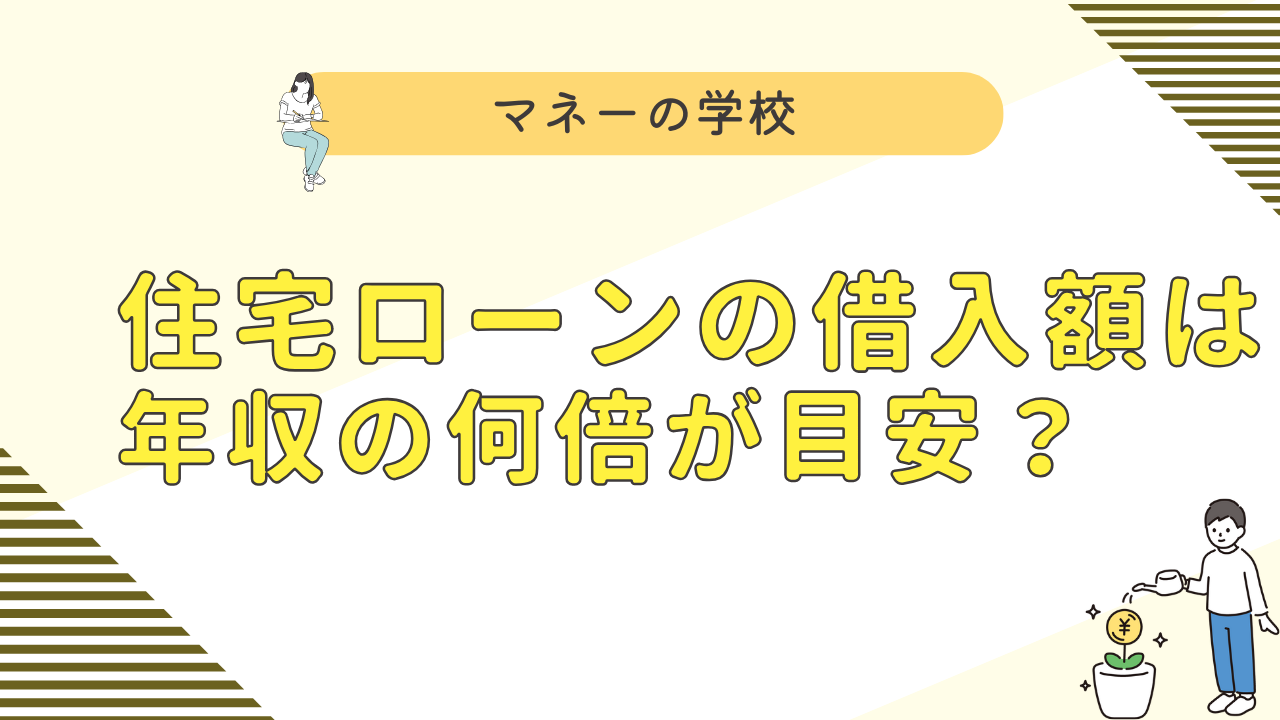

みんなの口コミ