2025年以降、住宅ローンの変動金利はどう推移するのでしょうか?
日銀の金融政策や経済情勢の変化により、「金利が上昇するのでは?」という意見も多いようです。
住宅ローンの契約を控えている方のなかには、固定金利との差が縮まることで「変動金利と固定金利どちらを選ぶべきか?」と、迷うケースも多いでしょう。
今回は、2025年4月以降の変動金利がどうなるのか、経済情勢や金融機関の動向を踏まえ専門家が解説します。
変動金利のリスクや固定金利との比較、金利上昇時の対策についても詳しくご紹介しますので、これから住宅ローンを組む方はぜひ参考にしてください。
【最新金利】おすすめの人気住宅ローンを徹底比較!金利・手数料・優遇が良いのは?
住宅ローンの金利が変動する要因
住宅ローンの金利は、さまざまな要因によって変動します。特に、変動金利と固定金利では影響を受ける要因が異なります。
変動金利は、主に日銀の政策金利に連動し、短期的な市場の動きにも敏感です。
一方で、固定金利は長期国債の金利や金融機関の戦略によって決まるため、景気やインフレ動向に左右されやすい傾向があります。
住宅ローン金利変動の要因1:「長期国債(日本国債10年物)金利」
固定金利型住宅ローンのなかでも、特に全期間固定型の金利は、日本国債(10年物)をはじめとする長期国債の金利に大きく影響を受けます。
これは、長期国債の金利が長期金利の代表的な指標であり、将来の経済動向や物価変動を織り込んだ市場の期待が反映されるためです。
例えば、景気が好調で物価が上昇すると、長期国債の利回り(=金利)が上昇し、金融機関の資金調達コストが増加します。それにより、住宅ローンの固定金利も引き上げられるのです。
逆に、景気が低迷し金融緩和政策が継続されると長期国債の金利が低下し、固定金利の住宅ローンも低水準で推移するケースが一般的です。
固定金利で住宅ローンを組む際は、長期国債の金利動向を注視することが重要です。
特に、金利が低いタイミングでは、固定金利を選択することで長期的に安定した返済計画を立てることが可能になります。
参考:財務省「国債金利情報」
住宅ローン金利変動の要因2:「日銀の政策金利」
住宅ローンの変動金利は短期プライムレートを基準としていますが、この短期プライムレートは日銀の政策金利に強く影響を受けます。
「短期プライムレート」とは、金融機関が企業に対して短期間の資金を貸し出す際の最優遇金利のことで、これが住宅ローンの変動金利の基準となっています。
日銀が政策金利を引き上げると、金融機関の資金調達コストが増加、それに伴い短期プライムレートが上がり、変動金利住宅ローンの金利も上がる仕組みです。
逆に、政策金利が低下すると、短期プライムレートも下がり、変動金利の住宅ローンは低水準が維持されるでしょう。
特に、日銀の金融政策の方向性が重要なポイントです。景気を刺激するための低金利政策が続けば、変動金利も低く抑えられます。
しかし、インフレ抑制のために利上げが行われると、変動金利の上昇リスクは高まるでしょう。
変動金利で住宅ローンを組む場合は、日銀の政策金利の動向をこまめにチェックし、金利上昇に備えた返済計画を立てることが重要です。
参考:日本銀行「金融政策」
住宅ローン金利変動の要因3:「銀行の戦略」
銀行は日銀の政策金利の動向を踏まえながら、住宅ローンの金利を調整しています。
政策金利が引き上げられると、銀行の調達コストが上昇するため、変動金利も上がるでしょう。
一方、政策金利が据え置かれたり引き下げられたりした場合は、競争力を維持するために低金利が維持されるケースがほとんどです。
銀行は「利ざや(貸出金利と調達金利の差)」を拡大することで収益向上を図ります。
しかし、他行との競争が激しくなると、住宅ローンの金利を引き下げて、顧客を獲得する戦略に切り替える可能性は高いでしょう。
一方で、金利上昇局面では、収益確保のために変動金利を段階的に引き上げる可能性もあります。
銀行ごとに戦略は異なるため、住宅ローンを検討する際は複数のローンを比較し、より有利な条件で借りられる銀行を選ぶことが重要です。
三菱UFJ銀行など大手5銀行は4月から、変動型の住宅ローンの基準金利を引き上げる。既存の契約者らが対象で、上げ幅は0.25%程度で調整している。
日銀の1月の利上げを受け、各行は変動型の住宅ローンなどの貸出金利の指標となる短期プライムレート(短プラ)を引き上げているため反映させる。
日本経済新聞「変動型の住宅ローン金利、4月上昇へ 大手行0.25%程度」
直近の金利政策とそれによる住宅ローン金利の変動
2025年4月現在、日本の金利政策は転換期を迎えているといえます。
日銀の金融緩和修正や政策金利の調整により、短期プライムレートが上昇すれば、変動金利型の住宅ローン金利も上昇する可能性があります。
一方、長期国債の金利上昇により、固定金利型の住宅ローン金利も注視する必要があるでしょう。
日銀の金融緩和と住宅ローン金利との関係
日銀の金融緩和政策が入ると、金融機関は低金利で資金を調達できるため、企業や個人向けの貸出金利は下がります。
その結果、住宅ローンの金利も引き下げられ、借りやすい状況が続くでしょう。
ただ、現在は金融緩和により住宅ローン金利が低い状況が続いていますが、必要以上に借りすぎないよう注意が必要です。
金融政策の転換によって金利が上昇する可能性があるため、住宅ローン契約時には無理なローンを組まないよう、慎重に検討しましょう。
住宅ローンの変動金利は今後どうなる?
住宅ローンの変動金利は、日銀の政策金利や短期プライムレートの影響を受けて低水準を維持していますが、今後の利上げ次第ではわかりません。
景気回復や物価上昇により短期プライムレートが引き上げられると、金融機関も変動金利を上げてくるでしょう。
今後も「変動金利の優位性」は継続する見込
固定金利との比較だけを考えると、変動金利は今後も引き続き優位性を保つでしょう。
ちなみに、固定金利が変動金利より低くなるには、日銀が5回以上の利上げを行う必要があります。2025年1月時点では、変動金利が1.8%、固定金利が0.4%であり、その差は1.4%です。
日銀が過去に実施した政策金利の引き上げは一度に0.25%ずつであったため、この差を埋めるには5回の利上げが必要となるでしょう。
しかし、短期間での連続利上げは考えにくく、当面は変動金利の優位性が続く見通しです。
金利の動向は今後も不透明なため、日銀の金融政策に注目し金利動向を定期的に確認することが重要です。
専門家の見通し2025年のシナリオ
2025年3月18日から19日にかけて開催された日本銀行の金融政策決定会合では、政策金利を現行の0.5%程度に据え置くことが全会一致で決定されました。
会合後の声明では、「国内経済は一部に弱めの動きも見られるものの、緩やかに回復している」と評価されています。
日銀は3月19日まで開いた金融政策決定会合で、政策金利を0.5%程度に据え置くことを決めました。
NHK「日銀 3月の金融政策決定会合 “利上げ積極検討を”などの意見」
また、消費者物価(生鮮食品を除く)の前年比上昇率は、政府によるエネルギー負担緩和策の縮小もあって、足もとは3%台前半です。
これらの状況を踏まえ、日本銀行は引き続き経済・物価動向を注視し、適切な金融政策運営に努める方針を示しています。
なお、今回の会合では追加の利上げは見送られましたが、今後の経済指標や国際情勢の変化によっては、政策の見直しが行われる可能性もあります。
住宅ローンの利用を検討しているなら、引き続き日本銀行の金融政策や経済指標の動向に注目することが重要です。
住宅ローンの変動金利が上昇した時に検討すべきこと
変動金利が上昇すると、住宅ローンの返済負担が増加します。
金利の上昇幅によっては、家計に大きな影響を及ぼす可能性があるため、早めの対策が必要です。
借り換えや繰上げ返済の検討、家計の見直しなど、適切な対応をとればリスクも抑えられるでしょう。
住宅ローンの借り換え
金利が上昇した時は、低金利のローンへ借り換えることで、返済負担を軽減できる場合があります。
例えば、現在の借入残高が1,000万円で金利2%、残り返済期間が10年のケースでは、1%の金利に借り換えることで毎月の返済額が92,013円から87,604円に減少し、総返済額も約53万円節約できます。
ただし、借入残高が1,000万円未満では借り換えメリットが小さく、手数料負担が返済軽減額を上回るケースが多いため注意しましょう。
また、木造住宅の場合は返済開始から11年を経過すると担保評価が下がり、審査が厳しくなる可能性もあります。
借り換えを検討する際は、建築時期と残返済期間、そして手数料を見ながら慎重に検討することが重要です。
【最新金利】住宅ローンの借り換えにおすすめのタイミングと注意点
繰上げ返済で元本を圧縮する
繰上げ返済をすれば、金利負担を軽減し総返済額を減らせます。
特に、短期の固定金利特約型の終了時や、変動金利の上昇が見込まれるタイミングで行うと効果的です。
例えば、現在の借入残高3,900万円・金利2%・残り返済期間15年の住宅ローンで、1,000万円を繰上げ返済すると、毎月の返済額は約65,000円削減できます。
ただし、金融機関によっては繰上げ返済手数料が発生するため、事前に確認が必要です。
【保存版】住宅ローン控除の仕組み・条件・申請方法を完全解説!最新の法改正でどうなった?
家計やライフプランの見直し
住宅ローンの金利が上昇した際には、家計の見直しができる点がないか、確認してみましょう。
光熱費や通信費などの固定費を見直し、必要のない保険の解約や安いプランへの切り替えを検討すると、支出を抑えられる場合があります。
特に生命保険については、住宅ローンの団信と重複した保障になっている可能性もあるため、団信内容と生命保険の死亡保障の内容を、よく確認してみましょう。
変動金利の5年ルールと125%ルールとは?
変動金利の住宅ローンには、急激な返済額の増加を防ぐために「5年ルール」と「125%ルール」が設けられています。
それぞれ、どのような制度なのか詳しく見ていきましょう。
5年ルールや125%ルールができた理由
変動金利型住宅ローンでは、急激な金利上昇による返済負担の増加を防ぐために、「5年ルール」と「125%ルール」が導入されています。
これは、大蔵省(現・財務省)が1983年に定めた指針に基づくもので、住宅ローン利用者の生活を守るために設けられた制度です。
特に125%ルールは、長期的な金利上昇局面において、借り手の急激な負担増を抑える目的があります。
日本は欧米と異なり長らく低金利政策が続いてきたため、大幅な金利上昇時に返済不能者が増えることを懸念して作られました。
参考:国土交通省資料「前回検討会における質問事項について」民間金融機関の変動金利の返済ルール
変動金利5年ルールの仕組み
変動金利の5年ルールとは、たとえ金利が上昇しても、5年間は毎月の返済額が据え置かれる仕組みのことです。
貸付金利は半年ごとに見直されますが、返済額の変更は5年ごとに行われるため、急激な金利上昇の打撃を受けることはありません。
しかし、この仕組みには注意が必要です。適用金利が上昇すると、毎月の支払いのうち利息の割合が増え、元本の返済が進みにくくなります。
結果として、5年後の見直し時に「元本があまり減っていない」というリスクがあるのです。
5年ルールの恩恵を受ける場合でも、繰上げ返済を活用するなどして、元本を計画的に減らしていくことが重要になります。
変動金利125%ルールの仕組み
125%ルールとは、金利が上昇した場合でも、返済額がこれまでの125%を超えないよう制限される仕組みのことです。
たとえば、毎月の返済額が10万円だった場合、見直し後の上限は12万5,000円となり、それ以上の増額はありません。
しかし、このルールにも落とし穴もあります。金利が上昇しても返済額が一定の上限内に抑えられるため、返済額の多くが利息に充てられ、元本の減少が遅れる可能性が高くなります。
これが長期間続くと「未払い利息」として残債が増え、最終的な支払総額が膨らむ可能性があるのです。
また、125%ルールはすべての金融機関で適用されるわけではなく、一部のネット銀行ではこのルールを採用していない場合もあります。
住宅ローンを契約する際には、金融機関ごとのルールを事前に確認することが重要です。
住宅ローンの変動金利がおすすめな人
変動金利型の住宅ローンは、どのような人におすすめなのか詳しく見ていきましょう。
変動金利は、金利の低さが魅力ですが、将来的な金利上昇リスクも伴います。
変動金利を選ぶべきかどうかは、収入の安定性や返済計画によって判断する必要があるでしょう。
【元融資担当者が解説】住宅ローンの審査はどこを見られる?通過率をアップさせるためのポイント
返済資金に余裕のある人
変動金利は、家計に余裕のある人に適しています。共働き夫婦など、収入源が複数ある家庭なら、金利上昇時にも柔軟に対応できるため安心です。
とはいえ、片方の収入が減少したり、予期せぬ出費が発生するリスクもあるため、変動金利を選ぶ場合は余剰資金を確保しておくと良いでしょう。
就業不能保険や所得補償保険への加入も検討し、万が一の事態への備えも大切です。
短期間で返済できる人
住宅ローンを短期間で返済できるなら、変動金利の低金利メリットを活かしやすいでしょう。
なぜなら、短期間で完済できるのであれば、金利変動リスクを受ける期間が短くなり、トータルの支払利息も抑えられるからです。
ただし、病気や突発的な収入源が発生した場合は返済不能に陥るリスクもあるため、ある程度の余剰資金を用意しておくことも大切です。
金利動向を見続けられる人
変動金利は、金利の動向に左右されるため、経済ニュースや市場の変化を日常的にチェックできる人に向いています。
物価の上昇や景気の動向・為替レートの変化などをよくチェックできるのであれば、適切なタイミングで繰上げ返済や借り換えもできるでしょう。
【保存版】住宅ローンを借りる流れは?申込〜融資までにすること・必要書類・気をつけるポイントを専門家が解説
住宅ローンの固定金利・フラット35がおすすめな人
次に、固定金利やフラット35の利用が向いている人についても見ていきます。
固定金利やフラット35は、毎月の返済額が一定で計画を立てやすいため、今後大きな出費を控えている人や、長期間の安心して返済を続けたい人に向いています。
リスクを避けたい人
固定金利は、毎月の返済額を一定に保ちたい人や、市場金利の変動リスクを避けたい人におすすめです。
将来の金利上昇による返済負担の増加を心配しているなら、少々金利が高くても安心できる固定金利が良いでしょう。
固定金利型の住宅ローンは、市場金利が上がっても返済額は変わらないため、教育資金や車の買い替え資金などが必要になった際でも安心です。ただし、固定金利型住宅ローンの貸付金利は、変動金利よりも高めに設定されています。
住宅ローンの金利タイプを選ぶ時は、「安定を優先するか?」「変動金利のリスクを取るか?」など、自身の考え方やライフプランに応じて慎重に検討しましょう。
借入額が大きい人
借入金額が大きい人は、固定金利の住宅ローンがおすすめです。
変動金利は金利が低く設定されているため魅力的に見えますが、金利が上昇すると毎月の返済額も増え、大きな負担となる可能性があります。
特に、数千万円単位のローンを組んでいる場合、金利が1%上がるだけでも総返済額は数百万円単位で増えるため注意が必要です。
その点、固定金利なら契約時に返済額が確定するため、将来の金利変動を気にせず長期的な資金計画も立てやすくなります。
金利動向を見続けられない人
金利の変動を常にチェックするのが難しい人には、固定金利の住宅ローンがおすすめです。
変動金利は定期的な金利見直しがあり、金利動向を注視しながら、適切なタイミングで借り換えや繰上げ返済を検討しなければいけません。
忙しくて金利情報をこまめにチェックできない人や、金利変動に一喜一憂したくない人は、固定金利の方が安心です。
住宅ローンの変動金利まとめ
住宅ローンの変動金利は、低金利の情勢が続けば魅力的ですが、将来的な金利上昇リスクは注視する必要があります。
ただ、金利が上がったとしても5年ルールや125%ルールがあるため、急激に返済額が増えることはないでしょう。
「固定金利か?」「変動金利か?」で悩んでいるなら、中長期的なライフプランや、自分自身が金利変動のリスクを許容できるかどうかを考え、慎重に比較検討しましょう。

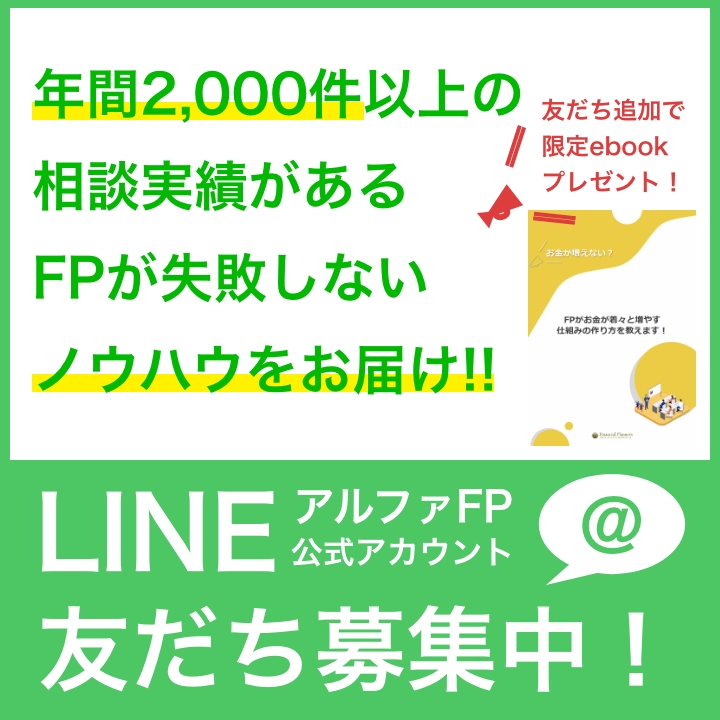

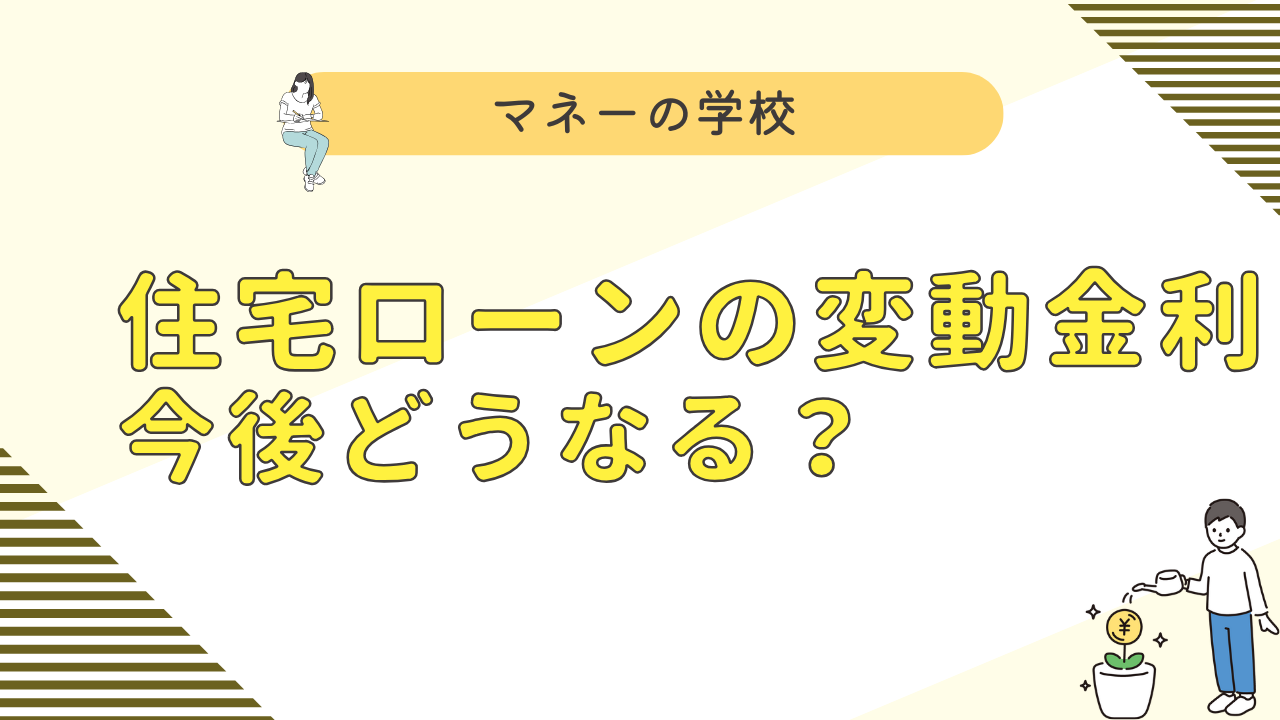

みんなの口コミ