住宅価格の高騰が続くなか、「年収300万円で家を買う」となると、どの程度の額まで住宅ローンを組めるのか不安になる方も多いでしょう。
無理なく住宅ローンを組んで返済していくためには、「年収倍率」や「返済比率」を考える必要があります。
今回は、年収300万円の人が買える住宅の価格と借入可能額の考え方、そして収入合算やペアローンの活用法などについて解説します。
【最新金利】おすすめの人気住宅ローンを徹底比較!金利・手数料・優遇が良いのは?
年収300万円で借りられる住宅ローン額|年収倍率や返済負担率から考える
年収300万円で住宅ローンを組む場合の「借入可能額」は、年収倍率や返済負担率をもとに算出されます。
まずは、年収倍率や返済比率の定義や、年収300万円の人の適切な借入額、理想的な月々の返済額から見ていきましょう。
住宅ローンの審査で重視される「年収倍率」
年収倍率とは、「年収に対して何倍の住宅ローンを借りられるかを示す指標」で、金融機関は審査を行う際に年収倍率を重要な指標の一つとしています。
年収倍率は、一般的に年収の3〜5倍が理想とされていますが、実際の審査では購入物件の種類や自己資金の有無、住宅ローン以外の負債によっても違ってきます。
また、住宅ローンを組む際は、年収倍率だけでなく返済負担率(年収に占める年間返済額の割合)も合わせて考える必要があるでしょう。
ちなみに、年収倍率の目安として、フラット35の調査では「土地付き注文住宅は約7.6倍」「マンションは約7.2倍」とされています。中古物件は新築よりも倍率が低く、「中古マンションが5.6倍」「中古戸建は5.3倍」が目安です。
年収倍率を考えた場合、年収300万円の方が借りられる借入可能額の目安は以下の通りとなります。
- 土地付注文住宅:約2,280万円
- マンション:約2,160万円
- 注文住宅:約2,100万円
- 建売住宅:約1,980万円
- 中古マンション:約1,680万円
- 中古戸建:約1,590万円
理想的な返済負担率(返済比率)
住宅ローンを契約する際は、返済負担率も考える必要があるでしょう。
返済負担率は別名「返済比率」とも呼ばれ、年収に対する年間のローン返済額の割合を示す指標のことです。
年収が低いほど負担率の上限は低く設定され、年収400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下で考えるとよいでしょう。
年収300万円の場合、適正な返済負担率は30%以下(年間90万円以内、月額7.5万円以内)ですので、「年間90万円の返済を何年続けるか?」で計算すると、借入可能額を算出できます。
フラット35の審査で見られる年収倍率や返済負担率のポイント
フラット35の審査でも、「年収倍率」と「返済負担率」の両方がチェックされます。
一般的に、フラット35の審査では年収倍率6~7倍程度が目安とされ、年収300万円の場合の借入可能額は1,800~2,100万円となるケースがほとんどです。
審査基準で年収倍率より重視されるのは返済負担率で、フラット35では年収400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下が基本ルールです。
ちなみに、無理のない返済を考えるなら、返済負担率を20%程度に抑えるのが理想です。
返済負担率を20%に設定すると、年間返済額は60万円(月5万円)以内になり、教育費や介護費用などの出費がかさんだとしても安心できるでしょう。
なお、机上計算だけでは住宅ローンの借入可能額は把握しにくいため、インターネット上のローンシミュレーターを活用するのがおすすめです。
【年収倍率】住宅ローンの借入額は年収の何倍が目安?適切な借入額と返済額は?
年収300万円の場合に現実的に買える住宅と毎月の返済額
年収300万円の場合、購入できる住宅の価格や毎月の返済額は、借入可能額と返済負担率によって決まります。
無理のない返済を考えるなら、借入額は2,000万円前後、毎月の返済額は5~7万円程度が目安です。
金利や返済期間によっても支払総額は変わりますが、具体的な計算例をもとに、現実的に購入できる住宅の価格や毎月の返済額の目安について見ていきましょう。
年収300万円の人が借りられる住宅ローンの目安
年収300万円の場合の借入可能額は、返済負担率を基準に算出すると良いでしょう。
金融機関では、年収400万円未満の人の返済負担率を30%以下とするケースが一般的です。そのため、年収300万円の人が年間に返済できる額は、300万円×30%=最大90万円(毎月7.5万円)が目安となります。
借入可能額は金利によって変動します。例えば、金利2%なら約2,200万円、金利1%なら約2,600万円が借入の上限です。
- 金利2%の場合:借入可能額2,200万円(年間返済額87.4万円・返済比率29.2%)
- 金利1%の場合:借入可能額2,600万円(年間返済額88.0万円・返済比率29.4%)
年収300万円の人が頭金無しで借りられる額と毎月の返済額
年収300万円で頭金なしの場合、借入可能額は金利と返済負担率によって決まります。下記は、返済負担率を30%以下で考えた場合の借入可能額の目安です。
- 変動金利0.5%:最大2,800万円(毎月72,684円)
- 固定金利2.0%:最大2,200万円(毎月72,878円)
ただし、将来的なリスクを考えると、ある程度の頭金(自己資金」を用意するのが理想です。
下記の表で必要な頭金と毎月の返済額の目安を整理しましたので、こちらも参考にしてください。
【物件価格別の頭金と毎月の返済額※35年返済の場合】
| 物件購入額 | 固定金利2.0% 返済負担率29.2% 借入可能額2,200万円 | 固定金利1% 返済負担率29.4% 借入可能額2,600万円 | 変動金利0.5% 返済負担率29.1% 借入可能額2,800万円 | |||
| 自己資金 | 毎月返済額 | 自己資金 | 毎月返済額 | 自己資金 | 毎月返済額 | |
| 3,000万円 | 800万円 | 72,878円 | 400万円 | 73,394円 | 200万円 | 72,684円 |
| 3,500万円 | 1,300万円 | 900万円 | 700万円 | |||
| 4,000万円 | 1,800万円 | 1,400万円 | 1,200万円 | |||
年収300万円の場合夫婦での収入合算やペアローンを組む方法も検討すべき
夫婦で住宅ローンを組むことを考えているなら、収入合算やペアローンの利用も検討してみましょう。
収入合算やペアローンを活用すれば、借入可能額を増やせます。
ただし、それぞれメリットデメリットがあるため、自身のライフスタイルや将来的なリスクも考え、慎重に検討することが重要です。
収入合算とペアローンの違い
「収入合算」と「ペアローン」は、それぞれ特徴が異なるため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
収入合算は、主債務者の収入に配偶者や親の収入を加算し、1本の契約でローンを組む方法です。一方、ペアローンは夫婦それぞれが主債務者となり、2本のローン契約を結びます。
【収入合算とペアローンの違い】
| 契約形態 | 収入の扱い | 連帯責任 | 借入可能額 | 控除 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収入合算 | 1本のローン | 主債務者の収入に合算(通常は1/2程度) | 合算者は連帯保証人または連帯債務者になる | 合算できる割合に制限あり | 主債務者のみ |
| ペアローン | 2本のローン | それぞれの収入を個別に計算 | 互いに連帯保証人になる | 収入を全額考慮できるため、より多く借りられる | 双方に適用 |
収入合算は、手続きが比較的簡単で諸費用も抑えられますが、合算者は団体信用生命保険(団信)に加入できず、住宅ローン控除も利用できない点がデメリットです。
ペアローンは、双方が団信に加入でき、それぞれ住宅ローン控除を受けられるメリットがあります。その一方で、契約が2本になるため手続きや諸費用が増える点に注意が必要です。
また、ペアローンの場合はローンの負担割合に応じて住宅の持分登記を行う必要があり、離婚や収入の変化があった際の調整が難しくなることもあります。
【保存版】住宅ローン控除の仕組み・条件・申請方法を完全解説!最新の法改正でどうなった?
年収300万円の場合は変動金利と固定金利のどちらが良いか
年収300万円の方が住宅ローンを組む際、変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきかは、返済計画やリスク許容度によって異なります。
安定した返済を重視するなら固定金利、低金利の恩恵を受けたいなら変動金利を選びましょう。
変動金利と固定金利の違い
変動金利は金利が低く設定されるため、短期的な返済負担が軽くなりますが、金利が上昇すると支払い額が増えるリスクがあります。
一方、固定金利は契約時の金利が変わらず、長期的な資金計画が立てやすいですが、変動金利に比べて総返済額が高くなる可能性があります。
| 特徴 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 変動金利 | 一定期間ごとに金利が見直される | 政策金利など大きな変更がない限り低金利で利用できる | 金利上昇の局面では返済額が増える |
| 固定金利 | 契約時の金利は一定期間固定 | 返済額が一定で長期的な資金計画が立てやすい | 変動金利より手数料が高くつくケースが多い |
将来の金利上昇リスクを避けたい場合は固定金利、現在の低金利を活かして、少しでも支払いを抑えたい場合は変動金利が適しているでしょう。
特に年収300万円の場合は、無理のない返済計画を立てるのがポイントです。ライフプランや金利変動リスクを考慮しながら、慎重に検討しましょう。
【金利予想】変動金利と固定金利の違い・メリット・デメリット|今後住宅ローンの金利はどうなる?
年収300万円の人におすすめな金利形態
年収300万円の場合、収入が今後も大幅に増える見込みがないなら、固定金利が無難かもしれません。
固定金利を選択すれば、金利上昇の影響を受けずに毎月の返済額が一定で済むため、年収が少なくても家計管理がしやすいでしょう。
変動金利を選ぶと、金利が上昇すれば返済額も増えるため、返済負担が増えるリスクを想定しておく必要があります。
- 固定金利:安定した返済計画を立てたい場合に適している。
- 変動金利:当面の金利が低いため返済負担を軽減できるが、将来的な金利上昇リスクを考慮する必要がある。
ただし、将来的に一括返済や借り換えを予定しているなら、変動金利を活用して低金利の恩恵を受けるという選択肢もあります。
相続財産の活用や、ボーナスによる繰上げ返済が見込めるなら、変動金利で契約しておいて様子を見るのもひとつです。
年収300万円の人にフラット35がおすすめな理由
年収300万円の人が住宅ローンを利用する際は、変動金利よりフラット35がおすすめです。
【フラット35をおすすめする理由】
1.審査基準が柔軟
民間の金融機関に比べ、勤続年数や雇用形態の審査が比較的緩やか。収入が安定していれば、審査に通る可能性も高い。特に、非正規雇用や個人事業主の方は利用しやすいのが特徴。
2.金利が全期間固定で安心
フラット35は借入時の金利が固定されるため、将来的に市場金利が上昇しても、影響を受けることはない。年収が低めの人にとっては、リスクを最小限に抑えることができるためおすすめ。
3.住宅の担保価値を重視してくれる
フラット35は、個人の信用情報よりも住宅の担保価値を重視する傾向がある。年収300万円でも、優良物件を選べばローンが組めるケースも多い。
ただし、フラット35の金利は民間の変動金利よりも高めに設定されているため、少しでも支払利息を抑えたいという方には不向きです。
年収300万円で住宅ローンを申し込む際に審査を通りやすくするためのコツ
住宅ローンを申し込む際は、審査通過率を上げるために「審査で見られるポイント」を理解しておくことが重要です。意外な理由で審査に落ちるケースもあります。
特に、信用情報や現在契約しているクレジットカード・カードローンについては、注意しておきましょう。
属性で注意すべきポイント
住宅ローンの審査では、申込者の信用情報や勤務先の安定性など、「申込者の属性」が重要な判断基準となります。
信用情報にクレジットカードやローンの延滞履歴、過去の債務整理の履歴があると、審査で不利になるケースがほとんどです。
特に3ヵ月以上の長期延滞履歴があると、信用情報機関に「異動情報」として記録され、完済しても5年間は審査通過が難しくなります。また、スマートフォンの分割払いの延滞も審査に影響を与えるため、注意しましょう。
勤務先や勤続年数も重要なポイントです。金融機関は、安定した収入を持つ正社員を好む傾向があり、勤続年数が1年以上あれば、審査通過率は高くなります。
契約社員や派遣社員でも、勤務実績が長ければ審査の対象となる場合がありますが、審査のハードルは正社員より高いでしょう。また、転職後1年未満の方は審査が厳しくなる可能性があるため、転職前に住宅ローンを検討するのがおすすめです。
勤務先や勤続年数で気になる点があるならば、まずは金融機関窓口に相談してみましょう。なんらかの解決案を提示してくれる場合もあります。
審査に通りやすい金融機関や不動産会社を選ぶ
住宅ローンの審査に通るためには、金融機関選びも重要です。金融機関ごとに審査基準が異なり、実際のところ「審査が厳しい金融機関」と、「比較的緩やかな金融機関」が存在します。
例えば、大手都市銀行は厳しい審査を行いますが、地方銀行やネット銀行は柔軟な審査をするケースが多いです。
フラット35のような公的融資制度も、民間の銀行と異なる基準で審査を行うため、審査は通りやすいでしょう。
また、銀行と提携している不動産業者を選べば、審査通過率を上げられるケースがあります。
金融機関は不動産会社に土地購入の事業融資を行うことがあり、その関係で、販売した住宅のローンについても同一金融機関と提携するケースがあるのです。不動産会社を通じて金融機関に申込むことができれば、書類の準備や手続きもスムーズに進むでしょう。
金融機関は、良好な関係を築いている不動産会社からの紹介案件に限り直接融資を行う場合もあるため、審査を有利に進めたいなら、直接金融機関に申込むより不動産会社を通すのが得策です。
年収300万円でも住宅ローン審査に通った例
実際に、年収300万円でも住宅ローンの審査に通った例を見てみましょう。実際の住宅ローン審査では、個人信用情報機関の登録内容に問題がなく、返済負担率さえ合致していれば年収はあまり影響しません。
金融機関も「身の丈に合った物件を購入すればいい」という考え方のため、条件さえ整えば年収300万円でも審査通過は可能です。
- ある30代の会社員は、2,500万円の住宅を希望していましたが、現状の年収だけを考えると希望額の借入が難しい状況でした。
- そこで、自己資金として500万円を用意し、借入額を2,000万円に抑えました。
- これにより、返済負担率が基準内に収まり、金融機関の審査を通過しました。
- 共働き世帯の事例では、夫婦で収入合算を利用し審査に通ったケースがあります。
- 夫の年収が300万円、妻の年収が200万円だったため、合算後の年収は500万円となり、返済負担率の基準を満たすことで希望額の借入が可能になりました。
- 親からの住宅取得資金の贈与を活用し、自己資金を増やして審査を通過した事例もあります。
- 親からの支援を受けることで、借入額を減らし、返済負担率を抑えたことで審査が有利に進みました。
年収300万円で住宅ローンを借りる場合は慎重に計画する必要がある
年収300万円で住宅ローンを組む場合、毎月の返済額や将来のライフプランを考慮し、慎重な計画が必要です。無理のない返済額を設定し、教育費や老後資金の確保も視野に入れましょう。
また、金利の変動リスクや収入減少の可能性を考え、固定金利の選択や一定の貯蓄を持つことも大切なポイントです。
ライフプランを考え無理のない返済プランを考える
住宅ローンを組む際には、返済負担率だけを基準にせず、長期的なライフプランを考慮することが重要です。
年収300万円の場合は、返済負担率30%以内が理想ですが、これを上限いっぱいまで設定すると教育費や老後資金の確保が難しくなる可能性があります。
無理なく返済したいなら、返済負担率は20%程度に抑え、残りを貯蓄や投資に回すなどして将来のリスクにも備えましょう。
特に、子どもがいる家庭では、養育費が大きな負担となります。学費や習い事、大学進学資金などの支出を見積もったうえで、どれくらいの住宅ローンを組むべきかを慎重に検討する必要があります。
住宅ローンを組む際は「いくら借りられるか?」ではなく、「将来も無理なく返せる金額はいくらか?」を考えることが重要です。
金利の変動リスクにも注意する
住宅ローンは長期間の返済が前提となるため、金利の動向によって返済総額が大きく変わる可能性があります。
変動金利を選択すると、当初の返済額は低く抑えられますが、経済状況の変化に伴い金利が上昇すれば毎月の返済額も増加します。
現在のように低金利が続いている状況では、今後の金利上昇リスクを考慮しながら、慎重に選択する必要があるでしょう。
住宅ローンを組む際には、借り換えや一括返済の選択肢を持ちながら、リスクを分散させることが大切です。はじめは変動金利で契約し、「金利上昇局面になったら固定金利へ借り換える」といった戦略もおすすめです。
収入減少リスクも考慮する
住宅ローンの返済期間中に、収入が減少するリスクにも注意しなければいけません。
転職や失業、病気・ケガによる長期休業、勤務先の業績悪化による給与減少など、予測できない事態になることも少なくないでしょう。共働き世帯では、育児や介護によって一時的に収入が減少する可能性もあります。
これらのリスクに備えるためには、無理のない返済計画を立てることが重要です。
たとえば、返済負担率を30%ではなく20~25%程度に抑え、急な収入減少があった場合でも生活に支障が出ないようにするのが理想です。また、一定の生活防衛資金を確保し、万が一の事態にも対応できるよう準備しておきましょう。
年収300万円で住宅ローンを組む時によくある質問
最後に、年収300万円の方が住宅ローンを組む際によくある疑問や、注意点について解説します。
年収300万円の50代ですが住宅ローンは組めますか?
50代でも住宅ローンは組めますが、年齢や返済期間の制限があるため慎重な計画が必要です。
多くの金融機関では完済年齢を80歳までと設定しているため、50代で借りる場合は最長30年程度のローンが限界でしょう。
リタイア後も返済が続くリスクがあるため、自己資金を増やし借入額を抑えることも検討しましょう。また、団体信用生命保険(団信)への加入が必要となるため、健康状態が審査に影響を及ぼす点にも注意しなければいけません。
年収300万円で頭金無しで住宅ローンを組むのは危険ですか?
頭金なしで住宅ローンを組むことは可能ですが、リスクは高いでしょう。借入額が増えることで総返済額が大きくなり、毎月の負担も重くなります。
特に変動金利を選択した場合、金利上昇の影響を受けやすく、将来的に返済額が増加する点には注意が必要です。
住宅購入後には固定資産税や維持費も発生するため、ローン返済以外の支出も考慮しなければなりません。
リスクを抑えるためには、物件価格を抑えたり、諸費用分の自己資金を確保するのが望ましいでしょう。
年収300万円の住宅ローン控除はいくらですか?
住宅ローン控除は、年末時点のローン残高に対して適用されますが、2025年度の控除率は0.7%です。例えば、年末時点のローン残高が2,000万円の場合、年間で最大14万円の所得税控除が受けられます。控除しきれなかった分は翌年度の住民税から控除されますが、その上限は9.75万円です。
「新築か中古か?」、または「省エネ基準を満たしているか?」によっても控除額の上限は異なるため、国税庁の公式サイトなどで、詳細を確認しておきましょう。
【住宅ローン控除】
| 種類 | 年末残高限度額 | 控除期間 | 控除率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新築 | 認定(長期優良・低炭素)住宅 | 4,500万円 | 13年 | 0.7% |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | |||
| 中古 | 認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 10年 | |
| その他の住宅 | 2,000万円 |
年収300万円の40代でも審査に通った事例はありますか?
年収300万円の40代でも、住宅ローンの審査に通る例はあります。
住宅ローンの審査では、年収よりも返済負担率が重視されるため、基準内であれば年齢を理由に否決されることはほとんどありません。
「頭金を用意して借入額を抑える」、「共働きなら収入合算を活用する」、「長期間の固定金利を選択して金利上昇リスクを回避する」といった方法を取れば、借入も可能でしょう。
年収300万円で住宅ローンを組むなら頭金の用意がポイント
年収300万円でも住宅ローンを利用してマイホームを購入することは可能ですが、慎重な計画が必要です。
夫婦での収入合算やペアローンを活用すれば、借入額を増やせますが、リスクも伴います。
年収が低い場合は、親からの援助や貯蓄を利用し、できるだけ頭金を入れるよう検討してみましょう。

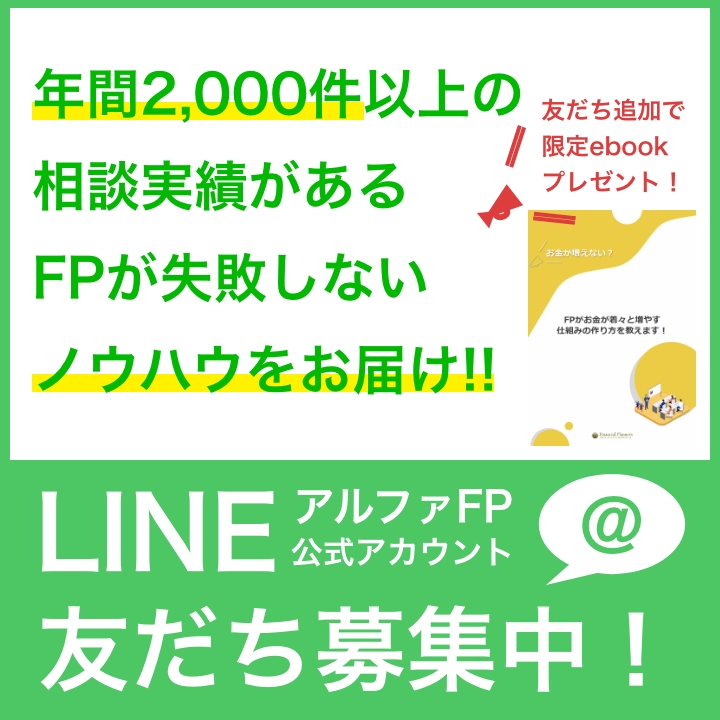

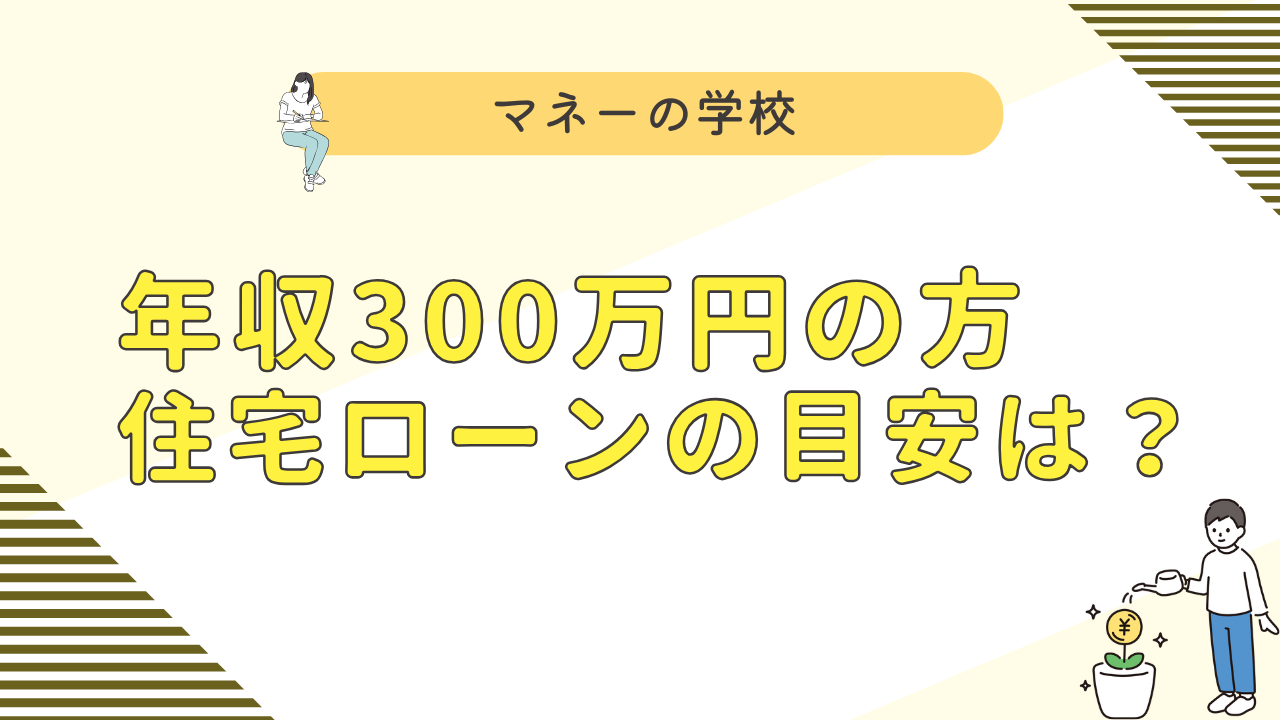

みんなの口コミ